数値気候モデルによる20世紀の気候再現実験について
- 20世紀における地球の平均地上気温の変動要因を推定
近年の昇温傾向は人間活動に因ると示唆 -
|
平成16年11月5日 国立大学法人東京大学 気候システム研究センター 教授 住 明正 教授 木本 昌秀 独立行政法人国立環境研究所 主任研究員 野沢 徹 主任研究員 江守 正多 独立行政法人海洋研究開発機構 地球環境フロンティア研究センター グループリーダー 江守 正多(兼任) |
波学園都市記者会同時発表)
要旨
国立大学法人東京大学気候システム研究センター(CCSR)、独立行政法人国立環境研究所(NIES)、独立行政法人海洋研究開発機構地球環境フロンティア研究センター(FRCGC)の合同研究チームは、地球全体の大気・海洋を計算する数値モデルを用いて、20世紀において観測された地球の平均地上気温の変化を再現することに成功した。この計算では、従来の計算では考慮されてこなかった様々な気候変動要因を最大限考慮している。様々な要因を切り分けて計算を行った結果、近年(20世紀最後の30年程度)の昇温傾向は人間活動に伴うものであることが強く示唆された。一方、20世紀前半(1910〜45年ころ)の昇温傾向は自然起源の気候変動要因に因ることが示唆された。今後の解析により、気温以外の量についてもさらなる知見が得られることが期待される。
なお、本研究は環境省の地球環境研究総合推進費及び文部科学省の人・自然・地球共生プロジェクト等の研究費により実施された。
国立大学法人東京大学気候システム研究センター(CCSR)、独立行政法人国立環境研究所(NIES)、独立行政法人海洋研究開発機構地球環境フロンティア研究センター(FRCGC)の合同研究チームは、地球全体の大気・海洋を計算する数値モデルを用いて、20世紀において観測された地球の平均地上気温の変化を再現することに成功した。この計算では、従来の計算では考慮されてこなかった様々な気候変動要因を最大限考慮している。様々な要因を切り分けて計算を行った結果、近年(20世紀最後の30年程度)の昇温傾向は人間活動に伴うものであることが強く示唆された。一方、20世紀前半(1910〜45年ころ)の昇温傾向は自然起源の気候変動要因に因ることが示唆された。今後の解析により、気温以外の量についてもさらなる知見が得られることが期待される。
なお、本研究は環境省の地球環境研究総合推進費及び文部科学省の人・自然・地球共生プロジェクト等の研究費により実施された。
1.背景
観測事実によれば、20世紀の100年間で地球の平均気温は約0.6度上昇しており、最近では、世界の各研究機関でコンピュータによる20世紀の気候再現実験が行われている。このような計算では、温室効果気体の増加など、観測された様々な気候変動要因をモデルの外から与えている。従来は、情報が不足していたため、重要と考えられる気候変動要因の一部しか考慮されてこなかったが、今回、不足している情報を収集・整備し、人間活動に伴って排出される煤などの炭素性エアロゾルの増加や、土地利用変化など、現状で考えられるほぼすべての気候変動要因を考慮した、20世紀の気候再現実験を行うことが可能となった。
2.計算の概要
モデルは大気が300km、海洋が100km程度の、世界的にも標準的な解像度のものを用いた。計算は20世紀を含む過去150年間に対して行った。ここで考慮した気候変動要因は以下の8つである。
(1) 太陽エネルギーの変動
(2) 大規模火山噴火に伴い成層圏にまで到達したエアロゾルの変化
(3) 温室効果気体(二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、ハロカーボン)濃度の増加
(4) 1970年代半ば以降の成層圏オゾン濃度の減少
(5) 人間活動に伴う対流圏オゾン濃度の増加
(6) 工業活動に伴う二酸化硫黄(硫酸エアロゾルの元物質)排出量の増加
(7) 人間活動に伴う煤などの炭素性エアロゾル排出量の増加
(8) 土地利用変化
上記のうち、(1)〜(2)は自然起源の気候変動要因、(3)〜(8)は人為起源の気候変動要因である。観測された平均地上気温の変動要因を推定するために、人為起源のみ、自然起源のみなど、気候変動要因を切り分けた場合の計算も行った。
3.再現実験結果
すべての気候変動要因を考慮した場合(図1最上段)、モデルは20世紀に観測された気温変動、すなわち、20世紀前半(1910〜1945年ころ)や近年(20世紀最後の30年程度)の昇温傾向を非常によく再現していた。これに対して、一切の気候変動要因を考慮しなかった場合(図1最下段)には、観測されたような気温変動は全く再現されなかった。
4.近年の昇温傾向について
観測に見られる1970年以降の著しい昇温傾向については、人間活動に伴う気候変動要因のみ考慮した場合(図1第2段)にはよく再現されているが、自然起源の気候変動要因のみ考慮した場合(図1第3段)には全く再現できていない。このことから、近年の温暖化傾向は人間活動に伴う気候変動に起因することが強く示唆された。人為的な気候変動要因は、温室効果気体の増加に伴う温暖化と、対流圏エアロゾルの増加に伴う寒冷化とに大別されるが、前者が後者を大きく上回るために、昇温傾向が顕在化していると考えられる。
5.20世紀前半の昇温傾向について
観測では20世紀前半の1910〜1945年ころにも昇温傾向が見られるが、今回の計算によれば、人間活動に伴う気候変動要因のみ考慮した場合(図1第2段)にはほとんど再現されていない。一方、自然起源の気候変動要因のみ考慮した場合(図1第3段)には観測に近い昇温傾向が再現されており、20世紀前半の昇温傾向は自然起源の気候変動に起因することが示唆された。自然起源の気候変動要因は太陽エネルギーの変化と大規模火山噴火のみであり、両者の時間変化(図2下段)からは、20世紀前半の気温上昇には太陽エネルギーの増加が大きく寄与しているであろうと想像される(図2下段の1910〜1950年付近)。しかし、太陽エネルギーの変化のみ考慮した場合(図2中段)には、観測に見られるような昇温傾向は再現されなかった。19世紀終盤から20世紀初頭にかけては火山活動が活発な時期であったため(図2下段の1885〜1915年付近)、地球の平均地上気温もやや低温傾向であったが、それが回復しはじめた頃とほぼ同時期に太陽エネルギーが増加しはじめたため(図2下段の1910〜1950年付近)、両者の重ね合わせにより、観測に見られるような昇温傾向が得られたと考えられる。
(補足)
IPCC第3次評価報告書(2001年)においても、数値気候モデルを用いて、20世紀後半の昇温傾向は人間活動に因ること、20世紀前半の昇温傾向は自然起源の気候変動に起因する可能性のあること、が指摘されていたが、当時の計算では、いくつかの重要なプロセスや気候変動要因を考慮していなかった。今回の計算では、それらの問題点を改善し、現状で考えられるほぼすべての気候変動要因を考慮しているため、従来の知見の信頼性をより高めることができた、と言える。
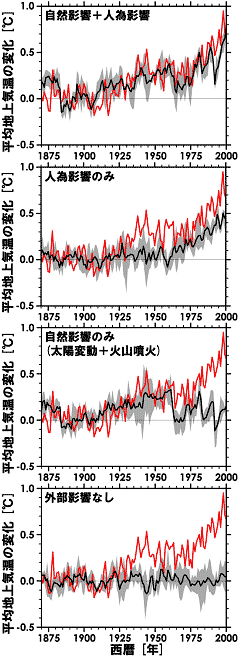 |
図1 全球年平均地上気温の時間変化。赤太線は観測値を、黒太線は計算結果(初期値の異なる4実験の平均)を示す。観測、モデルとも、1881〜1910年の平均気温を引いたもの。灰色の部分は初期値の異なる4実験結果のばらつきの範囲を示す。上段から、すべて(自然+人為)の気候変動要因を考慮した場合、人為起源の気候変動要因のみを考慮した場合、自然起源の気候変動要因のみを考慮した場合、一切の気候変動要因を考慮しない場合。20世紀最後の30年程度の昇温傾向は、人間活動に伴う気候変動を考慮しなければ再現できない。一方、20世紀前半(1910〜1945年頃)の昇温傾向は、自然起源の気候変動を考慮しなければ再現されないことが示唆される。 |
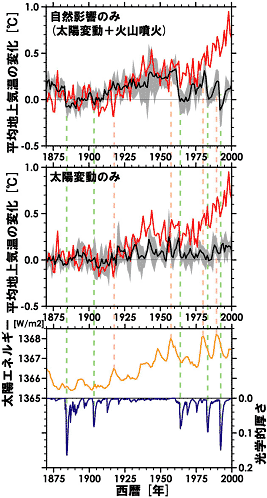 |
図2 上段:図1第3段に同じ。中段:太陽エネルギーの変化のみを考慮した場合。下段:モデルに与えた自然起源の気候変動要因の時間変化。黄色線は太陽エネルギーの変化を、青線は大規模火山噴火に伴い成層圏まで到達したエアロゾルが地表面を冷やす効果を表す。両者は違う物理量を示しているため、その大きさを直接比較できないことに注意が必要。この結果から、20世紀前半(1910〜1945年頃)の昇温傾向は太陽エネルギーの増加のみでは説明できず、火山噴火による寒冷傾向からの回復と太陽エネルギーの増加に伴う緩やかな昇温との重ね合わせに因るものであると考えられる。 |
問い合わせ:
国立大学法人東京大学気候システム研究センター
柏地区駒場事務分室研究協力係 担当:三浦
Tel:03-5453-3953 Fax:03-5453-3964 URL:http://www.ccsr.u-tokyo.ac.jp/
独立行政法人国立環境研究所
企画・広報室 担当:田邉
Tel:029-850-2303 Fax:029-851-2854 URL:http://www.nies.go.jp/
独立行政法人海洋研究開発機構
地球環境フロンティア研究センター 担当:太田
Tel:045-778-5687 Fax:045-778-5497 URL:http://www.jamstec.go.jp/frcgc/jp/
総務部普及・広報課 担当:五町
Tel:046-867-9066 Fax:046-867-9055 URL:http://www.jamstec.go.jp/