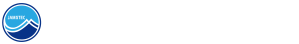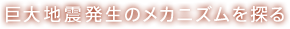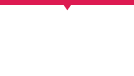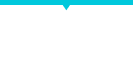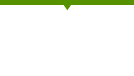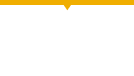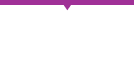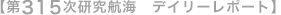

12.18, 2007
Day: 33
天候:半晴
サイト:C0002 (NT3-01) (33°18’ N, 136°38’ E)
乗船研究者は掘削孔Dで採取したコアで物性の測定と間隙水の分析を行いました。また、サイトC0002の成果をとりまとめるためのミーティングを行い、各研究グループが解析結果を報告しました。このサイトで採取したコアは4つの岩相に分類され、熊野海盆堆積物からなるユニットと付加体のユニットとは構造、化学組成、物性等が明らかに異なることが観察されました。

12.17, 2007
Day: 32
天候:半晴
サイト:C0007 (NT1-03) (33°01’ N, 136°47’ E)
乗船研究者はサイトC0002のレポートを作成し、採取したコアの土質評価と計測を続けています。

12.16, 2007
Day: 31
天候:半晴
サイト:C0002 (NT3-01) (33°18’ N, 136°38’ E)

12.15, 2007
Day: 30
天候:半晴
サイト:C0002 (NT3-01) (33°18’ N, 136°38’ E)

12.14, 2007
Day: 29
天候:半晴
サイト:C0002 (NT3-01) (33°18’ N, 136°38’ E)

12.13, 2007
Day: 28
天候:満天雲
サイト:C0002 (NT3-01) (33°17’ N, 136°38’ E)
乗船研究者の約半数が下船し、次の第316次研究航海の研究者と交代しました。掘削孔Bのコアで、X線CTスキャン等の計測と肉眼による記載を引き続き行っています。

12.12, 2007
Day: 27
天候:曇
サイト:C0002 (NT3-01) (33°17’ N, 136°38’ E)

12.11, 2007
Day: 26
天候:曇
サイト:C0006 (NT1-03) (33°01’ N, 136°47’ E)
乗船研究者は研究航海を総括するミーティングを行い、今後の研究航海計画や研究報告会の開催について議論しました。サイトC0002のコアの密度・質量計測や撮影、X線などの通常の計測と肉眼による記載、C0001のサンプルでのプラズマ質量分析計(ICP-MS)による分析も続いています。

12.10, 2007
Day: 25
天候:曇
サイト:C0002 (NT3-01) (33°17’ N, 136°38’ E)
乗船研究者は掘削孔Bのコアで、通常の計測と肉眼による記載を始めています。同じ深度の微化石年代を比較すると、サイトC0002の堆積物はサイトC0001のものよりかなり若い年代であることが分かりました。これらの作業と併行して、サイトC0001のコアから採取したサンプルで、プラズマ質量分析計(ICP-MS)によるヨウ素分析を行っています。研究航海のレポートについては、まず研究手法についての章を共同首席研究者と研究支援統括が査読しています。

12.9, 2007
Day: 24
天候:半晴
サイト:C0002 (NT3-01) (33°17’ N, 136°38’ E)

12.8, 2007
Day: 23
天候:半晴
サイト:C0002 (NT3-01) (33°17’ N, 136°38’ E)
乗船研究者は自然ガンマ線強度の再計測を完了し、無機炭素分析をしています。またプラズマ質量分析計(ICP-MS)を使い、岩石中の隙間に含まれる水の中の金属元素の分析を始めています。サイトC0001の終了にあわせてミーティングを開き、各グループから結果について報告がありました。海底下210 mの地点を境に大きな変化が起きていることが、いくつかの測定で確認されました。

12.7, 2007
Day: 22
天候:半晴
サイト:C0001 (NT2-03) (33°14’ N, 136°42’ E)

12.6, 2007
Day: 21
天候:半晴
サイト:C0001 (NT2-03) (33°14’ N, 136°42’ E)
コア・検層・地震反射波のデータ統合研究者は、コアの自然ガンマ線強度測定の結果と、前の航海(Expedition 314)の掘削同時検層(LWD)で取得したガンマ線のデータがよく一致することを確認しました。乗船研究者はセミナーを開き、Mike Underwood博士が南海トラフに沈み込んでいく物質について講演を行いました。

12.5, 2007
Day: 20
天候:半晴
サイト:C0001 (NT2-03) (33°14’ N, 136°42’ E)

12.4, 2007
Day: 19
天候:半晴
サイト:C0001 (NT2-03) (33°14’ N, 136°42’ E)
乗船研究者は、自然ガンマ線強度の測定を続けるとともに、コアから採取したサンプルを使ってP波速度と電気伝導度の測定をしています。これらの結果は前の航海で得られた検層データとよく一致しています。

12.3, 2007
Day: 18
天候:半晴
サイト:C0001 (NT2-03) (33°14’ N, 136°42’ E)
乗船研究者は、第314次研究航海で採取した掘削孔Bの土質評価用コアを含め、これまでに取得したコアからのサンプル採取を完了しました。また、コア採取時に機器の故障で計測できなかった自然ガンマ線強度の測定を再度行いました。船上で科学セミナーを開催し、乗船研究者の廣野哲郎さん(日本)とWen-Lu Zhuさん(アメリカ)が、台湾でのチェルンプ断層掘削の成果について紹介しました。

12.2, 2007
Day: 17
天候:半晴
サイト:C0001 (NT2-03) (33°14’ N, 136°42’ E)
乗船研究者は掘削孔E、F、Hで採取したコアから、各自の研究計画に基づくサンプル採取を完了しました。微化石研究者は、掘削孔EとFのサンプルで化石に基づく年代推定を行い、古地磁気分析に基づく年代推定との相関について議論を行いました。

12.1, 2007
Day: 16
天候:半晴
サイト:C0001 (NT2-03) (33°14’ N, 136°42’ E)
乗船研究者はレポートの作成に着手しています。同時に半割したコアから研究者各自の研究計画に基づくサンプルの採取を進めています。これまでは時間がかかる円柱状サンプルの採取を優先していましたが、コア採取を行っていない期間を利用して、航海の後半に予定していた半割したコアからのサンプル採取も予定を早めて実施しています。


11.30, 2007
Day: 15
天候:満天雲
サイト:C0001 (NT2-03) (33°14’ N, 136°42’ E)
研究ラボでの、コアの記載と各種データ計測は順調に進んでいます。科学支援技術者は半固結状態の岩石で薄片試料を作る方法を試し、非常に良いサンプルを作成しています。

11.29, 2007
Day: 14
天候:雨
サイト:C0001 (NT2-03) (33°14’ N, 136°42’ E)
乗船研究者は船内でコアの計測とサンプリングを続けています。悪天候のため、船体の振動は収まりませんが、コアのデジタル画像にノイズが出る問題は科学支援技術者の努力が実りかなり改善しました。通常の計測に加えて、ICP発光分光分析計や蛍光X線分析装置によりコア試料の元素組成の同定を行っています。
乗船研究者の何人かは悪天候で船が揺れるため船酔いしています。大きな船体の「ちきゅう」でも、やはり揺れるのです。

11.28, 2007
Day: 13
天候:雨
サイト:C0001 (NT2-03) (33°14’ N, 136°42’ E)
乗船研究者は、コア全体の計測を続ける一方で、半割したコアから各自の研究計画に基づくサンプルの採取を始めました。悪天候の影響で発生している振動が計測機器に悪影響を及ぼし、コアをスキャンしたデジタル画像にノイズが混じるようになり、再計測が必要となっています。構造地質の研究者グループは微小な断層の形状と古地磁気データから、過去の応力場を復元しようとしています。その他、共同主席研究者と研究支援統括から乗船研究者に今後の掘削作業予定について報告をしました。

11.27, 2007
Day: 12
天候:雨
サイト:C0001(NT2-03)(33°14’ N, 136°42’ E)

11.26, 2007
Day: 11
天候:曇
サイト:C0001(NT2-03)(33°14’ N, 136°42’ E)
乗船研究者は回転式掘削で得られたコアの各種データ計測と肉眼による記載を始めています。最初の2本のコアは掘削孔Fのコアと同じ深度から採取したコアでしたが、X線CT画像で確認したところ、回転式掘削で採取したコアの方が、伸縮式コア採取システム(ESCS)に比べて掘削による乱れが少ないことがわかりました。円柱状コアでの熱伝導率の測定が終了し、続いて半割後、小さくサンプリングをして各種物性の計測を始めています。構造地質のグループは科学支援技術者の協力を得て、断層や応力を受けた痕跡が見られる部分の岩石薄片を作成しています。また、CT画像中に見られる変形・切断面に着目し、画像データを精査しています。

11.25, 2007
Day: 10
天候:半晴
サイト:C0001(NT2-03)(33°14’ N, 136°42’ E)

11.24, 2007
Day: 9
天候:半晴
サイト:C0001(NT2-03)(33°14’ N, 136°42’ E)

11.23, 2007
Day: 8
天候:半晴
サイト:C0001(NT2-03)(33°14’ N, 136°42’ E)
乗船研究者はコアの各種データ計測、肉眼による記載をフル体制で続けています。また2箇所の掘削孔での比較も行っています。構造地質の研究者は、地層の変形構造の詳細な記載を行っています。

11.22, 2007
Day: 7
天候:半晴
サイト:C0001(NT2-03)(33°14’ N, 136°42’ E)

11.21, 2007
Day: 6
天候:半晴
サイト:C0001(NT2-03)(33°14’ N, 136°42’ E)
乗船研究者は採取したコアの分析処理、計測を続けています。

11.20, 2007
Day: 5
天候:曇
サイト:C0001(NT2-03)(33°14’ N, 136°42’ E)
コア試料中の堆積物がガスを含んでおり船上で膨張するため、切断時の基準の長さ(150cm)よりも、15 cmも長く(165cm)なったコアもありました。

11.19, 2007
Day: 4
天候:曇
サイト:C0001(NT2-03)(33°14’ N, 136°42’ E)
乗船研究者は、最初のコアサンプルが船上に回収されてくるのに備えて、分析・処理の準備に取りかかり、古地磁気研究者と古生物研究者は地層の年代決定のための基準について話し合いました。船上に回収したコアは手順に従って処理を進め、X線CTスキャナーにより良好な三次元コア可視化データを取得しています。また、地層の温度計測を2回目のコア採取時に実施し、高品質なデータの取得に成功しました。

11.18, 2007
Day: 3
天候:半晴
サイト:C0001(NT2-03)(33°14’ N, 136°42’ E)

11.17, 2007
Day: 2
天候:曇
サイト:C0001(NT2-03)(33°14’ N, 136°42’ E)

11.16, 2007
Day:1
天候:満天雲
サイト:C0001(NT2-03)(33°14’ N, 136°42’ E)