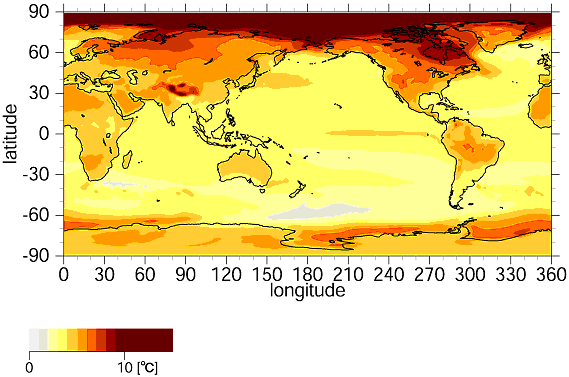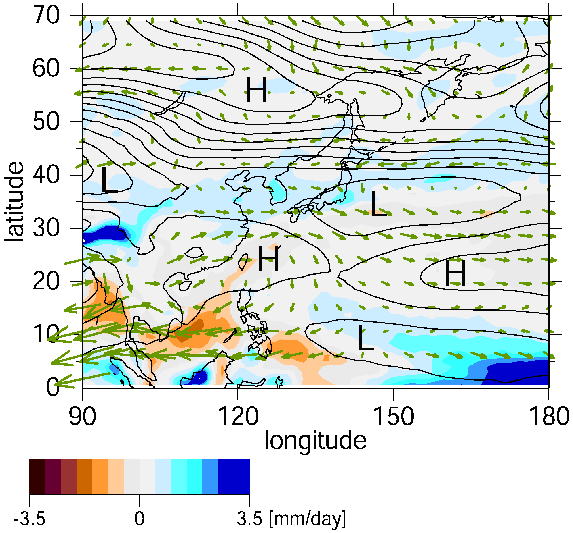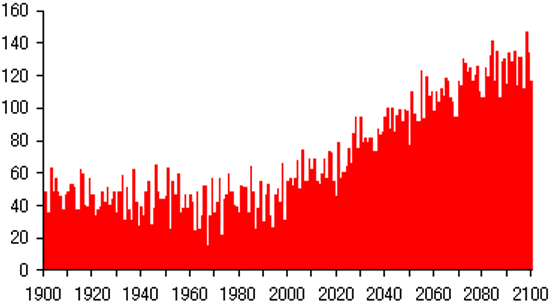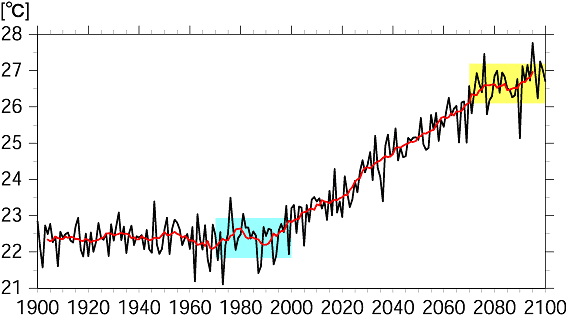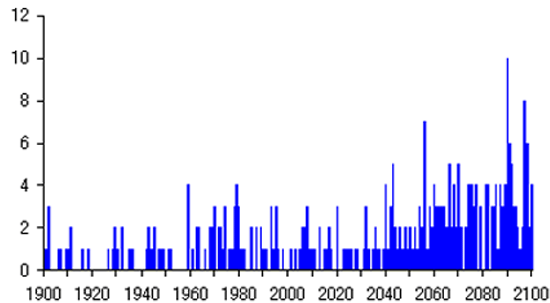地球シミュレータによる最新の地球温暖化予測計算が完了 − 温暖化により日本の猛暑と豪雨は増加 − |
||||||||||
| ||||||||||
|
||||||||||
1.背景 大気中の二酸化炭素など温室効果気体の増加による地球の温暖化について、かねてより世界の各研究機関でコンピュータによる将来の気候変化見通し計算が行われている。このような計算では、大気・海洋を格子に分割し、その上で物理法則を近似して解く。この格子の細かさを解像度といい、解像度を高くするほど大規模なコンピュータ資源が必要となる。従来は、大気が300km、海洋が100km程度の解像度の計算しか行えなかったが、今回、世界最大規模のスーパーコンピュータである地球シミュレータを利用することにより、大気が100km程度、海洋が20km程度の、世界で最高解像度の地球温暖化の計算を行うことに成功し、空間的により詳細な気候変化の検討が可能となった。 2.計算の概要 1900〜2000年については観測された温室効果気体濃度等の変化を与えて計算を行い、2001〜2100年についてはIPCC(気候変動に関する政府間パネル)により作成された将来のシナリオのうち2つについて計算を行った。1つは将来の世界が経済重視で国際化が進むと仮定したシナリオ「A1B」(2100年の二酸化炭素濃度が720ppm)、もう一つは環境重視で国際化が進むと仮定したシナリオ「B1」(2100年の二酸化炭素濃度が550ppm)である。 3.地球規模の結果 地球規模の結果は、従来より得られている見通しと概ね同様であった。2071〜2100年で平均した全地球平均の気温は1971〜2000年の平均に比較して、B1で3.0℃、A1Bで4.0℃上昇、同じく降水量はB1で5.2%、A1Bで6.4%の増加となった(注1)。気温上昇の地理分布は、北半球高緯度で大きく、海上に比べ陸上で大きい(図1)。
4 .日本の夏について 2071〜2100年で平均した日本の夏(6・7・8月)の日平均気温は1971〜2000年の平均に比較してシナリオB1で3.0℃、シナリオA1Bで4.2℃上昇、同様に日本の日最高気温はシナリオB1で3.1℃、シナリオA1Bで4.4℃上昇となった。日本の夏の降雨量は温暖化により平均的に増加するという結果となった(2071〜2100年平均で1971〜2000年平均に比較してシナリオB1で17%、シナリオA1Bで19%増加)。これは、熱帯太平洋の昇温と関係して日本の南側が高気圧偏差となり、これが日本付近に低気圧偏差をもたらすと同時に暖かく湿った南西風をもたらすこと、および、大陸の昇温と関係して日本の北側が上空で高気圧偏差となり、これが梅雨前線の北上を妨げることによると見られる(図2)。また、真夏日の日数は平均的に増加するという結果となった(図3)。これは、平均的な気温が上昇することによるもので、気温の年々の振れ幅には大きな変化は無いと見られる(図4)。さらに、豪雨の頻度も平均的に増加するという結果となった(図5)。これは、平均的な降雨量が増加することに加えて、大気中の水蒸気量が増加することにより、一雨あたりの降雨量が平均的に増加することによると見られる(注2)。
|
||||||||||
|
問い合わせ: 国立大学法人東京大学気候システム研究センター 柏地区駒場事務分室研究協力係 担当:三浦 Tel:03-5453-3953 Fax:03-5453-3964 URL:http://www.ccsr.u-tokyo.ac.jp/ 独立行政法人国立環境研究所 企画・広報室 担当:田邉 Tel:029-850-2303 Fax:029-851-2854 URL:http://www.nies.go.jp/ 独立行政法人海洋研究開発機構 地球環境フロンティア研究センター 担当:太田 Tel:045-778-5687 Fax:045-778-5497 URL:http://www.jamstec.go.jp/frcgc/jp/ 総務部普及・広報課 担当:五町 Tel:046-867-9066 Fax:046-867-9055 URL:http://www.jamstec.go.jp/ |