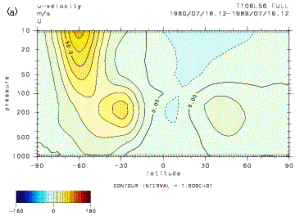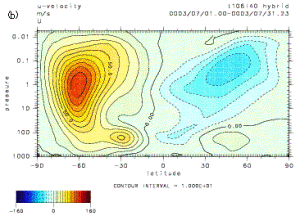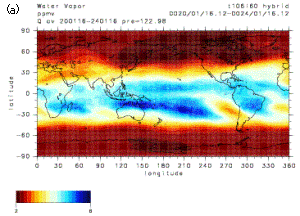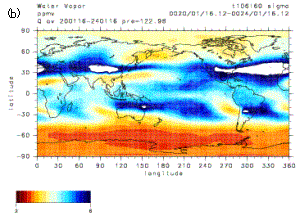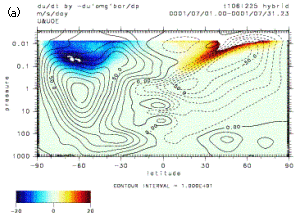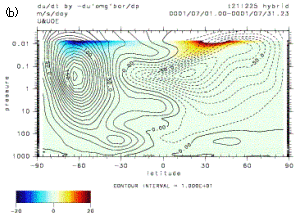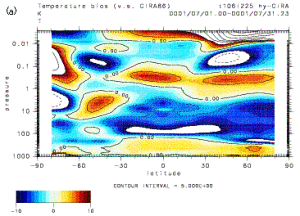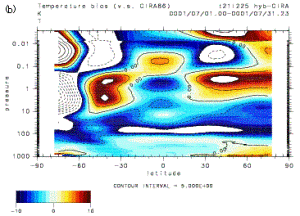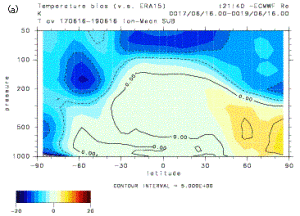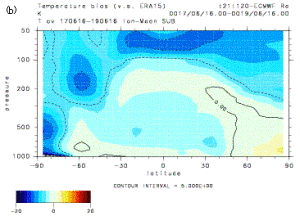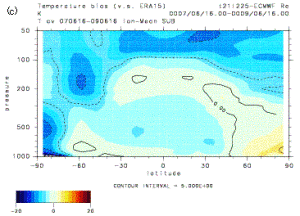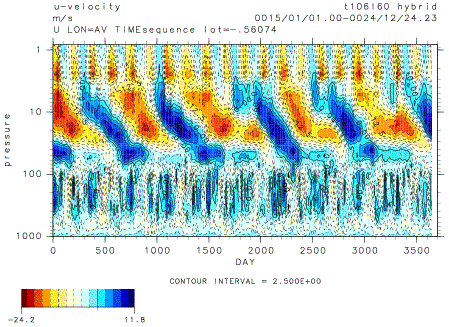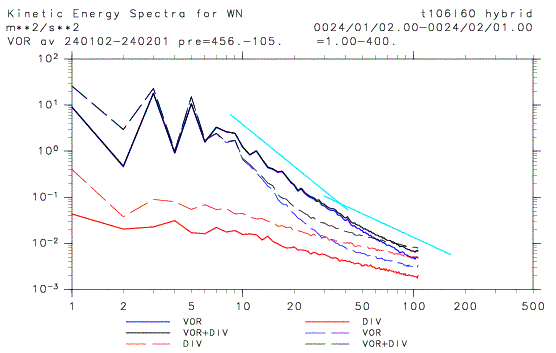4.気候物理コアモデル改良3 研究結果の詳細報告へ戻る | HOMEへ戻る |
|||||||||||||||
|
担当機関:地球フロンティア研究システム
a.要約大気・海洋・陸地面の主として物理過程から成る気候モデル(CCSR/NIESモデル、既存)で成層圏の諸プロセスを改良もしくは新しく取り入れたモデルを開発する。 大気モデルの改良に関しては、現モデルで不十分な中層大気(成層圏・中間圏)の諸プロセスの改良を図る。即ち、中層大気中への人為起源物質の侵入により、中層大気特有のオゾン層の物理・化学過程と太陽からの放射の変動が相互に影響し合って中層大気の変動を引き起こすと共に、それが下層対流圏の変動と結合して気候変動を生じる機構をモデル実験によって明らかにする。また、内部重力動波の挙動とそれが大気循環に及ぼす影響を超高解像度大気モデルによって明らかにする。本年度は、気候モデルの上端を上部中間圏(80km)まで拡張し、モデルの水平・鉛直解像度ならびに物理過程のチューニング・パラメーターを変化させた実験を数十ケース行うことにより、中層大気の様々な過程を支配する大気波動の役割の重要性を認識できた。本年度のシミュレーションで達成した解像度は、水平T106(1.1度格子)、鉛直層厚200mである。また、解像度を変えて実験した際に、地球シミュレーターの計算機資源と、実際の計算時間をどの程度必要とするかも調査した。また、従来のモデルで用いられてきた鉛直座標系はσ座標系であり、地表から離れた対流圏界面付近以上の高度では、力学過程の表現に問題が生じる可能性が指摘されていたが、これをσ-pハイブリッド座標系に変更することにより、成層圏以上での計算精度が向上した。一方、このモデルに特有の問題である、対流圏界面付近の低温・湿潤バイアスに関しては、その実態の詳細と、原因となる過程に関する調査を進めたが、その解決は次年度の課題として残された。 b.研究目的本研究の目的は、気候物理モデルの開発・改良と、それに結びつく大気中の様々な過程をより良く理解することにある。とりわけ、中層大気中における、大気組成の変化と気候との相互作用過程を正確にシミュレートするためには、大気微量成分やエアロゾルの輸送を支配する大気の運動と、光化学反応過程に重要な大気の温度場を適切に再現できる必要がある。中層大気中の大規模な循環と温度場の季節変化や年々変動をよりよく再現するためには、オゾンによる太陽紫外線吸収がもたらす加熱や、二酸化炭素・メタン・オゾン・水蒸気を代表とする温室効果気体が放つ赤外放射による冷却、すなわち放射過程と、数百メートルから惑星規模にわたるさまざまな大気波動が、それぞれモデル中で適切に表現される必要があると考えられている。放射過程および小規模の大気波動を正しく表現するためには、モデルの水平・鉛直解像度がある程度高くなければならないと考えられている。 しかしながら、長期間にわたって、大気組成変化との相互作用までも含めた温暖化予測実験を行ううえで必要十分な解像度は、今もって十分明らかにはされていない。地球シミュレーターを用いた大規模計算により、各々の過程のモデル解像度に対する依存性を明らかしていくことは、統合モデルの設計にとって必須であるとともに、学術的にも意義深いものであり、本サブテーマの中心課題である。 全体計画において、最終的な統合モデルの基礎となる高解像度全球大気モデルの開発を長期的な目標とするとともに、各サブグループ(部分統合モデル)のニーズに合わせた大気モデルの開発・提供を行っていく予定である。 c.研究計画、方法、スケジュール大気・海洋・陸地面の主として物理過程から成る気候モデル(CCSR/NIESモデル、既存)で成層圏の諸プロセスを改良もしくは新しく取り入れたモデルを開発する。成層圏・中間圏大気の温度と循環・物質輸送に大きな役割を果たす内部重力波の効果を正しく取り入れるため、内部重力波をパラメタライズせず直接取り扱う水平解像度20km、鉛直層厚100m程度のモデルで数値実験を行う必要がある。この実験を2年目までに実施し、3年目には、中層大気までを含む中解像度大気化学・気候結合モデルに新しいパラメタリゼーションを組み込めるようにする。中層大気を含む化学・気候結合モデルは、サブテーマ(2)−「温暖化・大気組成相互作用モデル」の開発−とも協力して平衡して開発を進め、オゾン層破壊と温暖化の相乗効果など中解像度モデルで実験を行う。d.平成14年度研究計画物理気候コアモデルに関して、高度約80kmまでの成層圏・中間圏までを含め、同時に鉛直解像度を高くする作業に着手する。中層大気化学(オゾン層化学)過程で統合モデルに適切なプロセスモデルの考察も行う。並行して、現状の気候モデルの問題点の改良も行う。e.平成14年度研究成果e-1) モデル上端の拡張最初に、モデルの鉛直計算範囲の拡張を行った。具体的には、CCSR/NIESモデルの上端を従来の50km未満から、80kmに上げた。このことにより、成層圏・中間圏のすべてを表現できるようになり、長期間にわたる大気組成の変化と気候の変動を適切に予測できる可能性が高まった。例として、7月の帯状平均東西風を図1に示す。図1aは、従来のモデルの結果であり、南半球の冬季西風ジェットの上部や、北半球の夏季東風が表現されていない。これに対して、図1bは、上端を80kmにしたモデルの結果である。また、オゾンホールの発達に関係のある下部成層圏の季節進行に関しても、冬半球の西風ジェットや夏半球の東風ジェットをすべて表現できるようになったことから、より正確なシミュレーションが可能となった。
e-2) 鉛直座標系の変更 モデルの鉛直座標系を、従来のσ座標系から、中層大気モデルで一般に用いられており、上部対流圏から中層大気における循環場および物質輸送の改善が期待されるσ-pハイブリッド座標系に変更した。これに伴い、微量成分気体(水蒸気)の分布が変化した。 図2aは、σ-pハイブリッド座標系を用いた場合の120hPa面の水蒸気混合比、図2bは、従来のσ座標系の結果である。σ座標系を用いた場合には、山岳地形周辺でモデルの座標面が盛り上がるため、より下層の水蒸気を多く含んだ空気がヒマラヤ、ロッキー、アンデス等、山岳の風下(右手方向)に向かって流出する効果により、下部成層圏がより湿潤になる傾向が見られたのに対し(図2b)、σ-pハイブリッド座標系いた際には、そのような悪影響が除去されることが分かる(図2a)。
e-3)水平・鉛直解像度・および物理過程のパラメーターの違いに対するモデル大気の応答 モデルの水平・鉛直解像度、および様々な物理過程のパラメーターを変更して、それに対するモデル大気の応答の違いを調査した。実際の作業は、数十例におよぶ実験を数年間ずつ繰り返すものであったが、主な実験設定と、その成果のみを整理して以下に挙げる。 e-3-1) 水平解像度モデルの水平解像度を上げることは、より詳細な気温や降水の分布を再現できるようになるといった、対流圏の気候の再現性を向上させる意味だけではなく、中層大気においても、大循環の形成に重要な役割を果たす小規模の内部重力波の表現が可能となるという点において重要である。たとえば、大気大循環モデルに共通した大きな問題点として、冬季-春季にかけて極域下部成層圏の気温が観測に比較して低温になりやすいという「高緯度低温バイアス」が存在する。その主な原因として、小規模の内部重力波の表現が不十分であることが考えられている(たとえばHamilton et al., 1999)。 図3のカラースケールは、水平解像度をT106(1.1度格子)およびT21(5.6度格子)で行った実験における、重力波の運動量輸送に伴う東西風の加・減速の分布を示している。いずれも7月の結果で、鉛直解像度は成層圏で200m、モデル上端付近で500mとなるように取っている。水平解像度が高い方が、より多くの重力波を表現し、結果として、帯状平均東西風をより強く、より低い高度から減速させていることが分かる。等値線で表されている東西風の分布を見ると、南半球冬季の極夜ジェットのピークは、高解像度のものは110m/s程度であるのに対して、低解像度のものは170m/s程度となっている。
図4は、同じ実験の温度場を、観測(CIRA86)からのずれ、すなわちバイアスで表現したものを表す。水平解像度が高くなるほど、南半球冬季の高緯度成層圏の低温バイアスが改善される様子が分かる。低解像度では50℃以上ある低温バイアスが、高解像度では15℃程度まで小さくなっている。
e-3-2) 鉛直解像度 GCMの水平解像度のみを上げて鉛直解像度が相対的に低いままであると、再現される大規模な流れの場や大気波動に問題が生じることが指摘されている(Lindzen and Fox-Rabinovitz 1989)。また、放射過程や微量成分の輸送、重力波の散逸過程を正確にシミュレートするためには十分な鉛直解像度が必要になる。このため、鉛直解像度を変化させて実験を行った。波動に関する詳しい解析は未だ行っていないが、鉛直解像度を高くすることによって、このモデル(CCSR/NIES AGCM)に固有の問題である、下部成層圏の低温・湿潤バイアスがある程度改善されることが分かった。 図5は、鉛直解像度を、従来中層大気大循環モデルで用いられてきた1500m程度から、200mまで細かくしたときの、温度場の再現性の変化(6月の帯状平均温度バイアス)を示す。これらの図の数値は、シミュレーションの結果から、ECMWFの再解析データ:ERA15の値を引いたものであり、絶対値が小さくなるほどシミュレーションの結果が良好であることを表す。なお、結果は数年間積分した最後の3年間の平均を示してある。この結果から、鉛直解像度を高くすることによって、下部成層圏から対流圏界面付近(50-300hPa)の低温バイアスが改善されていくことが分かる。また、図は示さないが、湿潤バイアスに関しても、鉛直解像度を上げることにより対流圏界面付近において水蒸気の過剰な成層圏への輸送が抑制されることが分かった。湿潤バイアスは水蒸気の放射冷却を通じて低温バイアスの原因ともなりうるため、より詳しい解析が必要である。
e-3-3) 重力波エネルギー・スペクトルと成層圏赤道QBOの再現 単に水平・鉛直解像度のみを高くしても、モデル中の重力波は適切に再現されず、したがって、大気大循環の気候場の再現性も向上しない。重力波をよりよく再現するためには、複数の物理過程のパラメーターを適切にチューニングする必要がある。それらパラメーターの中で、重力波の散逸に関する水平拡散と、励起に関する積雲対流パラメタリゼーションにおける相対湿度の閾値(RHc)が、特に重要であることが確かめられた。(RHcに関しては、辻ほか,2002を参考にした。) 図6はT106L60(上端は約50km、下部成層圏の鉛直解像度は約500m)の解像度で再現された成層圏赤道東西風の準二年振動(QBO)を示す。およそ20hPa付近を中心として、約25~27ヶ月周期で東西風が交代する様子が見られる。観測されているものに比べるとやや振幅が小さいが、モデルの上端の低さや鉛直解像度の不足などが原因であると推測される。なおQBOのレビューとしては、Baldwin et al. (2001)、重力波パラメタリゼーションを用いないGCMによるQBOの再現に関しては、Takahashi (1996, 1999)、Horinouchi and Yoden (1998)、Hamilton et al.(2002)などが挙げられる。
図7はこのときの水平運動エネルギーの全波数スペクトルを示す。図の黒い実線は、上部対流圏における正味のエネルギー・スペクトルを表しているが、その傾きに注目すると、およそ全波数10-40の範囲では、波数の-3乗に、それより大きな波数では、およそ波数の-5/3乗に従って、高波数ほどエネルギーが弱くなっていることが分かる。これらは航空機観測から得られた実際のスペクトル分布と良い一致を示している(Nastorm et al., 1984)。 図の赤線は水平運動エネルギーのうち、発散成分を表すが、その大部分は内部重力波に関するものである。特に成層圏においては、大気密度の減少とともに重力波の持つエネルギーは増加し、特に高波数では、正味のエネルギーの大部分を占めるようになることが分かる。この重力波成分による運動量輸送が、QBOの再現に特に重要であると考えられている(たとえばDunkerton, 1997, Horinouchi and Yoden, 1998)。 多数のパラメーターを変化させて行った感度実験の結果から、このような観測事実に近いエネルギー・スペクトルの傾きとQBOを同時に再現するためには、水平拡散および積雲対流に関するパラメーターを、ある程度こまめにチューニングしてやる必要があることが分かった。T106の場合、水平拡散に関しては標準的な∇4の拡散から、∇8の拡散に変更し、最大波数に対するダンピング・タイムを1日程度とする必要があった。また積雲対流から、適当な時空間スペクトルを持った重力波を励起させるために、対流発生の判定に関するパラメーターRHcを、鉛直解像度に応じて適宜調節を行った。 e-4 モデルの鉛直範囲の拡張と鉛直解像度の決定に関する補足本研究では、既存の九州大学GCM(Miyahara et al.,1995)や、GFDLのSKYHI GCM (Fels et al.,1980)を参考にし、それらよりもはるかに鉛直解像度を高めることを念頭に開発を行った。以下にモデル開発を通じて経験的に得られた知見を記しておく。
鉛直層厚を一定にとることが内部重力波の伝播と散逸過程を正確に表現する上で重要であるが、計算安定性の面から言えば、鉛直層厚を高度とともに線形に増加させると、より安定に、より長いタイム・ステップで高速に積分が可能になることが確認された。(同じ鉛直層数の場合、実際の計算コストはおよそ6割になった。)SKYHI GCMをはじめ他のGCMも同様に高度とともに鉛直解像度を粗くしており、鉛直高分解能ではあるが、重力波そのものには注目せず、安定に短時間でモデルのスピン・アップを行いたい場合などには、有効であると考えられる。線形以外の割合で層厚を増加させた場合には、モデル大気の東西風や大気波動の鉛直伝播に際立った不連続が生じることも確認した。
また、同様の不連続は、放射の計算に用いるオゾンデータの鉛直分布が不連続な場合にも生じたため、用いるオゾンデータには必要最小限のスムージングを施した。
一方、重力波による東西風の減速を近似するためにGCMで一般に用いられているレイリー摩擦は、鉛直高解像度モデルに適用した場合には、その適用高度において、モデル大気に著しい不連続が現れることが分かったため、モデル上端付近のスポンジ層以外では使用を中止した。その結果、たとえばT106L250(1.1度格子、鉛直層厚300m)の解像度では、中・高緯度の極夜ジェットが、両半球とも観測に比較して20-30m/s程度強く、また、低緯度では、成層圏界面の半年周期振動や中間圏の半年周期振動の再現性が悪くなっている。今後は、より水平・鉛直解像度を高めた実験を行うとともに、モデルの上端をもう少し上げるなどして、改良に取り組む必要がある。
f.考察全体的に、ほぼ当初の研究計画どおり、あるいはそれ以上の成果を達成したといえる。
鉛直座標系の更新に伴って、水蒸気輸送に大きな改善が見られたが、山岳地形周辺の循環場そのものの変化は、場所や季節でまちまちであり、座標系の変更によるものなのか、簡単な解析からは判断できなかった。以後の課題としたい。 水平解像度の向上に対するモデル中層大気の応答に関しては、すでに今回調査したT106の1.1度格子を上回る0.3x0.33度格子を用いたSKYHI GCMの結果が出版されている(Hamilton et al.,1999)。しかしながら、彼らのモデルは格子法に基づいており、スペクトル法を用いたわれわれのモデルとは結果が異なる可能性がある。今後、より水平解像度を高めた実験を行い、詳しく検証する必要がある。
鉛直解像度の向上に対するモデル大気の応答に関して、世界を見渡すと、中層大気GCMとしては下部成層圏で鉛直層厚500-700m程度とし、高度とともに鉛直解像度を粗くしていくものが最高であり、鉛直層数は80-90層である(Hamilton et al.,1999、Giorgetta et al.,2002)。現時点で、前項で例に示した200-300mという解像度で十分な期間にわたって計算ができるのは、地球シミュレーターを用いたわれわれのモデルだけである。内部重力波の伝播や砕波を正確に表すためには、鉛直層厚が100mのオーダーになることが求められているため、今後さらに開発を続けていく必要がある。また、下部成層圏の低温・湿潤バイアスの改善に向けても、より詳しい検討が必要である。
内部重力波を含んだ運動エネルギーの全波数スペクトルに関しては、様々な水平解像度の中層大気GCMの結果を比較した論文がある(Koshyk et al.,1999)。水平解像度がT42(2.8度格子)程度であり、内部重力波のうち比較的大規模なものしか表現できない従来の気候モデル、あるいは数値予報のためのモデルにおいては、モデルの表現できる最小規模にちかい重力波は、計算不安定をもたらすノイズとして数値的に除去されていた。そういう経緯のため、水平解像度が高められた今日のGCMにおいても、高波数の波に対しては、強めの水平拡散を作用させてしまい、観測されているスペクトル強度よりも小さくなっている例が多かった。
開発中のモデルでは、重力波の再現性を重視しており、ひとつの指標としてスペクトルの傾きが観測事実に近づくように調整を行った。ただし、スペクトルの強度そのものに関しては、異なる積雲対流スキームを用いた他のモデルと比較するとやや小さい傾向にあるので、今後はそのあたりの考察も行いたい。また、QBOの生じる下部成層圏高度だけでなく、内部重力波の砕波が頻繁に生じる上部中間圏における重力波の振る舞いに関しても、今後より高解像度のモデルを用いて詳しく調べていきたい。
最後に、今回の報告書では触れていないが、次年度中には、中解像度版GCMにおいて重力波のパラメタリゼーション(Hines 1997a,b)を導入する予定である。それに先駆けて、超高解像度版の中層大気GCMにおける重力波のパラメーターとの直接比較を行い、より適切なパラメタリゼーションの実装方法を模索する予定である。
謝辞: 本研究の計算は地球シミュレーターを用いて行われた。作図にはGFD-DENNOU Library およびGTOOLを使用した。鉛直座標系の変更に関しては、方程式系の導出および実際の作業の大部分は、東京大学気候システム研究センター大学院の院生である三浦氏の手によって行われた(Miura,私信)。 g.引用文献Baldwin, M. L. J. Gray, T. J. Dunkerton, K. Hamilton, P. H. Haynes, W. J. Randel, J. R. Holton, M. J. Alexander, I. Hirota, T. Horinouchi, D. B. A. Jones, J. S. Kinnersley, C. Marquardt, K. Sato and M. Takahashi, The Quasi-Biennial Oscillation, Rev. Geophys., 39, 179-229, 2001.Dunkerton, T. J., The role of gravity waves in the quasi-biennial oscillation, J. Geophys. Res., 102, 26,053-26,076, 1997. Fels, S. B., J. D. Mahlman, M. D. Schwarzkopf and R. W. Sinclair, Stratospheric sensitivety to perturbations in ozone and carbon dioxide: radiative and dynamical response, J. Atmos. Sci., 37, 2265-2297, 1980. Giorgetta, M. A., E. Manzini and E. Roeckner, Forcing of the quasi-biennial oscillation from a broad spectrum of atmospheric waves, Geophys. Res. Lett., 29, 8-86., 2002. Hamilton, K ., R. J. Wilson and R. S. Hemler, Spontaneous stratospheric QBO-like oscillations simulated by the GFDL SKYHI general circulation model, J. Atmos. Sci., 58, 3271-3292, 2002. Hamilton. K, R. J. Wilson and R. S. Hemler, Middle atmosphere simulated with high vertical and horizontal resolution versions of a GCM: Improvements if the cold pole bias and generation of a QBO-like oscillation in the tropics, J. Atmos Sci., 56, 2829-3846, 1999. Hines, C. O., Doppler-spread parameterization of gravity-wave momentum deposition in the middle atmosphere. Part 1: Basic formulation, J. Atmos. Solar Terr. Phys., 59, 371-386, 1997a. Hines, C. O., Doppler-spread parameterization of gravity-wave momentum deposition in the middle atmosphere. Part 2: Broad and quasi monochromatic spectra, and implementation, J. Atmos. Solar Terr. Phys., 59, 387-400, 1997b. Horinouchi, T and S. Yoden, Wave-mean flow interaction with a QBO-like oscillation simulated in a simplified GCM, J. Atmos. Sci., 55, 502-526, 1998. Koshyk, J. N., B. A. Boville, K. Hamilton, E. Manzini and K. Shibata., Kinetic energy spectrum of horizontal motions in middle-atomosphere models, J. Geophys. Res., 104, 27,177-27,190, 1999. Lindzen, R and Fox-Rabinovitz, Consistent vertical and horizontal resolution, Mon. Weather Rev., 117, 2575-2583, 1989. Miura, H., Vertical differencing of the primitive equations in a Sigma-p hybrid coordinate (For Spectral AGCM), CCSR Internal Report, University of Tokyo, in press. Miyahara, S ., Y. Miyoshi, T. Kayahara, Y. Yoshida, M. Ooishi and T. Hirooka, Development of a middle atmosphere general circulation model at Kyushu University, Climate System Dynamics and Modeling, Center for Climate System Research, University of Tokyo, pp. 75-103, 1995. Nastorm, G. D., K. S. Gate and W. H. Jasperson, Kinetic energy spectrum of large-and mesoscale atmospheric processes, Nature, 310, 36-38. 1984. Takahasi, M., Simulation of the stratospheric quasi-biennial oscillation using a general circulation model, Gephys. Res. Lett., 23, 661-664, 1996. Takahashi, M, Simulation of the quasi-biennial oscillation in a general circulation model, Geophys. Res. Lett., 26, 1307-1310, 1999. 辻ほか,対流圏積雲対流活動のQBOサイクルに及ぼす影響,日本気象学会2002年度春季大会講演予稿集, pp. 58, 2002. h.成果の発表<口頭発表>S. Watanabe, Development of a middle atmosphere GCM at the Frontier, GRIPS annual workshop, Mar 6 2003, Washington D.C., USA. |