今年度の当サブグループの最優先課題は、共生第一課題(住グループ)と共有している大気大循環モデル(CCSR/NIES/FRSGC AGCM)において上部対流圏-下部成層圏に見られる、顕著な低温バイアスの除去であった。それに加えて、オゾンホールの生じる冬季から春季の高緯度下部成層圏の気温、および熱帯の循環を現実的にシミュレートするために、地形起源以外の重力波のパラメタリゼーションの導入を行った。
AGCMの低温バイアスは、このモデルが開発された当初から現在に至るまで存在し、成層圏と対流圏の間の物質交換、特に成層圏中の水蒸気量を正しくシミュレートするのに大きな障害となっていた。CCSRの放射グループでは、放射収支の計算に用いるプログラムの改良が行われており、新しい放射コードをAGCMに組み込み、テストを行うことができた。
図13は、新放射コードを用いた実験の結果で、北半球夏季平均の帯状平均温度から観測値を引いた値を示している(カラーの両端は+-10 Kを表す)。従来の放射コードを用いた実験に見られた顕著な低温バイアス(図14)が、大幅に改善されている。今後さらに改良を重ねて行けば、将来化学過程を含めたシミュレーションを行う際にも、水蒸気やオゾンといった地球温暖化にとって重要な物質の分布がより良く再現されることが期待される。
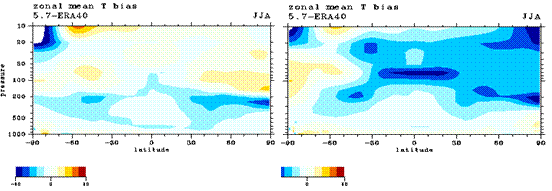
|
| 図13: 新放射コードを用いた実験における、北半球夏季の帯状平均温度バイアス。 | 図14: 従来のコードを用いた実験における、北半球夏季の帯状平均温度バイアス。 |
非地形性重力波抵抗パラメタリゼーションの導入に当たっては、最も普及しているHines(1997)のものを選択した。下部成層圏の重力波の観測は限られているため、このパラメタリゼーションに入力する必要のある、各方位に伝播する重力波のRMS振幅を、T106L250 AGCMによるシミュレーション結果から導出することを試みた。このモデルの鉛直解像度は300mであり、通常のAGCMでは解像できない鉛直方向に小規模な重力波を表現しうる。現在テスト段階ではあるが、地理変化・季節変化を含む重力波ソースを用いて、現実的な赤道QBOの再現に成功している。今後は高緯度循環の再現性向上を目指す必要がある。