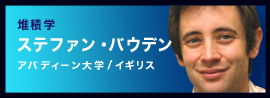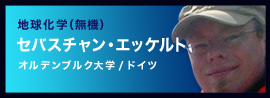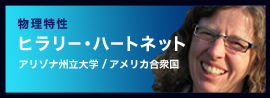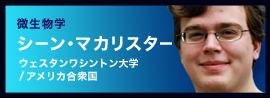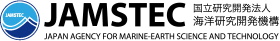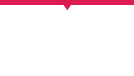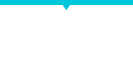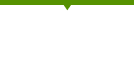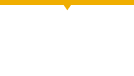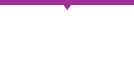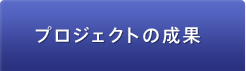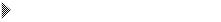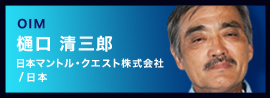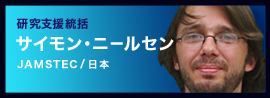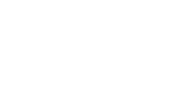
海洋研究開発機構 海洋・極限環境生物圏領域 深海・地殻内生物圏研究プログラム プログラムディレクター及びプレカンブリアンエコシステムラボララトリー ユニットリーダー。
研究者の第一歩を踏み出して以来、深海熱水活動域などの極限環境に生息する微生物を次々に血祭りにあげてきた微生物ハンター。
彼らの生活ぶりを知りたくて、生息環境を詳しく調べるうちに、微生物の活動が地球の壮大な歴史と密接に関連することに猛烈に感動し、以後、地球生物学者と名乗るようになる。
そのうち、生命の誕生や進化が惑星の営みと密接に関連することをしみじみと思い知り、宇宙生物学者とも名乗るようになる。
現在は、もっぱら地球の深海熱水における地球と生命の関わりを如何に美しく証明するかを目指している。
沖縄熱水掘削航海では、熱水噴出孔直下の生態系の直接証明に挑む。
研究者の第一歩を踏み出して以来、深海熱水活動域などの極限環境に生息する微生物を次々に血祭りにあげてきた微生物ハンター。
彼らの生活ぶりを知りたくて、生息環境を詳しく調べるうちに、微生物の活動が地球の壮大な歴史と密接に関連することに猛烈に感動し、以後、地球生物学者と名乗るようになる。
そのうち、生命の誕生や進化が惑星の営みと密接に関連することをしみじみと思い知り、宇宙生物学者とも名乗るようになる。
現在は、もっぱら地球の深海熱水における地球と生命の関わりを如何に美しく証明するかを目指している。
沖縄熱水掘削航海では、熱水噴出孔直下の生態系の直接証明に挑む。
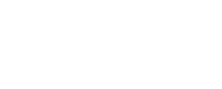
地質学、中でも地球化学が専門です。
プリンストン大学とハーヴァード大学で、ハインリッヒ・ホランド氏とともに博士課程の研究を行い、その後スタンフォード、ウッズホール海洋研究所にて勤務し、1986年からはハワイ大学で教えています。また、ハワイ大学海洋学部と、NASA宇宙生物学研究所の構成メンバーの一員です。過去33年間の海洋学者としての人生のうち、のべ3年間を洋上で過ごしてきました。
「ちきゅう」での航海は初めてですが、海洋研究の航海としては30回目、掘削航海としては9回目、掘削航海の首席研究者としては2度目の航海になります。
「ちきゅう」は、今まで私が乗船した研究船の中でも最も大きく、高性能です。その掘削能力とラボ設備は、狭いスペースにありながら巧みに配置されており、陸上・海上どちらにおいても、群を抜いたものといえます。今回の沖縄トラフ熱水海底下生命圏掘削プロジェクトは、科学技術界の最先端をいくものなので、そのようなプロジェクトの一員となれることに大きな喜びを感じています。
今回も沖縄トラフの海底下にある高温の熱水活動域を掘削することによって、素晴らしい結果が得られることを、心から期待しています。
プリンストン大学とハーヴァード大学で、ハインリッヒ・ホランド氏とともに博士課程の研究を行い、その後スタンフォード、ウッズホール海洋研究所にて勤務し、1986年からはハワイ大学で教えています。また、ハワイ大学海洋学部と、NASA宇宙生物学研究所の構成メンバーの一員です。過去33年間の海洋学者としての人生のうち、のべ3年間を洋上で過ごしてきました。
「ちきゅう」での航海は初めてですが、海洋研究の航海としては30回目、掘削航海としては9回目、掘削航海の首席研究者としては2度目の航海になります。
「ちきゅう」は、今まで私が乗船した研究船の中でも最も大きく、高性能です。その掘削能力とラボ設備は、狭いスペースにありながら巧みに配置されており、陸上・海上どちらにおいても、群を抜いたものといえます。今回の沖縄トラフ熱水海底下生命圏掘削プロジェクトは、科学技術界の最先端をいくものなので、そのようなプロジェクトの一員となれることに大きな喜びを感じています。
今回も沖縄トラフの海底下にある高温の熱水活動域を掘削することによって、素晴らしい結果が得られることを、心から期待しています。

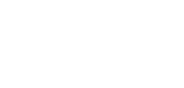
JAMSTEC CDEX運用管理室掘削管理グループサブリーダー
早稲田大学理工学部資源工学科卒。
石油会社に入社後、サウジアラビア、中国、ベトナムで石油開発リグでの掘削作業のCompany Man(現場監督)をしていました。
その後、総合電機メーカーで海洋調査及び海底ケーブル敷設埋設作業の現場監督を経て、2004年に「ちきゅう」プロジェクトに参加。掘削機器(特にSubsea / BOPやRiser)を担当し現在は掘削計画及び現場監督(船上代表)を務める。
早稲田大学理工学部資源工学科卒。
石油会社に入社後、サウジアラビア、中国、ベトナムで石油開発リグでの掘削作業のCompany Man(現場監督)をしていました。
その後、総合電機メーカーで海洋調査及び海底ケーブル敷設埋設作業の現場監督を経て、2004年に「ちきゅう」プロジェクトに参加。掘削機器(特にSubsea / BOPやRiser)を担当し現在は掘削計画及び現場監督(船上代表)を務める。
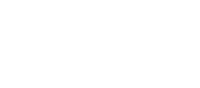
2008年から「ちきゅう」に従事。
オフショアインスタレーションマネージャー、つまり海上の設備に関するマネージャーということになります。
キャプテンは船の代表者ですが、私はこの「ちきゅう」の代表者であり、ちきゅう全体の安全を統括している立場と思って仕事をしております。
今回の掘削業務では、海底表面が固いことが想定されることや、台風の発生が予想され非常に難しい作業となりますが、研究者達が目的とするコアが取れたとき、そのことが最終的な喜びであり、仕事のやりがいとなっています。
オフショアインスタレーションマネージャー、つまり海上の設備に関するマネージャーということになります。
キャプテンは船の代表者ですが、私はこの「ちきゅう」の代表者であり、ちきゅう全体の安全を統括している立場と思って仕事をしております。
今回の掘削業務では、海底表面が固いことが想定されることや、台風の発生が予想され非常に難しい作業となりますが、研究者達が目的とするコアが取れたとき、そのことが最終的な喜びであり、仕事のやりがいとなっています。
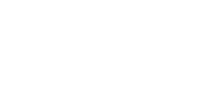
地球深部探査船「ちきゅう」船長
東京商船大学(現在の東京海洋大学)卒業
1981年:航海士として日本郵船に入社。
2002年:「ちきゅう」に従事。(建造時から8年間)
高い性能を持つ「ちきゅう」で、先端の学術目的を持った研究者達と一つの目標に向かって仕事をするのが「ちきゅう」で働くやりがいです。
台風の影響も心配されますが、船の行動予定について船長としての判断資料を各担当者に提供し皆さんと協議し同意を得たうえで台風を回避する最善策をとることが私の役割となります。
東京商船大学(現在の東京海洋大学)卒業
1981年:航海士として日本郵船に入社。
2002年:「ちきゅう」に従事。(建造時から8年間)
高い性能を持つ「ちきゅう」で、先端の学術目的を持った研究者達と一つの目標に向かって仕事をするのが「ちきゅう」で働くやりがいです。
台風の影響も心配されますが、船の行動予定について船長としての判断資料を各担当者に提供し皆さんと協議し同意を得たうえで台風を回避する最善策をとることが私の役割となります。
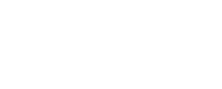
私たちの暮らす地球上に存在する微生物の歴史、微生物の地球化学的な循環や、地球以外の惑星に生命が存在する可能性について研究対象としています。
現在、NASA宇宙生物学研究所の一部である、ペンシルヴァニア州宇宙生物学研究センターのセンター長を務めています。
学部生時代はカリフォルニア大学サンディエゴ校にて生命起源化学者のスタンレー・ミラー氏と共に研究に励み、生化学の学位を取得しました。その後、カリフォルニア大学ロサンジェルス校で、先カンブリア紀の古生物学者であるJ.W.ショフ先生に師事、地質学の博士号を取得しました。
大学院時代には、微生物と炭素の代謝システムの関連性について、炭素同位体を用いて研究していました。
ここ10年ほどは、私自身が地下深度微生物やその特異な代謝作用について学んだペンシルヴァニア州立大学で、地球科学の准教授を務めています。
現在、NASA宇宙生物学研究所の一部である、ペンシルヴァニア州宇宙生物学研究センターのセンター長を務めています。
学部生時代はカリフォルニア大学サンディエゴ校にて生命起源化学者のスタンレー・ミラー氏と共に研究に励み、生化学の学位を取得しました。その後、カリフォルニア大学ロサンジェルス校で、先カンブリア紀の古生物学者であるJ.W.ショフ先生に師事、地質学の博士号を取得しました。
大学院時代には、微生物と炭素の代謝システムの関連性について、炭素同位体を用いて研究していました。
ここ10年ほどは、私自身が地下深度微生物やその特異な代謝作用について学んだペンシルヴァニア州立大学で、地球科学の准教授を務めています。
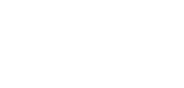
日本周辺の海域で初めて大規模な海底熱水域が見つかったのは1988年でした。
その時私は大学院の学生で、指導教員の酒井均先生と一緒にその調査航海に参加していました。海底熱水域を見つけるためにドイツからやってきた調査船ゾンネは、1ヶ月にわたって沖縄トラフのあちこちで海水の採取と分析・岩石や堆積物の採取・深海カメラ調査などの探査を続けました。そして航海の残りもあと数日というところで、熱水活動でできる特徴的な鉱石が大量に採取されたのでした。
酒井先生が「やっぱり本当にあるんだねえ」と感激していたのがとても印象に残っています。
沖縄トラフ熱水域の熱水化学をテーマにした研究で無事に大学院を修了した私は、その後も様々な海域の熱水調査に参加してきました。中でも1996年のミドルバレー熱水域掘削航海(ODP Leg169)への参加は、その後の研究の方向性を決める重要な航海でした。海底下から掘削で得られる試料は、海底面上から集められた試料では得られない多くの貴重な情報を持っています。各分野の研究者が船上で分析したばかりのデータを持ち寄って行う議論の中で、新しい問題、新しいアイデアがいろいろとわいて来るのです。
この沖縄熱水域掘削航海での私の研究テーマは、海底下の熱水の流れに沿って鉱石ができる化学反応を考えることです。普段はアクセスが不可能な海底下で起こっている化学反応について、自分が考えているアイデアを試すまたとない機会なのです。「ほうら本当にできてるじゃないですか」と言える証拠を堆積物から見つけ出すことを目指しています。
その時私は大学院の学生で、指導教員の酒井均先生と一緒にその調査航海に参加していました。海底熱水域を見つけるためにドイツからやってきた調査船ゾンネは、1ヶ月にわたって沖縄トラフのあちこちで海水の採取と分析・岩石や堆積物の採取・深海カメラ調査などの探査を続けました。そして航海の残りもあと数日というところで、熱水活動でできる特徴的な鉱石が大量に採取されたのでした。
酒井先生が「やっぱり本当にあるんだねえ」と感激していたのがとても印象に残っています。
沖縄トラフ熱水域の熱水化学をテーマにした研究で無事に大学院を修了した私は、その後も様々な海域の熱水調査に参加してきました。中でも1996年のミドルバレー熱水域掘削航海(ODP Leg169)への参加は、その後の研究の方向性を決める重要な航海でした。海底下から掘削で得られる試料は、海底面上から集められた試料では得られない多くの貴重な情報を持っています。各分野の研究者が船上で分析したばかりのデータを持ち寄って行う議論の中で、新しい問題、新しいアイデアがいろいろとわいて来るのです。
この沖縄熱水域掘削航海での私の研究テーマは、海底下の熱水の流れに沿って鉱石ができる化学反応を考えることです。普段はアクセスが不可能な海底下で起こっている化学反応について、自分が考えているアイデアを試すまたとない機会なのです。「ほうら本当にできてるじゃないですか」と言える証拠を堆積物から見つけ出すことを目指しています。
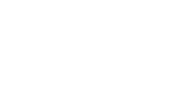
JAMSTEC CDEXのIODP研究支援統括とし「ちきゅう」に乗船することになりました。専門は地質学です。
今回の航海では、サイエンス・パーティーの皆さんと一緒に、深海の生態系からサイエンスの世界に新たな発見をもたらすような良いコア試料を採取できることを期待しています。
「ちきゅう」には、素晴らしいラボ設備と研究に最適な環境が備わっています。さらに、深海の生態系を掘削しサンプルを採取出来る機器と、それらを自在に使うことのできる専門家がたくさん乗船しています。気候条件を除けば特に心配な点もなく、快適な掘削作業が望めると思います。
これまで私は地質学者として、陸上と海上で、また北極と南極で調査にあたってきました。
これまでの研究では、堆積物のコア、沿岸の露頭を調査し、何百万年も前の環境がどのようなものだったかを研究してきましたが、ついに今回の航海で日本の亜熱帯地方での研究に参加します。
今回の航海では、サイエンス・パーティーの皆さんと一緒に、深海の生態系からサイエンスの世界に新たな発見をもたらすような良いコア試料を採取できることを期待しています。
「ちきゅう」には、素晴らしいラボ設備と研究に最適な環境が備わっています。さらに、深海の生態系を掘削しサンプルを採取出来る機器と、それらを自在に使うことのできる専門家がたくさん乗船しています。気候条件を除けば特に心配な点もなく、快適な掘削作業が望めると思います。
これまで私は地質学者として、陸上と海上で、また北極と南極で調査にあたってきました。
これまでの研究では、堆積物のコア、沿岸の露頭を調査し、何百万年も前の環境がどのようなものだったかを研究してきましたが、ついに今回の航海で日本の亜熱帯地方での研究に参加します。