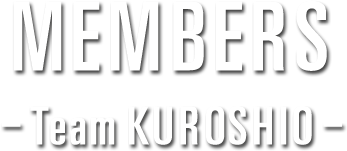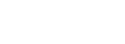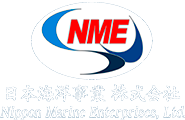月や火星の表面さえ、誰もが高精度で見られるこの時代。しかし、私たちは海の底のことをほとんど知りません。ニッポンの若き研究者、そして技術者が、知と情熱で挑む深度4,000メートルの「深海底」。いざ、未知の世界へー。
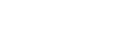

中谷 武志
Takeshi Nakatani

ソーントン ブレア
Blair Thornton

西田 祐也
Yuya Nishida

大木 健
Takeshi Ohki

長野 和則
Kazunori Nagano

増田 殊大
Kotohiro Masuda

稲葉 祥梧
Shogo Inaba

横田 早織
Saori Yokota

各務 均
Hitoshi Kakami

片桐 昌弥
Masaya Katagiri

石川 暁久
Akihisa Ishikawa

高江洲 盛史
Morifumi Takaesu

佐野 守
Mamoru Sano

小寺 透
Tohru Kodera

高尾 淳
Jun Takao

小島 淳一
Junichi Kojima

西谷 明彦
Akihiko Nishitani

進藤 祐太
Yuta Shindo

麻生 達也
Tatsuya Aso

久野 光輝
Mitsuteru Kuno

小池 哲
Tetsu Koike

倉本 佳和
Yoshikazu Kuramoto

徳長 航
Wataru Tokunaga

南野 直人
Naoto Minamino

藤森 英俊
Hidetoshi Fujimori

山北 好美
Yoshimi Yamakita

亀井 雅彦
Masahiko Kamei

杉山 真人
Masato Sugiyama

安蒜 孝政
Takamasa Ambiru

大久保 隆
Takashi Okubo
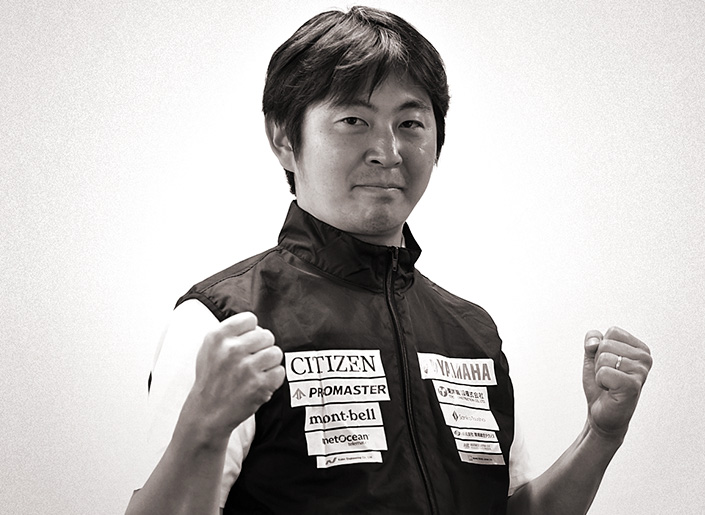
中谷 武志 Nakatani Takeshi
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
Team Leader
Board of Directors
Project Management
GO BEYOND 前進あるのみ!
大会のコンセプトは、ロボットだけで自律的に海中探査を行える世界を実現することであり、まさに我々が描いてきた将来ビジョンに通じるものがあります。この大会に参加して技術を磨くことが、次世代のAUV/ASV技術開発に大いにプラスになると考えました。上位を獲得し、世界を"あっ!"と言わせるとともに、日本の高い技術を形として示していきたいと思います。チームでは、リーダーとしてビジョンを示すとともに、現場でメンバーと熱い議論を重ねながらプロジェクトを進めています。スポンサー・サプライヤー様ならびに、支援や応援をしてくださっている方々への感謝の気持ちを胸に、素晴らしいチームメンバーとともに全力投球して参ります。
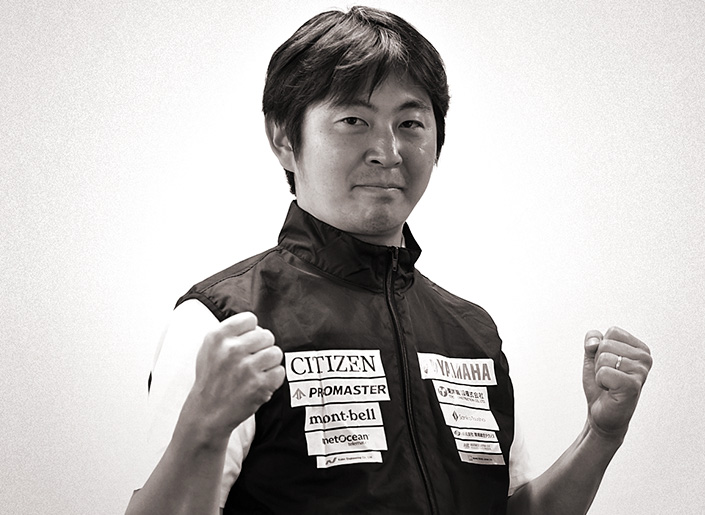
中谷 武志 Nakatani Takeshi
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
Team Leader Board of Directors Project Management
経歴/Career
●海洋研究開発機構(JAMSTEC) 海洋工学センター 技術研究員。2009年、東京大学大学院工学系研究科環境海洋工学専攻にて博士(工学)を取得。日本学術振興会ならびに東京大学の研究員を経て2011年より現職。専門は海中ロボット学。JAMSTECでは、これまで主にたんさ3兄弟(じんべい/ゆめいるか/おとひめ)の開発に従事。遊び心を持った研究精神と妥協を許さない厳しい姿勢で"未知なる深海"に挑戦中です!

ソーントン ブレア Blair Thornton
[ 東京大学生産技術研究所 ]
Board of Directors
Coming soon...

ソーントン ブレア Blair Thornton
[ 東京大学生産技術研究所 ]
Board of Directors
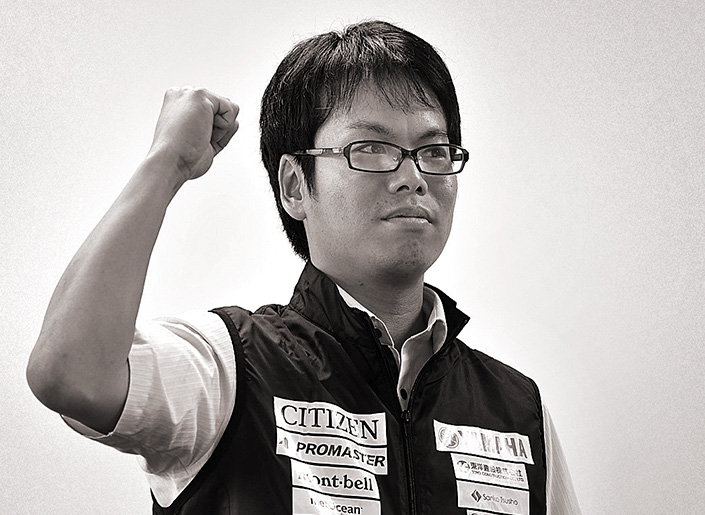
西田 祐也 Nishida Yuya
[ 九州工業大学 ]
Board of Directors
Development & operation
All Japanが切り開くAUVによる海底調査時代!!
石油業界大手のRoyal Dutch Shellがメインスポンサーであることから、Shell Ocean Discovery XPRIZEの競技内容は、言わば世界規模で望まれているニーズの一つであると言えます。これまで海関係の研究者に対して、様々な分野の方から要望を言われることは多々ありましたが、これほど明確で具体的な目標が掲げられたことありません。私を含む若手研究者の4名はこの世界規模のニーズに答え、日本が持つ海洋技術を世界に轟かせようと強く思い、Team KUROSHIOを結成しました。Team KUROSHIOは海中ロボットの開発から運用、解析、通信に関する様々な機関で構成されており、まさに海の「All Japan」といえるチームです。我々が今後の世界の海底調査を牽引して行くという熱い気持ちを持って、Shell Ocean Discovery XPRIZEに挑戦しようと思います。
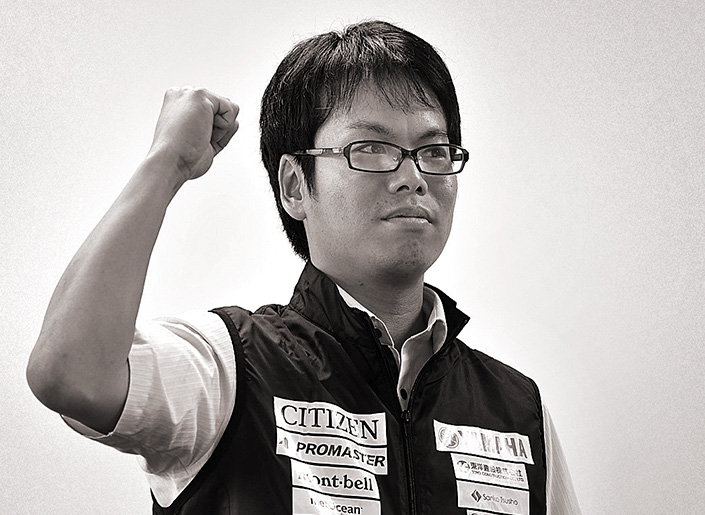
西田 祐也 Nishida Yuya
[ 九州工業大学 ]
Board of Directors Development & operation
経歴/Career
●2012年に東京大学生産技術研究所の特任研究員に就任した後から、本格的な海中ロボティクスの研究を開始しました。在籍中はAUV(自律型海中ロボット)やASV(洋上中継器)の開発、複数台AUVを用いた効率的な調査手法の開発に携わり、それらを用いて海底資源の調査に従事しました。2015年に九州工業大学の特任助教に就任してからは、生物捕獲AUVや3次元計測システムの研究・開発を中心に行っています。

大木 健 Takeshi Ohki
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
Board of Directors
Project Management
Development & operation
私たちのすぐそばにある未知の世界「海底」をロボットで探りたい。
もともと陸上や宇宙の移動探査ロボットから海中ロボット分野に研究フィールドを移した私は、Shell Ocean Discovery XPRIZEでの海底調査の話を最初に聞いたとき,「海底の地形がいまだ全然分かっていない」ことを初めて知り驚きました。こんなにも探査のしがいのある、誰も見たことがない世界が、宇宙よりも遥かに近い私達のすぐそばにあり、その探査に挑戦できる機会に恵まれたのです。これは挑戦するしかないと思いました。最初は私を含め4人の研究者でアイデアを出すところから始まった小さなチームでしたが、現在は”KUROSHIO”という名前となり、8機関共同の大きなチームとなりました。現在私はチームの共同代表として、開発運用の進捗管理や国際輸送の準備、広報活動や資金獲得活動など、状況に応じてチーム全体のマネジメントを行っています。

大木 健 Takeshi Ohki
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
Board of Directors Project Management Development & operation
経歴/Career
●海洋研究開発機構(JAMSTEC) 地震津波海域観測研究開発センター 技術研究員。2013年、東北大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻にて博士(工学)を取得。東北大学の博士研究員等を経て2014年より現職。専門は移動ロボティクス、海底ケーブルシステム。JAMSTECでは、大規模な地震津波観測監視システム”DONET”構築プロジェクトに従事。2016年より、Shell Ocean Discovery XPRIZEに挑戦する日本チーム”Team KUROSHIO”の共同代表を務めています。

長野 和則 Kazunori Nagano
[ 東京大学生産技術研究所 ]
Development & operation
“Kuroshio” - 日本(海流)の技術で世界最大規模の流れを。
私は、水中関連技術が好きだ。ROV(遠隔操作型の無人潜水機)では、マンガやアニメ、映画でしか聞いたことのない”アンビリカルケーブル”が本当に使われている。AUVは完全に人の手を離れ、ドローンのように調査を行う。ただドローンと違うのは、環境がちょっと過酷なところ(電波が使えない、耐圧容器がないとつぶれる外圧、数ノットの水の流れがある、調査場所が数千メートルの距離など)だけ、それが難しい。このような水中関連技術において、日本の存在感を示すために世界中と競うShell Ocean Discovery XPRIZEは重要だ。ROVもAUVもロボットであり、ロボットといえば、日本(のアニメ)だろう。水中においてもロボットといえば、日本(の技術)といわれることを目指し、参加を決意した。メインの役割は「AUV:AE2000-f」とそのペイロード「SeaXerocks3」のオペレート、メンテナンス、データ処理のすべてを行う。それ以外では開発グループに属し、AUV本体、観測装置、データ処理、AUVの調査海域までの輸送などにかかわり、開発を行っている。

長野 和則 Kazunori Nagano
[ 東京大学生産技術研究所 ]
Development & operation
経歴/Career
●東京大学生産技術研究所にて、ソーントン・ブレア准教授のもとで水中関連技術を研究。小型ROV運用や水中機器の開発/運用、AUV開発/運用を行ってきた。関東大震災後の海底状況の調査や福島原発事故後の海底土放射能調査、海底資源コバルトリッチクラストの賦存量調査など、種々のプロジェクトに参加。現在は、AUV等水中機器を専門家以外でも使えるようにすることを目指している。

増田 殊大 Kotohiro Masuda
[ 東京大学生産技術研究所]
Development & operation
勝負は、たったの1秒!世界初の海中ロボットの自律分離・観測を成功させる!
ASVとAUVの切り離し装置を担当しています。 例えるなら、ロケットの切り離しです。数々の試練を越え、目的地に辿り着いたとしても、”切り離し”がうまくいかなければ、全てが水の泡となります。”波と流れ”のある状況で、“精密機器”を自動的に分離するというのは極めて高度なノウハウと信頼性を要求されます。これまでは、手動で”やさしく”海に下ろすのがAUVの扱い方だったので、荒々しく見通しの悪い海で、自動的に分離して観測を行うというのは、大変なステップアップなのです。僕のシゴトは、『1秒以内』に全てが終わってしまいます。その瞬間の為に、試作・開発・実験を繰り返し行ってきました。はじめは失敗の連続でした。休日返上のKUROSHIOスタイルな開発で、ようやく現場で使えそうなモノが出来上がってきました。しかし、どんなに準備をしても海では何が起きるかわかりません。それでも挑戦し続けて壁を破った時、新たな景色が見えるはずです。

増田 殊大 Kotohiro Masuda
[ 東京大学生産技術研究所]
Development & operation
経歴/Career
●民間企業で産業機器のバックボーンを作っていましたが、「誰も見たことのない、過酷な環境でロボットを動かす」というロマンに突き動かされ、現在は東京大学生産技術研究所 海中観測実装工学センターの特任研究員をしています。海から空まで、ロボットという道具を使うことで人にはできないことをやり、「誰も見たことがないものを、探しに行く」という、”究極の好奇心”だけで作動しています。
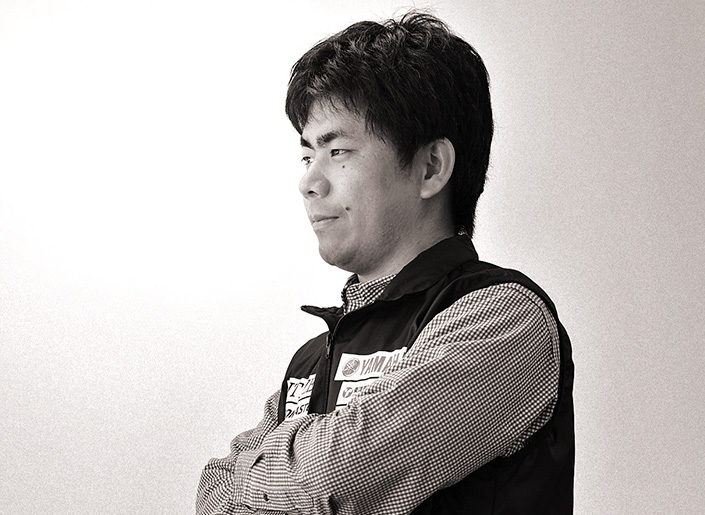
稲葉 祥梧 Shogo Inaba
[ 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 ]
Development & operation
日の丸AUVを日本の海から世界の海へ!
AUV(自律型海中ロボット)が活動する海の中では電波が通じませんので、通信や測位には音波を用いる音響機器が用いられます。しかしAUVからは音響機器の妨げとなる騒音が発生しており、しかも個々のAUVで騒音の生じる周波数の特性が異なります。私の担当はAUVごとに異なる騒音を解析して音響機器の利用できる周波数を調べ、実海域でも音響機器が動作できるよう各AUVで用いる音響機器の帯域を整理・調整する事です。Shell Ocean Discovery XPRIZEを成功させるためには、様々な課題を克服しなくてはなりません。困難な道であり、苦しい事も多く待ち受けているのですが、挑戦を通して得られた知識や経験は他では得難い、貴重な物となるはずです。そして何より、世界一という大きな目標に向かって仲間と取り組むことができるのは幸せな事でもあります。チームの中でも特に未熟者ではありますが、精進して参りますのでご期待下さい。
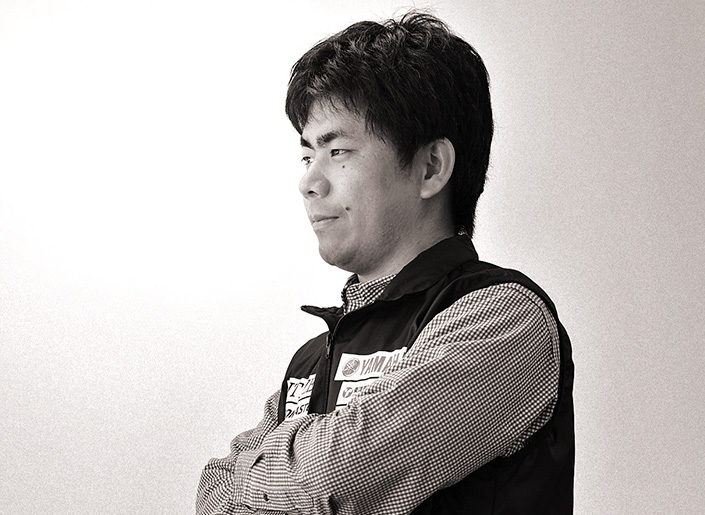
稲葉 祥梧 Shogo Inaba
[ 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 ]
Development & operation
経歴/Career
●海上技術安全研究所入所後はAUVを用いた様々な調査航海に従事し、潜航中のAUVを測位する音響測位装置のオペレーションやAUVに搭載される各種センサー等のデータ解析、AUV潜航時の海中音の計測などを担当してきました。近年では弊所で開発したAUV管制用ASVの主担当に抜擢され、ASVオペレーションのほかAUV管制機能の調整等にも取り組んでいます。

横田 早織 Saori Yokota
[ 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 ]
Development & operation
Coming soon...

横田 早織 Saori Yokota
[ 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 ]
Development & operation

永橋 賢司 Kenji Nagahashi
[ 三井E&S造船株式会社 ]
Development & operation
KUROSHIO技術力×KUROSHIOチーム力=世界を驚かす!
海洋開発は今後、より深い海底へと展開されていきます。そこはJAMSTECを中心に、日本が技術開発を進めてきたフィールドです。いま同じRegulationの下、誰が優れたモノづくりをしてきたか試される時が来たわけです。若手が中心となってこれにチャレンジしていく中で、今までの無人機運用経験を活かしてサポートしていきたいと思います。難しいこのチャレンジの先には、日本の技術への再認識があると信じております。

永橋 賢司 Kenji Nagahashi
[ 三井E&S造船株式会社 ]
Development & operation
経歴/Career
●三井造船(現:三井E&S造船)に入社したときから、ほぼAUV(自律型海中ロボット)開発に携わってきました。1990年代のR-one ロボットの開発から始まり、最新のSIP1号機、2号機の開発まで様々なAUVを開発、運用してきました。

各務 均 Hitoshi Kakami
[ 三井E&S造船株式会社 ]
Development & operation
日本の技術に世界が注目!
Team KUROSHIOでは、競技に使用するASV(洋上中継器)を担当しています。ASVは海底マッピングを行うAUV(自律型海中ロボット)の計測支援を行うほか、海中を航行するAUVと陸上にいる人員の間を中継する役割を持っています。日本の技術が詰まったAUVの能力を、ASVを通して世界に発信する絶好の機会ととらえています。またASVは、海中と陸上をつなぐ中継器であると同時に、無人機と人間をつなぐインタフェースでもあります。無人機と人間は今後どのように関わっていくのか、今回の挑戦を通して考えていけたらと思っています。

各務 均 Hitoshi Kakami
[ 三井E&S造船株式会社 ]
Development & operation
経歴/Career
●主にASV・ROV(有索式無人探査機)等の水上・水中ロボットの設計開発に携わっています。また、これらロボットの運用を支援する周辺機器の開発も行っています。

片桐 昌弥 Masaya Katagiri
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
日本の現場力で世界に挑戦
開発・運用グループメンバーで、Team KUROSHIO内ではAUV(自律型海中ロボット)の運用に従事しています。今回の大会に課せられているミッションは非常に難問であり、これまでの海洋調査技術からレベルを数段アップさせなければ達成できません。チーム一丸となって難問に向き合うことで、自分自身の成長につながると期待しています。また、同じ問題に対して世界の技術者が様々なアプローチで挑むので、他チームの柔軟な考え方を学んでいきたいと思います。

片桐 昌弥 Masaya Katagiri
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
経歴/Career
●日本海洋事業株式会社 深海技術部所属。入社後は有人潜水船「しんかい6500」のコパイロットとして、世界の様々な深海研究を支援した。現在は海底広域研究船「かいめい」の水中機器を運用するチームに配属され、海底資源のサンプリング作業などに従事している。

石川 暁久 Akihisa Ishikawa
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
海洋大国、日本の深海調査技術で世界一を取る!!
開発・運用グループメンバーとして、特にAUV(自律型海中ロボット)の運用について担当しています。15年くらい前、まだ駆け出しだったころ、当時のJAMSTEC理事長に「AUVの石川になる!!」と宣言したことがありました。若さゆえの大分強気な発言でしたが、その一言が今でも私の心の中に残り、自問自答しながらこれまでAUV「うらしま」の運用を行ってきました。はたして、「AUVの石川」になっているのか?Shell Ocean Discovery XPRIZEがその答えを出してくれるのではないかと思い、参加を決意しました。産学官の若いサムライで構成されたTeam KUROSHIOが日本代表として世界を相手に戦ってきます!応援よろしくお願いします!!

石川 暁久 Akihisa Ishikawa
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
経歴/Career
●日本海洋事業株式会社に2000年入社し、現在は深海巡航探査機「うらしま」運航長を務めています。年に半年くらいは調査船に乗って現場でバリバリ働いています。また、「うらしま」の運航を中心に、「しんかい6500」のパイロット業務を兼務。海底地形図のデータ処理、探査機の整備、音響測位、AUV開発に関するコンサルティング、潜水船の操縦、探査機の機能向上など、深海調査に関することは何でもやります。

高江洲 盛史 Morifumi Takaesu
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
深海の小さなデコボコから世界を観る、いくぞKUROSHIO。世界を覆い尽くすまで。
学生の頃、沖縄トラフの海底熱水域を自身の研究対象としていた。海底地形図を基として、その成り立ちや発達過程を知るためだ。当時はまだまだ海洋観測も過渡期にあり、研究のキモとなる海底地形も精度が粗く、水平分解能100m、良くても50mのデータしか取れなかった。広いスケールで成因論を考えるにはこの程度でよいが、熱水域といった局所的なイベントを語ることはこれでは難しい。ここが技術の限界かと感じつつ、海洋観測を仕事として選び数年が経った頃、「うらしま」などのAUVの登場によって、いまだ薄暗かった深海底に眩い光が差し込みだした。数千メートルの海の上から観た粗いデータではのっぺりとした地形だった場所が、AUVで近付いて観てみると実は非常にデコボコとした海底だったのだ。その時の衝撃はいまだに覚えている。今回の挑戦ではさらに細かく、水平分解能5mで海底地形を観るという。海洋観測に携わってきた者として、この挑戦に飛びつかない訳がない。

高江洲 盛史 Morifumi Takaesu
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
経歴/Career
●2003年入社。反射法地震探査の中央制御オペレーターをメインに、これまで約70の調査航海に参加、各種海洋観測データに触れる。観測機器の組立や整備、観測データの処理に携わり、近年では地震津波海域観測網DONETの構築に従事。8年の現場経験の後、JAMSTECに出向し、地震・津波データの処理と管理、データベース構築を成し現場に復帰。直近ではGISを用いた海洋観測のデータベース化を行っている。

佐野 守 Mamoru Sano
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
世界へ挑戦!!
チーム内では、データ処理を担当します。今までAUVで取得したデータ処理は経験があるものの、複数機体を使用したデータを処理した経験はなく、データ処理の難しさに魅力を感じ、参加を決意しました。

佐野 守 Mamoru Sano
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
経歴/Career
●入社後2年間は反射法地震探査のオペレーターを行い、その後現在に至るまで、海洋研究開発機構所属の船舶で取得したデータの管理を行っています。データと言ってもさまざまなデータがあり、その中で海底地形データの管理を行っています。

小寺 透 Tohru Kodera
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
日本の海中探査技術を結集し、若い力で世界一に挑戦!
普段から海洋調査に携わっており、Team KUROSHIO誕生以前からこのプロジェクトに関して意見交換する機会がありました。その中で「新たな海洋コミュニティの創出」や「有人支援母船レス」などのフレーズに心躍りました。なによりも「若手の研究者・技術者による“挑戦”」にとても興奮しました。データ処理担当として参加させてもらいましたが、現在は、若手が存分に力を発揮し、今回の挑戦を誇れるものにすべく、後方支援や調整を行っています。自身が現場に出たい気持ちと日々格闘しています。

小寺 透 Tohru Kodera
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
経歴/Career
●各種海洋調査船に乗船し、多くの調査プロジェクトへの海上技術支援を行ってきました。データ管理部門や事務部門での陸上勤務を経て、DONETプロジェクトに参加し海底ネットワーク構築に従事。現在は、管理業務を行いつつも「かいめい」船上の観測・実験機器の保守管理等を行っています。
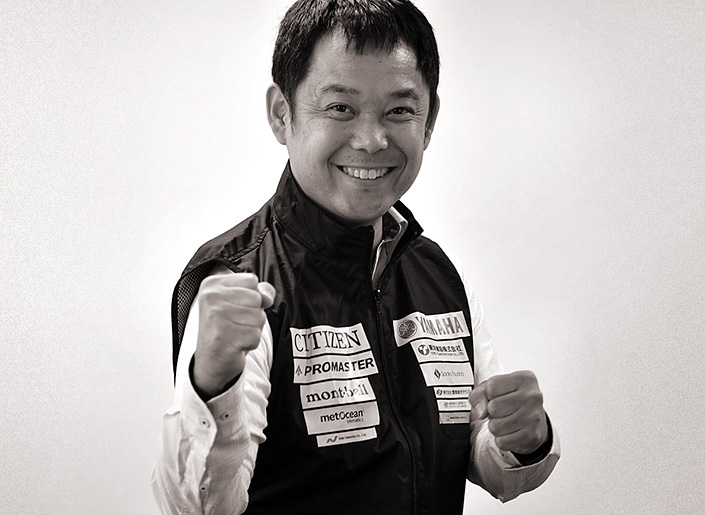
高尾 淳 Jun Takao
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
世界のAUV業界にTeam KUROSHIOの名前を響かせたい!
開発・運用グループメンバー。社内における調整・マネジメント業務、社外関係者との調整、チーム内のマネジメント補佐などを行います。AUV(自律型海中ロボット)の開発・運用を私が直接的に行うことはありませんが、当社からは運用やデータ処理のために多数の人間が関わることになります。彼らの力を存分に発揮させるためにも、様々な社内・社外との調整業務や全体のマネジメントを行う役目が必要と思い、また自分自身の成長のためにも参加を希望しました。今後、世界のAUV業界は右肩上がりに成長して行くものと思います。その中で、AUVのオペレーションに関わって行く我々としても自分自身のレベルを高め、世界の最先端技術を学び続ける必要があり、今回の挑戦はまさにその格好の舞台と思っています。
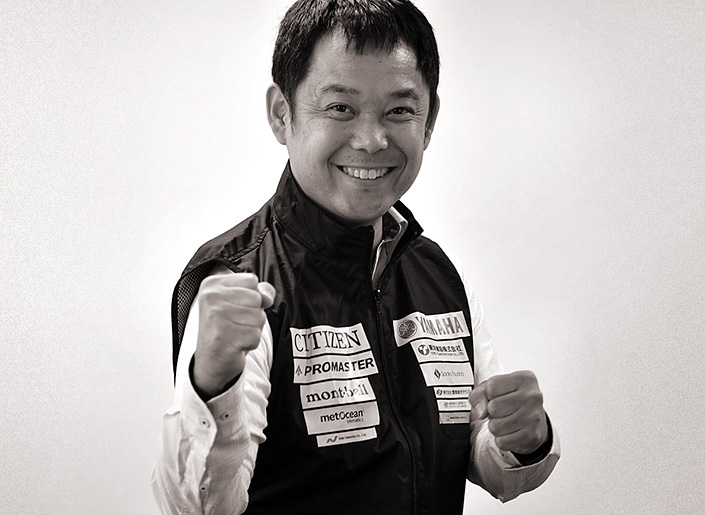
高尾 淳 Jun Takao
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
経歴/Career
●日本海洋事業 総務部/事業企画室所属。調査船の航海士として入社し、AUVのオペレーションを含む様々な海洋調査の業務に従事してまいりました。現在は陸上職員となり、総務部と事業企画室を兼務しています。社内では、契約・予算・新規事業に関する仕事を主に行っています。

小島 淳一 Junichi Kojima
[ KDDI総合研究所 ]
Development & operation
Coming soon...

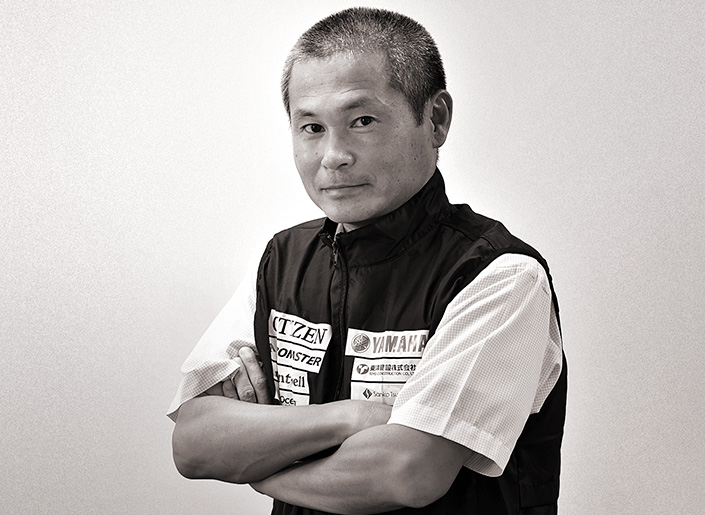
西谷 明彦 Akihiko Nishitani
[ KDDI総合研究所 ]
Development & operation
遠かった深海の夢と可能性を身近な存在に。深海~宇宙~陸地まで繋ぎます。
チーム内では、AUV(自律型海中ロボット)・ASV(洋上中継器)の通信技術・ソフトウェア部分について担当しています。衛星通信技術と水中音響通信技術を駆使し、深海~ASV(外洋)~通信衛星~地球局(日本)~管制局(海外)といった、広大な範囲を繋げられる通信ネットワークを築きます。私自身、海が好きで、海に囲まれた場所で、海からさまざまな恩恵を受け、海に守られ、海と深いかかわりを持って暮らしてきました。いつか自分の技術が、海洋事業に貢献できないかと前々から考えており、何かできることは無いかという思いと、この難関な世界大会にチャレンジしたいという強い思いから、今回参加を決意しました。
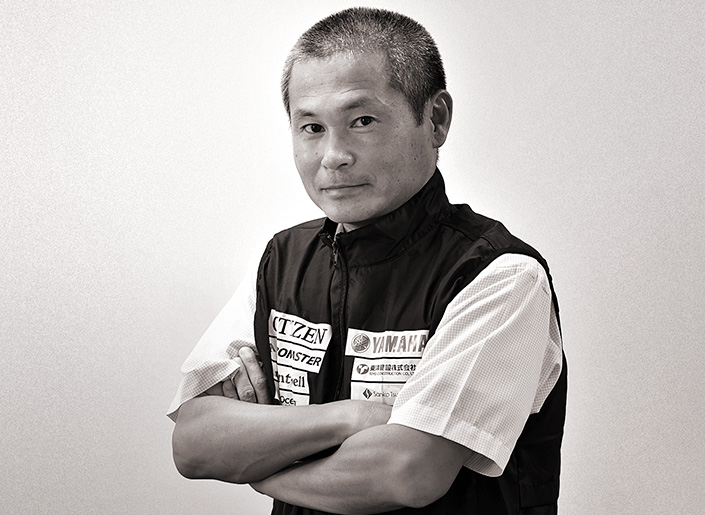
西谷 明彦 Akihiko Nishitani
[ KDDI総合研究所 ]
Development & operation
経歴/Career
●KDDI総合研究所入所後は、分散ファイルシステム技術や、サイレント障害検知技術などのデータ分析技術、およびデータ分析用クラスタ技術に関わる研究に従事してきました。現在は、市場分析や未来予測を行うシンクタンク部門と兼務し、水中音響通信機器の研究開発に取り組んでいます。

進藤 祐太 Yuta Shindo
[ ヤマハ発動機株式会社 ]
Development & operation
地球に残されたフロンティアに挑戦!
Shell Ocean Discovery XPRIZEは一種のレースだと思います。私はレースが大好きです。また、私が所属しているヤマハ発動機という会社は創立以来レースに取り組み続けてきた会社です。そして、「挑戦」を大切にする会社です。ある日、Team KUROSHIOの取り組みを聞く機会があり、その時に初めて地球の海底地形のほとんどが非常に粗い精度でしか分かっていないという事実を知って驚いたのと同時に、「このレースに挑戦し、海底地形を解き明かしたい!」と強く思ったことがきっかけで私の挑戦が始まりました。私個人としても会社としても海中・海底というのは未経験の領域ですが、海洋技術のスペシャリストが集うTeam KUROSHIOの中で日々学びながら、この魅力的なレースに挑戦します!

進藤 祐太 Yuta Shindo
[ ヤマハ発動機株式会社 ]
Development & operation
経歴/Career
●ヤマハ発動機に入社後、一貫してモーターサイクル(オートバイ)の商品設計を担当し、先進国向け・新興国向け共に多種多様な開発プロジェクトに携わってきました。Team KUROSHIOに参加してからは海洋研究開発機構内に籍を置き、XPRIZEに100%注力して取り組んでいます。

麻生 達也 Tatsuya Aso
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
Development & operation
Team KUROSHIOが躍動する様を、皆さんに見せたいね
「とにかく面白そう」 この大会のルールについて知った時、この業界未経験の私でも技術的な難易度がとても高いことが瞬時に理解できました。しかし、だからこそ我々が挑戦する意味があり、私の奥底から湧き上がるワクワクが止まらず、Team KUROSHIOへ参加せずにはいられませんでした。 チームでは、スムーズに海外への機器の輸送が行えるようにリストの作成、必要な機材等の発注などを担当しております。課題を着実に乗り越えていくチームメンバーの姿を見ていると、とても頼もしいです。

麻生 達也 Tatsuya Aso
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
Development & operation
経歴/Career
●海洋研究開発機構(JAMSTEC) 海洋工学センター 技術系職員。今年3月、東京理科大学大学院理学研究科物理学専攻にて修士(理学)の学位を取得。専門は超伝導。大学院時は産業技術総合研究所にて鉄系超伝導線材の開発を行っておりました。「しんかい6500」のカッコ良さに惹かれて本年度の新卒としてJAMSTECに入構。所属先ではAUV「ゆめいるか」に関する業務に従事。新人としてフレッシュな風を運び込めるようにと日々頑張っております。

久野 光輝 Mitsuteru Kuno
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
日の丸を背負い世界へチャレンジ!
Team KUROSHIO内では主にAE2000aが取得するインターフェロメトリーソーナー(GeoSwath)のデータ処理を担当。観測技術員として培ってきたこれまでの知見を活かして、AUVの仕組みや癖を理解したうえで最も効率的・効果的な処理内容を事前検討して本番を迎えたい。参加したきっかけは、当社の先輩社員が参加しているのを横目で見ていた際、技術者として単純に興味がわき、データ処理の専門家ではないが、やる気でカバーするとして兎にも角にも手を挙げたのがきっかけ。様々な機関の技術者と一緒に仕事をすることで良い刺激を受け、自身の力量をあげることで海洋観測業界に少しでも貢献できればと思う。

久野 光輝 Mitsuteru Kuno
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
経歴/Career
●2007年に日本海洋事業へ入社、海洋科学部に配属となる。以後4年間は反射法地震探査のオペレーターとして各種整備作業、曳航物の設計、製図など、機械工学系の分野を中心とした業務に携わる。その後、現在の所属に配属となり、簡易型反射法地震探査のオペレーターとして、データ処理を含む反射法全般の業務に従事。この他、横浜研究所における船舶取得データ(重磁力、海底地形等)のデータ処理業務にも携わる。
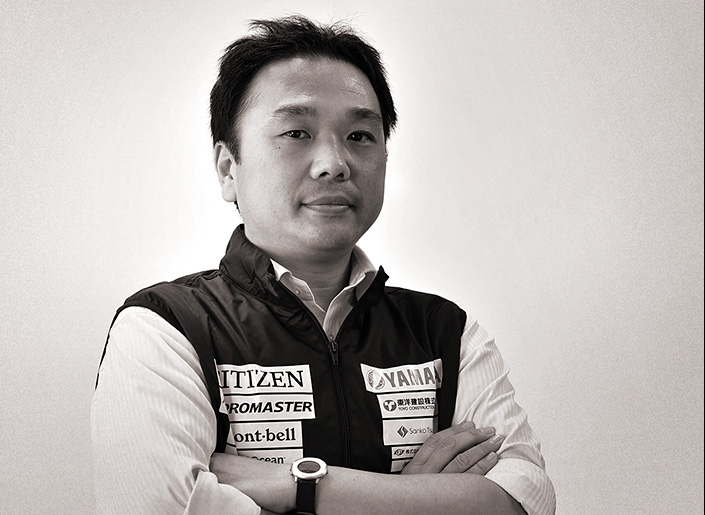
小池 哲 Tetsu Koike
[ 東京大学生産技術研究所 ]
Development & operation
未来水域へ。Aquatic Zone to the Future.
チームではAUV(自律型海中ロボット)のメンテナンスおよび計測した海底地形データの解析作業を行います。共同研究員として所属する東京大学生産技術研究所から、チームに参加することになりました。ナローマルチビーム音響測深機のサービスエンジニアとしての経験や、水産環境調査の経験、調査機器の制御ソフトウエア開発の経験を生かし、チームに貢献したいと存じます。これまで主に水産業に係わる仕事を行ってきましたが、海洋にはまだまだ開発できる産業資源があります。今回の挑戦によって海洋産業への注目度が上がり、その研究開発がより盛んになることを期待しています。
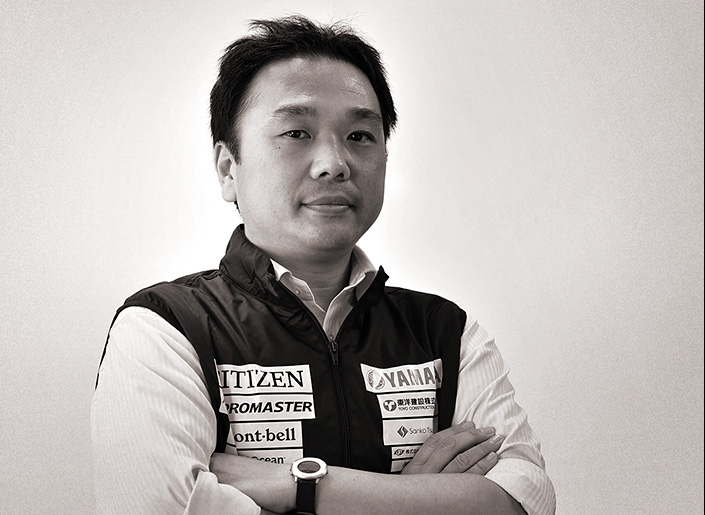
小池 哲 Tetsu Koike
[ 東京大学生産技術研究所 ]
Development & operation
経歴/Career
●学生時代は魚類の研究を行い、当初は魚類や鳥類の生息状況調査を主に行っていました。その後、音響探査機器の代理店としてハードウエアとソフトウエアの技術サポートを行うとともに、海底地形探査業務を行ってきました。2015年から東大生産技術研究所で民間等共同研究員として海底資源調査やAUVの運用に携わっています。

倉本 佳和 Yoshikazu Kuramoto
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
日本の観測現場の最前線を支える技術で未知の海底に挑戦
チーム内ではAUVに搭載されたマルチビーム音響測深機で取得したデータを地形図にする処理を担当しています。今回のShell Ocean Discovery XPRIZEを通して多くの機関の方々と同じ目標に向かって挑戦し、新しい技術に触れることで自分自身も成長できればと思い参加を決意しました。どうぞ宜しくお願いします。

倉本 佳和 Yoshikazu Kuramoto
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
経歴/Career
●日本海洋事業株式会社2010年入社。JAMSTECの研究船「なつしま」・「かいれい」・「よこすか」にて海底地形データ処理と探査機の整備・音響測位を担当。

徳長 航 Wataru Tokunaga
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
いつか若い世代、いつかAIに取って代わられるかもしれません。でも今は、私たちにしかできないかもしれない。海底地形データの処理は「大胆かつ繊細に」、そしてかつ「迅速に」、やってみます。
取得された海底地形データの処理、作図を行います。地図や地形が好きです。見ていて飽きません。ましてや自分の手で海底地形図を作り上げることができる。参加しない理由はありません。

徳長 航 Wataru Tokunaga
[ 日本海洋事業株式会社 ]
Development & operation
経歴/Career
●海洋地球研究船「みらい」における観測技術員として、マルチビーム音響測深装置をはじめとする観測装置の保守、運用を行っています。第54次、第55次南極地域観測隊隊員(夏隊)として、南極海周辺の海底地形調査も行いました。また、「しらせ」が座礁した際は水中カメラを用いて船底の損傷状況の調査を行いました。

藤森 英俊 Hidetoshi Fujimori
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
General Affairs
チームが一丸となって、スタートラインに立てるようにしたい。
チームの初期の段階で中谷さん、大木さんから話を聞き、この挑戦に関わることとなりました。各種の申請や手続き、国際輸送や現地での支援体制の検討、種々の取りまとめなど、主に後方支援を担当しています。今回の挑戦では、海中ロボットなどの調査機器を輸送し、現地で整備/調整を行なって海底地形の調査を行うことが必要で、これだけの規模のものは経験がありません。これらがうまくいくように準備を整えていくのも、大きな”挑戦”と思っています。

藤森 英俊 Hidetoshi Fujimori
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
General Affairs
経歴/Career
●海洋科学技術センター(JAMSTECの前身)に入所し、海洋音響トモグラフィー技術の研究開発という、海中に音波を長距離伝搬させ、その間の水温や流速を計測する技術の開発を行なっていました。その後、各種の研究支援や外部資金の手続、予算の獲得、広報関係等、様々な業務に携わってきました。現在は、次世代深海探査システムに関することや外部資金に関すること、全体の取りまとめ等を行なっています。

山北 好美 Yoshimi Yamakita
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
General Affairs
Go!Go! Team KUROSHIO! 一丸となって未知のフロンティア解明へ!
JAMSTEC内Team KUROSHIOウェブサイトの管理、ポスターやロゴシール作成などの仕事を担当しています。Team KUROSHIOメインメンバーとたまたま同じ部署に居合わせた関係でお声掛け頂き、お手伝いすることとなりました。裏方中の裏方ですが、未知のフロンティアへの挑戦へ微力ながら関わることができ大変光栄です!

山北 好美 Yoshimi Yamakita
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
General Affairs
経歴/Career
●学生時代は渡り鳥の研究を、畑違いのCAE・金型業界での仕事を経て、2014年にJAMSTECに入所。CAD・CAE・3Dプリンターを駆使して深海探査に使用する機器の開発支援、イラストをいじってポスターやプレゼン資料作成のお手伝い等をしています。

亀井 雅彦 Masahiko Kamei
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
Communication
メンバーがチャレンジに集中できるよう足場を支えます。頑張れ!
国内にはAUV(自律型海中ロボット)を保有し日々の活動に利用している組織が幾つかあるにも関わらず、使い方やノウハウがそれぞれ独自でした。ミッションに応じたAUVを開発していたという事情もあったと思います。独自に運用しているAUVを複数組み合わせて新しい使い方にチャレンジするには、保有する組織間の協力なしには成功は見込めません。技術についてはわかりませんが、私のような者でも組織間のつなぎ役としてならば役に立てるであろうと思い、参加を決意しました。

亀井 雅彦 Masahiko Kamei
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
Communication
経歴/Career
●民間企業を経て、現職に就く。所属先では、経営管理部門での企画・調整事務に従事。現在は「海洋科学技術からのイノベーション」という長距離マラソンを邁進しているところ。民間企業等へ研究開発成果の展開に注力中。

杉山 真人 Masato Sugiyama
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
Communication
Team KUROSHIOのつなぎ役!
Team KUROSHIOのスポンサー・サプライヤー様との調整や、チームイベントの企画、WEB・SNSの運営などを行っています。多くの方々にチームの活動を知っていただき、チームメンバーのアツい想いと将来性、XPRIZEというコンペティションの先進性や国際性というイメージに共感していただき、一人でも多くのサポーターを獲得することが私の役割です。また、チーム内のコミュニケーションも欠かせません。チームには8機関から30名超の若手研究者・技術者が参画していますが、それぞれ本業を抱えつつも、自分たちの技術レベルを世界に示すべく、日夜アツい議論・技術開発・準備を行っています。時には意見の衝突もありますが、参画メンバーがそれぞれの立場を超えて真にひとつの「チーム」となれるよう、ギャップを埋める役割もしています。Team KUROSHIOのチャレンジを成功させ、その先にある新たな海洋産業の創出を目指して、チーム内外をキッチリと繋いでいきます。

杉山 真人 Masato Sugiyama
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
Communication
経歴/Career
●2004年3月JAMSTEC入所。文部科学省研究開発局やNOAA(米国海洋大気庁)での勤務を経て2015年7月より現職。JAMSTECと他機関との連携促進、イノベーション促進施策の企画立案を行っています。

大久保 隆 Takashi Okubo
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
Communication
KUROSHIOのアツさを世界へ!
「大変だが面白い仕事がある。お前も加わらないか」この上司の一言がShell Ocean Discovery XPRIZE、Team KUROSHIOとのファーストコンタクトでした。社会人1年目(当時)の勢いに任せて加わったTeam KUROSHIO、上司の言葉通り、その仕事は想像以上に大変でした。ですが、世界的な暖流「黒潮」のような「アツさ」が、確かにそこにはありました。何もかもが未経験で右往左往な日々を送っておりますが、世界の人々にTeam KUROSHIOのほとばしる「アツさ」を伝えるべく、これからも前進して参ります。

大久保 隆 Takashi Okubo
[ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 ]
Communication
経歴/Career
●大学時代はサケ科魚類の研究に従事し、2016年4月JAMSTEC入所・現職。杉山とともにJAMSTECと他機関との連携促進、イノベーション促進施策の企画立案等をメインに行っています。