気候変動下で利根川からサケが消えたのはなぜか?

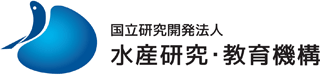

国立研究開発法人水産研究・教育機構
国立大学法人東京大学
1. 発表のポイント
- 利根川は北太平洋西部におけるサケ(Oncorhynchus keta)※1 の分布域の南限である。しかし、利根大堰でのサケの遡上データ※2 により観察された親魚の数は2013年以降急減し、2024年にはゼロになった。
- サケ個体群の減少要因を明らかにするため、JAMSTECの地球シミュレータで得られた海洋再解析データJCOPE2M※3 の再解析値を基に、サケ稚魚に見立てた粒子の追跡シミュレーションを実施した。
- シミュレーションの結果、海流の変化が稚魚の北上に及ぼす影響や致死に至る水温の限界値を考慮したいずれのシナリオでも、近年の減少は説明できなかった。
- 一方で、黒潮・黒潮続流と親潮の北偏に起因する平均水温の上昇と動物プランクトン量の減少が利根川のサケの個体群成長率の低下と相関し、さらに平均水温よりも動物プランクトン量が主要因となり、サケ稚魚の生残に影響を及ぼしたことが示唆された。
サケ(Oncorhynchus keta)
北太平洋でもっとも広域に分布するサケ属の魚。
サケの遡上データ
独立行政法人水資源機構による調査。
(https://www.water.go.jp/kanto/tone/water/fish-data/)
JCOPE2M
JAMSTEC アプリケーションラボが公開している海洋の再解析値の同化データで、1993年から現在までのデータが利用可能。
(https://www.jamstec.go.jp/jcope/htdocs/distribution/)
2. 概要
国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸、以下「JAMSTEC」という。)付加価値情報創生部門アプリケーションラボのYu-Lin Chang (ユリン チャン)副主任研究員は、水産研究・教育機構水産資源研究所の本多 健太郎グループ長、東京大学大気海洋研究所の森田 健太郎教授とともに海洋の再解析データと20年間(2001~2020年)に及ぶサケ稚魚に見立てた粒子の追跡シミュレーションを行うことによって、利根川サケの近年の個体数減少の要因を調べました。
シミュレーションの結果、遊泳戦略の違いや致死水温の限界値の追加に関わらず、近年の個体数減少を再現するシナリオは存在しませんでした。一方で、個体群成長率の低下は、黒潮・黒潮続流と親潮の北偏による水温上昇とサケ稚魚の餌である動物プランクトン量の減少と相関していました。本州太平洋側のサケ稚魚の移動経路上では、冷たく栄養豊富な親潮に代わって、温かく栄養の少ない黒潮・黒潮続流が流入し、水温上昇と動物プランクトン量の減少を引き起こしていることがわかりました。平均水温と動物プランクトン量の偏相関分析※4 では、後者の動物プランクトン量が利根川サケの個体群成長率と一貫して関連する主要因であることが示されました。動物プランクトン量の減少は、サケ稚魚の成長と生存に影響を及ぼし、個体群成長率を低下させたと考えられます。
黒潮・黒潮続流と親潮の北偏は、気候変動の影響によって今後も継続するのか、あるいは南側へ戻る可能性もあります。このことは、利根川サケの今後の個体群成長率、とりわけ、再び親魚の遡上が見られるかどうかに大きく影響するでしょう。
本研究はJSPS科研費(23K03503、24K01833)の助成を受けたものです。また、本成果は、「PLOS One」に9月11日付け(日本時間)で掲載されました。
Beyond lethal temperatures: Factors behind the disappearance of chum salmon from their southern margins under climate change
- 海洋研究開発機構 付加価値情報創生部門
- 水産研究・教育機構 水産資源研究所
- 東京大学 大気海洋研究所
偏相関分析
2つの変数の関係性を分析する際に、それらの関係に影響を与えている他の変数の影響を統計的に取り除いた上で相関を計算する手法のこと。
3. 背景
気候変動が生物に与える主要な影響の一つは、その地理的分布の変化であり、特に海洋生物は陸上生物に比べて変化が顕著です。北半球のいくつかの海産魚種では、水温上昇により分布域が北方へ移動し、その分布域の南限から消失する現象が観察されています。水温の上昇と海洋生物の北方への移動はよく相関しますが、その根本的なメカニズムは実はよくわかっていません。サケ(Oncorhynchus keta)はサケ属の中で最も広域に分布する種です。北太平洋に広大な回遊範囲を持ちながら、特定の母川に帰って繁殖する驚くべき帰巣能力を有します。分布域の南限に位置する個体群は、母川と隣接する沿岸域で高水温に曝されるだけでなく、北方の索餌海域までより長い距離を移動する必要があるため、高緯度地域の個体群よりも大きな課題に直面しています。
関東平野を流れる利根川は、北太平洋西部におけるサケの分布域の南限の一つです(図1a)。利根川の利根大堰で計数されるサケの親魚の数は2000年以降増加し、2013年に18,000尾を超えてピークに達しましたが、その後減少が続き、2024年にはゼロになりました(図1b)。利根川サケの個体群成長率は2010年まで概ね正の値で推移しましたが、2011年に負に転じ、以降最低値を更新するような状態が続いています(図1c)。

図1. (a) 研究海域と粒子の追跡期間(2001年2月中旬から2020年7月中旬)における5m深の平均流速。利根川(緑の星)を起源とするサケ(Oncorhynchus keta)の潜在的な移動経路をマゼンタ色で示す。実線は先行研究による、破線は推定による経路。(b) 1990年から2024年までの利根川河口の上流150kmに位置する利根大堰で計数されたサケ親魚の数。(c) 1世代を4年と仮定した利根川サケの個体群成長率。写真はそれぞれ2018年11月に撮影された(b)利根大堰、(c)魚道の観察窓で撮影されたサケ親魚。
4. 成果
本研究では、利根川サケの個体数減少の要因を明らかにすべく、海流、水温、餌の量(動物プランクトン量)の3つの要因の影響を分析しました。利根川の河口に放流された仮想のサケ稚魚の分散過程を、海流による輸送と能動的な遊泳行動を組み込んだ粒子追跡モデルを用いて、20年間(2001~2020年)シミュレーションしました。この数値シミュレーションの結果と、水温および動物プランクトン量の再解析データを用いて、サケの分布域南限における近年の個体数減少に寄与する主要因の特定を試みました。
20年間におよぶサケ稚魚に見立てた粒子の追跡シミュレーションの結果では、選択した遊泳戦略の違い(図2a)や致死水温の限界値の追加に関わらず、観察された個体群成長率の低下を再現できませんでした。これにより、海流や致死水温が重要な要因ではないことが示唆されました。一方で、個体群成長率の低下は、黒潮・黒潮続流と親潮の北偏による水温上昇とサケ稚魚の餌である動物プランクトン量の減少と相関していました。ただし、偏相関分析の結果、水温は重要でなくなり、動物プランクトン量のみが有意な要因として残りました(図2b, c)。これらの結果は、海洋生活初期に動物プランクトンをどれだけ利用できるかが、サケの個体群成長率を説明する唯一の要因であることを示しています。黒潮・黒潮続流と親潮の北偏は、気候変動の影響によって今後も継続するのか、あるいは南側へ戻る可能性もあります。このことは、利根川サケの今後の個体群成長率、とりわけ、再び親魚の遡上が見られるかどうかに大きく影響するでしょう。

図2. (a) 2001年から2020年に利根川河口から放流された仮想のサケ稚魚の北海道太平洋側沿岸への到着率(%)。偏相関分析の結果:(b) 平均水温と(c) 初期の動物プランクトンの利用可能量がサケの個体群成長率に与える影響(数値は標準化スコア)。動物プランクトンと個体群成長率の関係は、偏相関係数r値から中程度の相関(絶対値で0.4~0.6)があり、p値から統計的に有意(0.05以下)であることがわかる。
5. 今後の展望
本研究では、川から海に降った後の数ヶ月間におけるサケ稚魚の初期減耗に焦点を当てました。気候変動下で、黒潮・黒潮続流と親潮の北偏は、利根川から北方へ移動するサケ稚魚にとって深刻な餌不足を引き起こしていると考えられました。
気候変動の影響は稚魚期にとどまらず、成魚の成長率と成熟率の低下に加え、川に帰った際に高水温に曝される機会の増加をもたらす可能性があります。これらにより、繁殖地まで到達できない個体の増加も懸念されます。さらに、分布域の南限付近では、河川内での繁殖と仔稚魚の生存は、水温上昇に一層敏感である可能性が考えられます。これらの影響を包括的に理解することが、今後の研究を進める上で重要です。
本研究のお問い合わせ先
付加価値情報創生部門アプリケーションラボ
副主任研究員 Yu-Lin Chang (ユリン チャン)
教授 森田 健太郎
グループ長 本多 健太郎
報道担当
企画部門海洋科学技術戦略部報道室
経営企画部広報課
共同利用・共同研究推進センター 広報戦略室