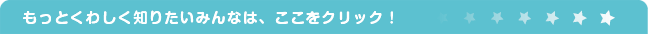2010年5月25日発表
駿河 湾 での地震 による海底地すべりのあとを発見!
2009年8月11日に静岡県を中心に広い


(解説3)
駿河湾での地震の

図1:駿河湾での地震
では、その津波はどうやって発生したのでしょう。それを解き明かそうと、研究者はコンピュータ上で津波を再現しようとしました。けれども、原因とされた断層をもとにした計算から再現できる津波は小さく、


海底地すべりを横と正面から見てみましょう(図2)。

図2:海底地すべり
海底地すべりの原因は、地震。海底地すべりが起きて海底が大きくへこむと、そこにたくさんの海水がいっきに流れこみます。それによって海水全体が上下するので、海底の変化がそのまま海面にあらわれます。その動きがうねりとなり広がって、津波となるのです。その津波は部分的に大きくなったり、また、浅い海では海底をはうようにして流れるのでどろをたくさんふくんだりして
「海底地すべりが、津波を大きくさせたのかもしれない。」研究者はそう考え、確かめるために駿河湾の調査に出ました。海底地すべりあったのなら、そのあとが残っているはず。それを、広い海底から見つけ出そうというのです。


2009年12月から2010年3月にかけて、3回の調査を行いました。調査で大かつやくしたのが、海洋調査船「なつしま」(解説4)、海中ロボット「うらしま」、そして「ハイパードルフィン」(解説5)(図3)。「なつしま」と「うらしま」は音波(参考:2009年8月6日発表)で、ハイパードルフィンは水中カメラで海底地形を調べます。これらがあれば、目では見えない真っ暗な海底でも、何がどこにあるのかわかります。

図3:調査した海域
そうして得られた海底地形図を地震前のものと比べると…。焼津沖5kmの水深600mで、以前の調査では見られなかったガケを発見したのです!そのガケの形は馬てい型で、幅約450m、高さ約10〜15mでした。さらに、そこから谷に向かって

図4:地すべりのあと
さらに、海洋深層水をくみ上げるために海底に設置されている管が、2km以上おし流されているのも発見しました(写真)。静岡県では、駿河湾での地震を境に、深層水をくみ上げる管がこわれ、深層水の

写真:うもれている管


駿河湾での地震の震源は、東海地震の震源域に位置しています(図5)。ですから、駿河湾地震で海底地すべりが起きたのなら、東海地震の時にも起きて、津波を引き起こす危険があります。

図5:東海地震を引き起きそうな震源域
それにそなえて対策をたてるために、研究者は今後、断層だけではなく海底地すべりのデータも計算に加えてさらにくわしいシミュレーションを行います。また、計算だけではなく実際に海底を観察したり、どろをとって調べたりする予定です。研究者は、「地震、津波、地すべりの関係をくわしく調べることで、津波予測の精度を高めて社会に役立てたい」、と話しています。
解説1:うらしま
うらしま:

解説2:馬てい型
馬の足のうら、ひづめの形のことです。

解説3:マグニチュードと震度のちがい
マグニチュードとは地震のエネルギーの大きさ(
解説4:海洋調査船「なつしま」
無人探査機「ハイパードルフィン」の母船として

解説5:ハイパードルフィン
最大3000mまでもぐれます。超高感度ハイビジョンカメラをもっているので、深海の

解説6:駿河湾深層水施設
ここでは、2本の管で水深340mと水深680mからそれぞれ海洋深層水をくみ上げていました。深い海からくみ上げる海水、その水温はもちろん低くひんやりしています。けれども、地震後から、水深680m管のくみ上げる海水の温度が上がってしまったのです。「どこかで管が切れて、深層水ではない海水をくみあげているのかもしれない」施設で働く人はそう考え、その切れている部分を探す調査をジャムステックとともに何回も行いました。そして今回、ついにその管がおし流されて全然ちがう場所にあるのを発見したのです。