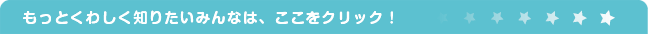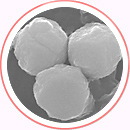
2010年11月8日発表
海底の微生物 の生き方、新発見!
仲間の体をリサイクルする!

図1:きびしい環境に生きるアーキア
様々な生命が息づく地球。その表面積70%をおおう海の下の
そこで研究者は、アーキアの体のなぞを解き明かそうと、アーキアを育てる
海底は日光もとどかず栄養分のとぼしいところ。リサイクルをすれば、エネルギーを節約できます。きびしい環境で生きていくために、アーキアはこのようなリサイクルして生きる方法を進化させたと考えられます。
研究者は今後も研究を続けて、アーキアの生きるスピードなども明らかにする予定です。「この研究を


アーキアのサイズは、1-10μmで、目には見えません。世界中の平均でいうと、海底の泥を1mももぐると、そこに生きる微生物の87%はアーキアです。海底から熱水をふき出す

図2:きびしい環境に生きるアーキア
そんなきびしい環境にも

図3:アーキアの細胞
海底の泥の中のアーキアの量は10億トンにも上ると考えられ、生き物の中でも最大の割合をしめるといえます。けれども、アーキアが海底の泥の中でどうやって生きているのかは、実はまだよくわかっていません。そこで研究者は、アーキアのなぞを解き明かそうと研究を始めました。



図4:開発した装置
まず研究者は、世界で初めて海底下でアーキアを育てる装置を開発しました。その装置は、高さ30cmの
無人探査機ハイパードルフィンを使って、装置を相模湾の水深1453mの海底に設置し、装置の中にグルコースをまいてアーキアを育てました(図5)。

図5:実験方法
どうしてグルコースをまくかというと、グルコースはアーキアの“エサ”なのです。もし、アーキアがグルコースを食べて体の一部にすれば、グルコースには印が付いているので、グルコースでつくった体の部分には印がのこります。反対にグルコースを食べなければ、体に印はのこりません。グルコースの印が、どこにどれだけあるのかを調べれば、海底下のアーキアの生き方がわかる、ということなのです。
装置を海底に設置してから数日〜405日後、研究者は泥のつまった筒を1本ずつ取り出しました。


研究者は、アーキアの細胞膜の成分であるグリセロールとイソプレノイドを装置の泥から取り出しました。そして、それぞれの成分に、グルコースの印がのこされているか確認しました。
その結果、グリセロールにはたくさんの印がありましたが、イソプレノイドにはありませんでした(図6)。グルコースは、グリセロールを作るためには使われたのですが、イソプレノイドを作るためには使われなかったのです。

図6:結果
では、どうやってイソプレノイドは作られるのでしょう。さらにくわしく

図7:リサイクルするしくみ
リサイクルをすればエネルギーを節約して、
また、これまで、アーキアの生きるスピードは非常にゆっくりだと考えられてきました。けれども今回の発見によって、実は活発に生きている可能性が示されたのです。


研究者は、イソプレノイドをさらにくわしく調べて、アーキアの成長のスピードなどを明らかにしようと思っています。今回の発見によって、地球全体の炭素循環の理解が進むでしょう。また、有害物質を分解する成分の開発への応用などが期待されます。
一方、もう1つの大きな「
解説:炭素循環
炭素は、人間のからだをつくったり、エネルギーとなったりするなど、生命にとって重要な役わりを果たしています。一方で、地球温暖化の原因でもあります。その炭素は、地球上の大気、水、陸上、生物の間でたえず交換されてめぐるので、炭素がどこで、どのように、どれくらい循環しているかを知ることは重要です。