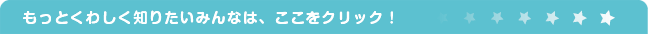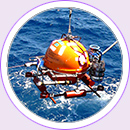
2012年5月7日発表
超低周波地震 を観測した!
海溝 近くも震源 に
大陸プレートの下に海洋プレートが
けれどこのたび、その海溝近くのプレート境界でも「

写真1:広帯域海底地震計を船からおろす様子


まず、地震の発生メカニズムからお話ししましょう。
紀伊半島から四国沖の海底には、大陸プレートの下に海洋プレートが沈みはじめる海溝、南海トラフがあります(図1)

図1:南海トラフ
沈みこむスピードは年間数センチですが、大陸プレートは沈みこむ海洋プレートにぴったりくっついて引き込まれゆがみ、ひずみが生まれます(図2)。そのひずみが

図2:地震の発生メカニズム
けれどこれまで、プレート境界すべてが地震を発生させるわけではないとされていました。地震が発生しないとされていたのは、海溝近く、海洋プレートの沈み始めの浅いところ(図3)。いったいなぜ? 海洋プレートの沈み始めには、

図3:地震が発生する深さと、しないとされていた深さ
ところがまれに、時間の長いゆっくり地震「超低周波地震」が、陸上より観測されていました。


地震が発生すると、地震波が地下や水中を伝わってゆれが広がります(図4)。地震波には様々な周波数があり、ふつうの地震よりも低く約10秒のタイプを超低周波地震と呼びます。超低周波地震は、地震の

図4:広がる地震波
けれど、超低周波地震の震源や発生メカニズムはよくわかっていませんでした。そこで杉岡博士たちは2008年、東南海地震の震源域である

図5:観測点


広域帯海底地震計は、2009年3月22日から10日間ほど、超低周波地震を間近で観測することに成功しました! 南海トラフ近くでの超低周波地震の発生は実に4年半ぶり。陸上からでは観測できないくわしいデータをとらえました。
地震の震源や発生メカニズムを

図6:海溝近くのプレートの境目で発生していた地震
地震の規模はマグニチュード4くらい。この規模の地震による

図7:長い時間がかかる超低周波地震
こうした超低周波地震は、断層の破壊が海溝まで達すれば広い


なぜ超低周波地震が海溝近くのプレート境界で発生していたのでしょうか。それを解明するため、杉岡博士は、「これからは、紀伊半島沖に設置している地震・

図8:DONETと「ちきゅう」によるデータも組み合わせ、地震の発生メカニズム解明を目指す!