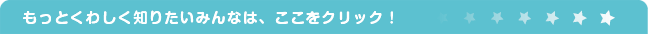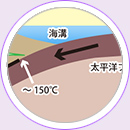
2012年8月20日発表
世界初!
東北地方太平洋沖地震 を引き起こした断層 を特定 !
2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震。
しかし海溝近くは、これまでは「断層の大きなすべりは起きない」とされてきたところ。いったいどの断層がどのように? それを


東北地方太平洋沖には、北米プレートと太平洋プレートの境目である日本海溝があります。ここでは、北米プレートの下にしずみこむ太平洋プレートにより、北米プレートが引きこまれ、ゆがみがためられています(図1)。そのゆがみが限界に達すると、北米プレートは元にもどろうとはね上がり、断層が一気にすべって地震と津波を引き起こします。

図1:地震発生のメカニズム
けれどこれまでは、プレートの境目でも海溝近く、つまり太平洋プレートのしずみ始めでは、断層の大きなすべりは起きないと考えられてきました(図2)。プレート同士のくっつきが弱いため、

図2:これまで、海溝近くは、断層の大きなすべりは起きないとされてきた
ところが2011年東北地方太平洋沖地震により、この考えがくつがえされました。日本海溝近くのプレートの境目で断層がすべり、北米プレートが約50m移動したほか、日本海溝の近くで大きな地殻変動があったのです。
どの断層がどのようにすべって、こうした地殻変動を? そこで小平 秀一 博士が、断層そのものの特定に


断層を特定するには、海底下の構造を調べなければなりません。その方法には、人工の
まず、深海調査研究船「かいれい」のエアガンから海底に向けて人工の地震波を発します。地震波は海と海底下を進みますが、海底や海底下の

図3:反射法地震探査のしくみ
調査は2011年3月と10月に行い(図4)、解析したデータを1999年のデータと比べました。

図4:調査海域


反射法地震探査システムにより、

図5:反射法地震探査で明らかになった海底下構造
1999年に行った調査のデータと比べたところ、太平洋プレートと北米プレートの境目をすべり面として、断層が日本海溝に達しているのを

図6:日本海溝近くの拡大図
北米プレートが50m動いたことにより、太平洋プレート上の
地震により変形した海底下の構造をとらえたのは、世界でも初めてです。

図7:いくつもの断層を作りながら海溝側へ


こうした断層は、日本海溝に