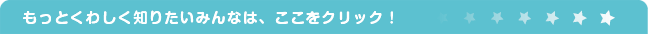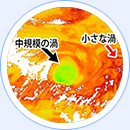
2014�N12��15�����\
�������Q�̓��������I
�C�̒����M���������^���������e�����I
�C�������ɂ���A1�`50�q�قǂ���r�I�������K���� �Q�₵���͗l�Ȃǂ��u�T�u���\�X�P�[������ �v�����т܂��B���̂��сA���̃T�u���\�X�P�[�����ۂ��A�C�̒����M���������^�������ɑ傫���e�����^���邱�Ƃ��킩��܂����B
���������ǂ��������ƁH�@���X���p�����m���ŐV�������Љ����܂��I

�C�̒��ɂ͑召���܂��܂ȉQ�₵�ܖ͗l�Ȃǂ̗��ꂪ����܂��B���̂����A100�`300�q�̗�������K���̌��ۂɂ�����A�u���\�i���ԁj�X�P�[���i�K���j���ہv������܂��i�}1�j�B���\�X�P�[���̑傫�����Q�͊C�m�����C������C�����Q�ŁA�M��v�����N�g���A�h�{���Ƃ����������𐢊E���̊C�։^���d�v�����������Ă��܂��B
���̃��\�X�P�[���̑傫�����Q�������ɂԂ���ƁA1�`50�q�قǂ̏����ȉQ�₵�ܖ͗l���ł��܂��B���̗�����u�T�u���\�X�P�[�����ہv�����т܂��B

�}1 �T�u���\�X�P�[����\�X�P�[���̗���
����܂ł̌�������T�u���\�X�P�[�����ۂ́A�~�ɑ����Ăɏ��Ȃ��G���ϓ���������Ă��܂��B���R�́A�~�ƉĂŊC�����\��������邽�߂ł��B
�~�A��������C�╗�͊C���\�w�����₵�܂��i�}2�j�B���₳�ꂽ�C���͏d���������݂܂��B����ƊC���������A���w�̊C������֍s���܂��B�����������������ɗ��ꂪ�ł��āA�C���������܂����܂��B�����w���u �����w�v�����сA�[���͓~�ɐ��S���[�g���ɂ��B���܂��B���̐[�������w�̒��͂ƂĂ��s�����ŏ����ȉQ�₵�ܖ͗l���ł��₷���A�T�u���\�X�P�[�����ۂ������ɂȂ�̂ł��B

�}2 �~�̃T�u���\�X�P�[�����ۂ̃��J�j�Y��
���ɉẮA�C�̕\�ʂ͑��z�����g�߂��܂��i�}3�j�B�g�����C���͌y�������\�w�ɁA�������C���͏d���������w�ɁA���ꂼ��Ƃǂ܂�₷���Ȃ�܂��B����������ƍ����w�������Ȃ�܂��B�������������w�̓����́C�~�����ׂ�ƈ��肵�Ă����ω����N���ɂ����C�T�u���\�X�P�[�����ۂ������ł͂Ȃ��Ȃ�̂ł��B

�}3 �ẴT�u���\�X�P�[�����ۂ̃��J�j�Y��
�����ō��X�ؔ��m���l�����̂��A�u�T�u���\�X�P�[�����ۂ��~�Ɋ����ɂȂ�Ȃ�A���̎����̓��\�X�P�[�����ۂɂ��e�����^���A����ɂ��M���������^�������ɂ��e��������ڂ��̂ł́v�A�Ƃ����\���ł��B����ɁA�u�����ł��グ����l�H�q������A�T�u���\�X�P�[�����ۂ����x�����ϑ��ł���̂ł͂Ȃ����v�ƍl�����̂ł��B
���X�ؔ��m���A���������݂܂����B

�����v��̑�܂��ȗ���́A�T�u���\�X�P�[�����ۂɂ��āA1�D�G���ɂ�芈���x���ǂ������̂��A2�D���傫�����\�X�P�[�����ۂƂ͂ǂ���W�Ȃ̂��A3�D�����ł��グ����l�H�q�������x�����ϑ��ł��邩�A�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃł��B
�v��1�D�ɂ��č��X�ؔ��m�́A�T�u���\�X�P�[�����烁�\�X�P�[���A�������K���Ȍ��ۂ����Č�����V�~�����[�V���������݂܂����B����܂ł̓R���s���[�^�̌v�Z�\���������ɂ��A�����m�S�̂ŁA�召���܂��܂Ȍ��ۂ����������x�ł̓V�~�����[�V�����ł��Ȃ������̂ł��B
����́A�V�~�����[�V�������͈����L���k�����m�Ƃ��A���������Ԃ�2001�N1���`2002�N12���ƒ�߂܂����B�����āA���l�������ɂ���X�[�p�[�R���s���[�^�u�n���V�~�����[�^�v�ŁA�v���O�����uOFES�v�𑖂点�܂����BOFES�Ƃ́A�R���s���[�^�ɊC��p�̌v�Z���������菇���̂悤�Ȃ��́B�n�����ׂ���3�q���̃u���b�N�ɕ��������x���グ�A���₭�v�Z���܂��i�}4�j�B

�}4 OFES���g�����V�~�����[�V����
���������A2001�N1���`2002�N12���܂ŁA�����ȉQ�₵�ܖ͗l���������܂ŁA�K���̂��������ۂ��ɃV�~�����[�V�����ł��܂����i�����j�B �Ԃ����v����A�������v����̗���ŁA�g�������v����̉Q�͊C�ʂ����肠����A�����������v������Q�͊C�ʂ��ւ���ł��܂��B�E������t�B�ׂ����Q�₵�ܖ͗l���A�~�͑����Ă͏��Ȃ��Ȃ��G���ω��������܂��B
����
�G�߂��Ƃ̉摜���A�}5�ł��B
�C�̕\�ʁi�}5���j������ƁA�Ă����~�̕����A�ׂ����Q�₵�ܖ͗l�����������܂��B
�C�̒��͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B���o 155�x�Ő��ĉ����猩�܂����i�}5�E�j�B�ΐ����A�����w�� ���ł��B�Ԃ��قǏ�����ɋ�������A���قlj������ɋ��������\���܂��B
�~�́A�����w�̐[���͐��Sm�ɂ��B���Ă��܂����B���������̗���i�ƐԂ̕����j�́A�Ă�葽���A�����w����������悤�Ɋ����ɗ���Ă��܂����B
�ẮA�����w�̐[���͐��\m�B���������̗���i�ƐԂ̕����j�́A�~�����ׂ�Ə��Ȃ��A�����w�͂قƂ���������炸�����ł͂���܂���B

�}5 �G�߂��ƂɌ����C�̕\�ʁi���j�ƊC�̒��i�E�j�̗���
�T�u���\�X�P�[�����ۂ��ǂ̂��炢�������m�邽�߁A����̉�]�̋����ƍ����w�̐[�����G���ω��ׂ܂����B���������A�����w���[���Ȃ�Ɨ���̉�]�������Ȃ�A�����w�������Ȃ�Ɖ�]���キ�Ȃ��X�����m�F�ł��܂����i�}6�j�B
![�}6 ����̉�]�̋����ƍ����w�̐[��(���v���ʁj](img/fig6.jpg)
�}6 ����̉�]�̋����ƍ����w�̐[���i���v���ʁj
�ł́A�v��2�D�́A �T�u���\�X�P�[�����ۂƃ��\�X�P�[�����ۂ͂ǂ��W���Ă���̂��B����������i�}7�j�A���a��25�q�����̂��������ȉQ�₵�ܖ͗l�Ȃǂ͑傫���K���̗���ƂԂ���ƁA�����܂�����邱�Ƃ��킩��܂����B
���ɁA25�q�ȏ��̉Q�₵�ܖ͗l�́A���\�X�P�[�����ۂ��Q�ȂǂƂԂ���ƁA��肱�܂ꍇ�̂��A����ɑ傫�������ɂ����Ă��܂����B�����X���͓~���I����Ă������������Ă��܂����B

�}7 �C�ʂ̉Q�̕ω�
�܂Ƃ߂�Ɓi�}8�j�A�����̋߂��ɂ����ăT�u���\�X�P�[�����ۂ́A�����w�̐[���~�Ɋ����ɂȂ�܂����A�~���I��荬���w�������Ȃ�ɂ����X�����₩�ɂȂ�܂��B���̎��ɂ́A���悻25�q�ȏ��̂�������̉Q�₵�ܖ͗l�Ɍ����闬��̃T�u���\�X�P�[�����ۂ��A�߂��̂��̂��ꏏ�ɂȂ��đ傫�������Q�◬��̃��\�X�P�[�����ۂɂȂ��Ă����̂ł��B�������ď����ȃT�u���\�X�P�[�����ۂ��傫�ȃ��\�X�P�[�����ۂ�����邱�ƂŁA�C�̒����M���������ȒP�ɉ^�Ԃ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B

�}8 �܂Ƃ�
�����āA�v��3�������ł��グ����l�H�q�����A�T�u���\�X�P�[�����ۂ��ϑ��ł���̂��B���X�ؔ��m�̓V�~�����[�V�����Ōv�Z���ꂽ�C�ʂ̂ł��ڂ��f�[�^�i�C�ʍ��x�j�������߂������ƁA�V�~�����[�V�����������o�͂��ꂽ���������ׂ܂����i�}9�j�B�C�ʂɂ͍�����������������������A�����X�����痬�������߂���̂ł��B
�C�ʂ̂ł��ڂ��������߂����́i�Ԑ��j�́A�V�~�����[�V�������������o�Ă������́i�����j�Ƃ悭��v���Ă��܂��B
![�}9�@�V�~�����[�V�����̊C�ʂ̂ł��ڂ����狁�߂�����̉�]�̑傫���ƁA�V�~�����[�V�������璼�ڂłĂ����o�͂��r�@�i�����F�C�ʂ̗���̉�]�C�����ƐԐ��F����>>����̉�]�C�E���BOX���F����̉�]�̑傫���̕ω��́C�C�ʍ��x���狁�߂�����ōČ��ł���j](img/fig9.jpg)
�}9 �V�~�����[�V�����̊C�ʂ̂ł��ڂ����狁�߂�����̉�]�̑傫���ƁA�V�~�����[�V�������璼�ڂłĂ����o�͂��r�i�}6�ɒlj��������́j�B
���̌��ʂ́A�l�H�q���ŊC�ʂ̂ł��ڂ����������x������A�T�u���\�X�P�[�����ۂׂ��邱�Ƃ��Ӗ����܂��B���N��ɑł��グ���鍂���Z�p���������l�H�q���̊ϑ��ŁA�T�u���\�X�P�[�����ۂ����A�ǂ��ŁA�ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��邩���x�悭�킩��Ɗ��҂���܂��i�}10�j�B

�}10 �C�ʂ̂ł��ڂ��f�[�^����A�������Z�o�I

���̌����ɂ��A�k�����m�̍����߂��ɂ����ăT�u���\�X�P�[�����ۂ́A�C�̒��̔M�╨���� �z���ɑ傫�ȉe����^���邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B�����́A�l�H�q���ɂ��ϑ�����A�n���S�̂̔M�╨���̏z���ǂ��ς���Ă����̂��A�������Ԃɂ킽�薾�炩�ɂ��Ă������Ƃ����҂���܂��B
���X�ؔ��m�́A�u����́A�V���ȋZ�p���g���āA�n���̊C�S�̂�����ɒ������ԂŃV�~�����[�V�����������B�����Ăł����f�[�^�����ƂɁA������l�����ł͂ł��Ȃ����Ƃ��A���ɐ��E���̊C���ϑ����Ă���l�Ƌ��͂��Ď��g��ł��������v�Ƙb���܂��B