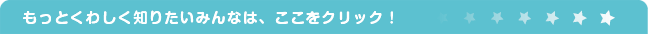2015年2月24日発表
超深海に、独自の生物集団を発見!
世界で最も深いマリアナ海溝の超深海層で、独自の生物集団がいることが発見されました。
そもそも、水深1万メートルにも達する超深海層に、いったいどんな生き物がいるのでしょうか。そして、どんな独自の生物集団を形成しているのでしょうか。 今回は、 地球の活動を支えに命を紡ぐ「微生物」の研究をご紹介します。

- 超深海層と呼ばれる水深6,000メートルより深い海に独自の微生物集団がいた。
- 独自の微生物集団は、地すべりによって飛び散る、海底にたまっていた微生物の死がいなどの有機物を食べて生きていると考えられる。
この研究論文を発表したのはジャムステック海洋生命理工学研究開発センターの微生物学者である布浦 拓郎 博士です(写真1)。

写真1 布浦博士
小学生のころは自宅で水槽に魚を飼うなど、生物や植物が身近な環境で育ちました。自然に興味の矛先は生物学へ向き、大学は生物を研究したいと農学部へ進学。そして研究テーマは微生物を選びました。理由は「生命の起源を知りたいと思ったから」。地球上のあらゆる生物に共通する遺伝情報から、生命の起源は約40億年前に海で誕生した微生物だと考えられているためです。
現在はジャムステックで働き、時に有人潜水調査船「しんかい6500」に乗り込んで実際に深海へ行き(写真2)、さまざまな地球の活動と微生物がどう関わっているのか、研究に励んでいます。

写真2 「しんかい6500」に乗り込む布浦博士

さて、今回、布浦博士らが 調査したマリアナ海溝チャレンジャー海淵(図1)は、地球上でいちばん深い海底です。太平洋プレートがフィリピン海プレートの下に 沈み始める場所で、太平洋側の水深4,000〜6,000mの海底が、さらに5,000m以上も深く切り込む谷になっています。水深6,000メートルを 超える海を、「超深海層」と呼びます。

図1マリアナ海溝
水深1万メートルにも達する海底には、太陽光も届かない暗黒が広がります(図2)。水温は約2℃、水圧は約1,000気圧。陸上にくらべて1,000倍もの圧力がのしかかります。人間から見れば、生物が生きるには過酷な環境です。

図2 マリアナ海溝を横から切って見たイメージ

これまでの無人探査機「かいこう」を使った調査から、マリアナ海溝にはたくさんの「カイコウオオソコエビ」(ヨコエビのなかま、写真3)がすんでいることや、海底にたまった泥(写真4)の中にたくさんの小さな生物(有孔虫)がいることが報告されています。

写真3 カイコウオオソコエビ

写真4 「かいこう」で海底にたまった泥をとる様子
そんな中で布浦博士が疑問に思ったのが、「同じ場所でも、深さにより微生物の 集団は変わるのだろうか」、「微生物は、海の深さにどう 適応しているのだろうか」といった点です。マリアナ海溝の底の生物もよくわかっていませんが、上から下まで、どんな微生物がいるのかも連続して知りたいと考えたのです。そこで布浦博士が、研究に 挑みました。

2008年、布浦博士は大深度小型無人探査機「ABISMO」を使って、マリアナ海溝の海面から海底直上(水深10,257m)まで50〜1,000mおきに海水を採取しました(図3)。

図3 最大で水深11,000mまで潜る「ABISMO」
とった海水は、 すぐ船上の冷凍庫で保存。ジャムステックの実験室に持ち帰ってから、分析しました(写真5 ,6)。主な分析項目は、塩分、化学成分、微生物の数や分類などです。

写真5 顕微鏡をのぞいて微生物を観察

写真6 DNAの配列を調べる装置「DNAシーケンサー」。平井 美穂 技術スタッフが分析しました。
海水の化学成分と微生物の数を分析したところ、深海層(水深4,000〜6,000m)と超深海層(水深6,000m以深)では、はっきりとしたちがいはありませんでした。
ところが、微生物の 遺伝子を調べた結果、深海層と超深海層の水の中では、明らかに異なる微生物の集団がすんでいることがわかりました。

そもそも生物は、「身体をつくる有機物を自ら“つくる”生物」と「有機物を“食べて”自分の身体をつくる生物」に分けられます。
例えば、植物は、太陽光のエネルギーを利用して「有機物を“つくる”生物」です。そしてその植物を草食動物が食べ、その草食動物を肉食動物が食べます。ヒトは、他の生物がつくった「有機物を“食べて”自分の身体をつくる生物」です。
海に話を戻すと、光の届かない深海では、プランクトンの 死がいや排泄物などの「有機物を“食べて”自分の身体をつくる生物」と 化学物質のエネルギーを利用して自ら「有機物を“つくる”生物」に分かれます(図4)。

図4 「有機物を“つくる”生物」と「有機物を“食べる”生物」
今回の分析では、水深200〜6,000メートルの中深層〜深海層では、自ら「有機物を“つくる”微生物」が多くすんでいました(図5)。
しかし、水深6,000〜10,000メートルの超深海層では大きく変化します。超深海層で 大きな割合を占めたのは、「有機物を“食べる”微生物」でした(図5)。

図5 それぞれの深さにいる微生物

同じ深い海でも、深さによって微生物の集団が異なるのは、なぜでしょうか。どんな微生物がいるのかは、食べ物となる有機物と深く関係します。超深海層に 特有の有機物が供給されているのかもしれません。
そこで、布浦博士は微生物たちが何を食べているのかを調べました。 特に亜硝酸菌と硝酸菌に注目しました。亜硝酸菌は有機物が分解されてできるアンモニアを食べて亜硝酸をつくり、硝酸菌はその亜硝酸を食べる微生物です(図6)。

図6 有機物と亜硝酸菌と硝酸菌の関係
亜硝酸菌と硝酸菌について分析を進めたところ、超深海層で、濃いアンモニアが好きな亜硝酸菌グループと、濃い亜硝酸が好きな硝酸菌グループを見つけました。どちらの微生物も、超深海層よりも浅い海中ではそんなに多くはいませんでした。
そこで、濃いアンモニアや亜硝酸が好きな微生物のグループがいる⇒そこにはアンモニアと亜硝酸がたくさんある⇒アンモニアと亜硝酸の源である有機物がたくさん分解されている、と考えました(図7)。

図7 濃いアンモニアや濃い亜硝酸が好きなグループがいるということは…

では、その有機物はどこから来たのでしょうか。地図でマリアナ海溝の北側を見ると、 日本海溝や伊豆・小笠原海溝があります。本州の東北沖は豊かな海で、プランクトンもたくさん育ちます。このプランクトンの死骸などが日本海溝に沈むと、海溝の中を伝って小笠原海溝までは有機物が豊かな水が流れてくる可能性があります。
しかし、これらの海溝とマリアナ海溝は、現在はつながっていないので、プランクトンの死がいや排泄物などの有機物が流れ込んでくる可能性は低いと言えます(図8)。

図8 深海の有機物はどこからきたのか。
考えられるのは、超深海層だけで、 独自に存在する有機物。
さらに、マリアナ海溝の海底から 掘り出した堆積物には、しましまの構造があり、過去に地すべりがくり返し起きていたことが示されていました。
こうした 証拠をもとに布浦博士は、「深海斜面に埋もれていた有機物が、地震による地すべりなどで飛び散って、超深海層の微生物たちが食べている可能性がある」と、この論文で 結論づけました(図9)。
2012年に発表された東日本大震災に伴って起きた深海底の地すべりが深海の海水中の微生物に与える影響の研究は、今回発見した微生物の変化と似ていて、このことも今回の仮説を裏付けるものとなっています。

図9 地すべりにより飛び散る有機物
今回の研究により、マリアナ海溝の超深海層には独自の微生物集団がいる可能性が高まりました。布浦博士は、「限りある少ない海水の 試料から、これだけの分析を行うのは大変だった。ただし、 直接的な証明はまだできていない。 今後さらに研究を続け、有機物と微生物の関係を確かめていきたい」と話します。
地球の活動を支えに命を紡ぐ、超深海層の微生物たち。こうした研究を続けていくことで、生命の 起源の答えに少しずつ近づくと期待されます。