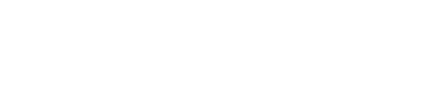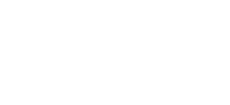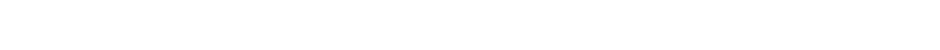- 2007年3月1日~3月27日
- 南西諸島にて試験・訓練潜航
- 2007年3月15日
- 南西諸島にて通算1000回潜航達成
作家の山根一眞氏が乗船 - 2007年4月4日~4月10日
- 相模湾調査
- 2007年5月31日~6月28日
- 伊豆小笠原調査にて試験潜航
- 2007年9月7日~9月18日
- 日本海溝、伊豆小笠原調査にて試験潜航
- 2007年9月25日~10月8日
- 千島海溝、釧路沖調査
- 2007年10月11日~10月27日
- 北西太平洋、三陸沖調査
2007年3月に「しんかい6500」は通算1000回目の潜航を迎えた。
建造から18年、およそ年に60回前後の潜航を実施しているなか大きな事故もなく極限環境へ挑み続けることができたことに、関係者一同は静かな喜びをかみしめた。
例年4月から11月までは調査潜航、12月から3月までは整備と調整を行っている。この1000回目は整備後の調整時期にあたることとなった。ちょうどこの頃、潜水船の利用が科学分野に限定されていることに対する意見もあったことから、1000回目の潜航者として作家の山根一眞氏を招いた。氏は深海研究に囚われない多様な試みを用意されたが、ここでは「深海の音」の収録を特記したい。海中では「音」を電波の代わりに利用するが、人間が聞こえる形での録音はこれまで「科学的には」価値が低かった。実際に熱水噴出孔のそばにICレコーダーを置いたところ「シュー、ココココ」といった周期的な音を聞くことができた。これらはテレビ等メディアでも紹介された。人々のイマジネーションに寄与できたのではないだろうか。
またこの年には、これまで潜在していた潜水船にとって重要な事象も明らかとなった。
乗員が乗り込む部屋は頑丈な殻となっているが、出入りのために天井部を切欠いて蓋が取り付けられている。この蓋(ハッチと呼ばれる)は潜航中には固く閉鎖されており、動くことはないと思われていた。しかし実は深度圧がかかると動く、ということが発見されたのである。これまでにも関係部品の修理頻度が高いことなどは把握されていたが、この事象が顕在化したのがこの年であった。これは設計者も未知のできごとであった。乗員の安全に関わることゆえ計画されていた深海調査をただちに中止し、事象を把握するための努力が始まった。実際の潜航を含む種々の実験を実施し、データの解析とシミュレーションの結果、深度圧が大きくなると殻が縮むので嵌め込まれたハッチは押し出されるように動く、深度圧が小さくなると殻は拡がりハッチは元の位置に戻る、ということが分かった。これら事象の把握と安全の確認に約3か月を要した。

2007年の運航チーム
>> 年表に戻る