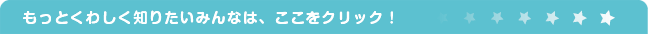2009年4月13日発表
インド洋の研究をさらに前進させる「新しい通信方法」の実験に成功!
海の様子をずっと観測し、そのデータを研究者に届ける


海にうかぶトライトンブイが観測するのは、風、気温、

写真:トライトンブイ

図1:トライトンブイ設置図
(今回の実験に使ったブイは18番)
このダイポールモード現象とは、ふだんより冷たい海水がインドの東側に現われ、アジアの気象をふだんとはちがうものに変えてしまう現象です。数年に一度、北半球の夏から秋に見られます。
インド洋の東側では、夏から秋にかけて東から西に向かって風が

図2:ふだんのインド洋
ところが何らかの理由でこの東風がとても強くなると、海面のあたたかい海水はたくさん西側に運ばれます(図3)。するとこの分をたすように下から冷たい海水がたくさんわき上がります。結果、インド洋の東側はいつもよりとても冷たい海水、西側はとてもあたたかい海水が広がり、ダイポールモード現象が起きます。

図3:ダイポールモード現象が発生している時のインド洋
(赤丸と青丸が、図2とは逆に位置している)

図4:ダイポールモード現象の影響
海の状態は気象と強く関係します。ダイポールモード現象がおきると、インド洋の西側のあたたかい海の上では、海水がたくさん
世界の気象を調べるためには、インド洋の様子を詳しく調べるトライトンブイの観測が欠かせません。


トライトンブイによるインド洋の観測は1998年から行われています。すでにお話したように、データは人工衛星を使って研究者に届けられますが、今までのシステムでは次のような弱点がありました。
(1)トライトンブイからはリアルタイムではデータを少ししか届けられないため、たくさん観測しても研究者が見れるのは平均
(2)くわしい観測データを見られるのはトライトンブイがこうかんされて日本にもどってくる1年に1度だけ。
そこで、技術者はもっとたくさんの観測データをすぐに研究者に届けられるシステムの開発に


海の現象の原因やしくみを、これからはさらに早くくわしく研究します。将来は、台風などをより正確に予測し、災害をできる限り少なくしたり、災害に負けない社会をつくることにつなげていきます。また、たくさんデータを送れるようになったので、化学や生物など他の研究もできるようになります。さらに、今までインド洋のトライトンブイは2つでしたが、今年は新しく1つ追加する予定です。トライトンブイからたくさんのデータを届けるだけではなくトライトンブイそのものを増やし、さらにこまかくインド洋を観測し、気象のうつり変わりを研究していきます。
技術者のお話
はるか洋上で観測しているトライトンブイを管理するのは大変な事なので、色々な方々の協力が必要です。特に日本の漁船の方々の協力は重要で、トライトンブイにトラブルが起きた時は近くの方にお願いして見に行ってもらったりしています。
しかし一方で、トライトンブイは“いたずら”により、機械をこわされたり、ワイヤーを切られたりする事があります。これらはほとんどが外国の漁船によるものです。トライトンブイのまわりはマグロなどの魚がたくさん集まってくるので、この魚をとろうとした外国漁船などがついでにいたずらをしていくようです。
いたずらによって、せっかくのデータが消えることも少なくありません。けれどもこれからは、データはすぐに研究者に届けられるので、いたずらによってトライトンブイからデータが消えたとしても以前ほどの影響はありません。