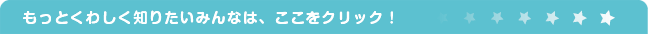2009年11月20日発表
北極海に異変 !
貝ガラをもつ生き物にとって、くらしにくい海になっちゃった!
海に住む貝のカラは、何からできているのでしょう?答えは、


炭酸イオンとカルシウムイオンは、海の生き物にとってとても大切です。これらの成分が作る炭酸カルシウムが生き物をささえるからです。たとえば炭酸カルシウムでできたカラは、動き回ることが苦手な貝にとって
そんな大切な炭酸カルシウムを作る炭酸イオンとカルシウムイオンですが、近年「北極海では少なくなっているかもしれない」との声が聞こえるようになりました。炭酸イオンとカルシウムイオンが少ないと、炭酸カルシウムが海にとけやすくなってしまいます。炭酸カルシウムがとけると、カラなどをもつ生き物は生きていけません。影響は



図1:1997年と2008年の炭酸カルシウムのとけやすさ
2008年、研究者は研究船にのって北極海を
さらにくわしく研究を進めたところ、この原因は「海の酸性化が進んだこと」と「海氷がとけたこと」の2つが重なったためだとわかりました。


(1)北極海で炭酸カルシウムがとけやすくなった理由の1つ目は、海の酸性化が進んだためです。海の酸性化とは、ふつうは弱いアルカリ性の海が酸性に近づくことです。海の酸性化の

図2:海と空気の間を出入りする二酸化炭素
二酸化炭素は海と空気の間でたえず出入りしていて、中でも人間が出す量のおよそ3分の1は海に取りこまれます(図2)。
二酸化炭素は水にとけると酸性になるので、海の二酸化炭素が増えると海は酸性に近づきます。すると、酸性化をやわらげよう(

図3:酸性化・二酸化炭素・炭酸イオンの関係。これらは、炭酸カルシウムのとけやすさに大きな影響を与えます。
今回の研究では、北極海では空気中の二酸化炭素が増えたことにともなって海の二酸化炭素も増えて、酸性化が進み炭酸カルシウムがとけやすくなったことが明らかになりました(図4)。

図4:北極海の炭酸カルシウムがとけやすくなった理由(1)
(2)炭酸カルシウムがとけやすくなった理由の2つ目は、温暖化によって海氷のとける量が増えたためです。海氷がとけると、これまで海水面をおおっていた海氷のふたが減ることになります(図5(a))。すると空気にふれる海水面が増えて、空気中の二酸化炭素が海に取りこまれやすくなります。結果、海の酸性化が進み、これをやわらげようとしてまた炭酸イオンが消費されたのです。さらに、

図5:北極海の炭酸カルシウムがとけやすくなった理由(2)


炭酸カルシウムがとけやすくなって貝やプランクトンが減ると、これをエサとしてきた魚などの食べ物も減ってしまいます。1つの種の生き物がいなくなると、他の生き物をもほろぼし、さらに他の生き物へと影響を広げるかもしれません。生き物への影響を調べるために、研究者はこれからも観測を続けます。また一方で、生き物にどんな影響がでるのかを予測するために、実験室で実験をします。研究者は地球を守るために、北極海の変化とそれによる影響を明らかにしていきます。