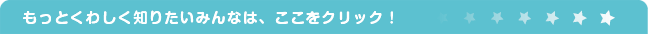2014年10月14日発表
ゴエモンコシオリエビは、毛の細菌を食べて栄養分をもらう!
世界で初めて実験で実証!
もじゃもじゃ毛むくじゃらのこの生き物の名は、「ゴエモンコシオリエビ」です(写真1)。

写真1 ゴエモンコシオリエビ
これまで、ゴエモンコシオリエビが体のどこかにいる細菌から栄養分をもらっていることや、口もとにある手のような器官(顎脚)でおなかの毛をこそいで口に運ぶ行動が見られることから、おなかの毛にたくさんいる細菌を食べて栄養分をもらっていると考えられてきました。そして、このたび、毛にいる細菌がゴエモンコシオリエビに食べられる直接的な証拠が得られました。和辻 智郎博士の最新研究にせまります!

ゴエモンコシオリエビは、海底から熱水を噴き出す熱水噴出孔 にいる甲殻類 です。カニのような姿をしていて名前にはエビとありますが、ヤドカリの仲間です。頭には触覚があり、尾を腹側に折り曲げています。甲羅はなめらかで、腹側には毛がびっしり。この毛に、無数の細菌がいます(写真2)。

写真2 ゴエモンコシオリエビと毛の細菌
毛についた細菌とゴエモンコシオリエビの関係は、深海研究の大きななぞでした。というのも、毛についた細菌は熱水中の硫化水素やメタンといった成分を使って栄養分をつくり、その栄養分をゴエモンコシオリエビがもらっているのではないかという考えはあるものの(図1)、毛についた細菌が「何をして(機能)何のために存在するのか(役わり)」がハッキリとは確認できていなかったのです。

図1 ゴエモンコシオリエビと毛の細菌の関係
細菌の機能や役わりが確認できなかった理由は、熱水域の甲殻類を深海底から引き上げると死んでしまい、体についた細菌を甲殻類に食べさせるような実験ができなかったためです。
和辻博士はその死亡原因が潜水病と考え、潜水病を防ぐと考えられる捕獲法をあみだし(図2)、2010年に沖縄の水深1,000mの海底から、ゴエモンコシオリエビを生け捕りにすることに成功しました。

図2 ゴエモンコシオリエビを生け捕りにする方法
そして、生きたゴエモンコシオリエビを実験に用いた結果、ゴエモンコシオリエビが栄養分をもらうのは「硫黄酸化細菌」と「メタン酸化細菌」からで、毛の細菌はほとんどその2種であることを世界で初めて明らかにしました(図3)。硫黄酸化細菌とは硫化水素を使って栄養分をつくる細菌、メタン酸化細菌とはメタンを使って栄養分をつくる細菌です。

図3 ゴエモンコシオリエビの栄養源は、硫黄酸化細菌とメタン酸化細菌
この実験結果は、ゴエモンコシオリエビが毛についた硫黄酸化細菌とメタン酸化細菌から栄養分をもらっていることを「間接的に」示します。しかしながら、ゴエモンコシオリエビには腸があります。腸があれば腸の細菌(腸内細菌)が存在します。そのため、「もしかしたら、腸の細菌には硫黄酸化細菌とメタン酸化細菌も存在して、その腸の硫黄酸化細菌とメタン酸化細菌からゴエモンコシオリエビは栄養分をもらうのではないか」という可能性もあったのです。そこで和辻博士が、さらなる研究に挑(いど)みました。

研究の目的は、ゴエモンコシオリエビが栄養分をもらうのは腸の細菌ではなく毛の細菌であることを実験で示すこと。和辻博士は、大きく4つの実験を行いました。

ゴエモンコシオリエビを解剖して腸を顕微鏡で観察したところ、数本の毛が腸に入っていました(図4)。つまり、顎脚で毛をこそいで口に運ぶゴエモンコシオリエビの行動は 摂食行動であることがわかりました。また、毛を食べるのなら、毛についた細菌も同じように食べていると考えられました。

図4 腸の中を観察
毛の細菌を色素で染めたゴエモンコシオリエビを24時間水そうで飼育した後、ゴエモンコシオリエビの腸を観察したところ、色の付いた細菌が見つかりました(図5)。

図5 色を付けた細菌の行方を観察
色の付いた細菌が腸に取りこまれたことから、ゴエモンコシオリエビが毛の細菌を口から食べる事実が示されました。

口から細菌を食べるのなら、腸でそれが消化されるか。和辻博士は腸をすりつぶした液にゴエモンコシオリエビの毛をつけました。3日後、毛についていた細菌が減り、消化されたのです(図6)。

図6 食べたものを消化するか観察
続いて何が働き消化をしたのか知るため、消化酵素を調べました。消化酵素とは、食べたものを分解して生き物が吸収できるかたちの栄養分に変える働きをするものです。分析の結果、消化の基本となるアミラーゼ、リパーゼ、プロテアーゼの3種の活性が見つかりました(図7)。

図7 腸の中で発見した消化酵素
腸のすりつぶし液で細菌が消化され、また3種の消化酵素もあったことから、ゴエモンコシオリエビは毛の細菌を口から食べて消化する事実が示されました。
ここからは、さらにくわしい部分にせまりますよ!

すでにお話したように、ゴエモンコシオリエビが栄養分をもらう「硫黄酸化細菌」と「メタン酸化細菌」は腸にもいる可能性があります。硫黄酸化細菌とメタン酸化細菌はそれぞれ硫化水素とメタンを消費することができます。そこで和辻博士は、ゴエモンコシオリエビの毛と腸を、それぞれ硫化水素またはメタンをとかした人工海水に入れて、硫化水素またはメタンの濃度の変化をみました(図8)。もし濃度が低くなれば硫化水素またはメタンが使われた=そのビンには生きた硫黄酸化細菌とメタン酸化細菌がいるということ。反対に、濃度が変わらなければ硫化水素とメタンは使われず、そのビンにはゴエモンコシオリエビの栄養を支える細菌がいないことを意味します。

図8 硫化水素やメタンの濃度はどうなるか実験
実験の結果、硫黄酸化細菌とメタン酸化細菌がいることがわかっている毛を入れたビンでは硫化水素もメタンも濃度が低くなりましたが、腸を入れたビンの硫化水素とメタン濃度はほとんど変化なし(図9)。

図9 硫化水素とメタン濃度の変化
腸が入ったビンでは硫化水素もメタンも使われなかったことから、腸には活動的な硫黄酸化細菌とメタン酸化細菌がいない事実が示されました。つまり、ゴエモンコシオリエビが、腸にすむ細菌から栄養分をもらう可能性が、実験3で否定されました。また、実験結果は、食べられて腸に入った毛の硫黄酸化細菌とメタン酸化細菌も活動していないこと示すので、この実験からも食べられた毛の細菌は消化されると考えられました。

最後に、ゴエモンコシオリエビはの栄養源は、腸ではなく毛の細菌である事実を、しっかりと示さなければ!
ゴエモンコシオリエビは消化した毛の細菌を栄養源として吸収すると予想されます。硫黄酸化細菌は硫化水素を利用して二酸化炭素から糖分をつくる炭素固定ができるので、印を付けた二酸化炭素をゴエモンコシオリエビに与えて印付き炭素の行方を追えば、毛の細菌から栄養をもらっているかどうかを調べることができます。和辻博士は、毛、腸、筋肉、カット腸で印付き炭素がどのくらい取りこまれたかを比べました(図10)。カット腸は、解剖してとりだした腸で、栄養分が腸から筋肉へいく前の状態を知るためのものです。

図10 炭素の量を調べる実験
比べた結果、印付き炭素量が少ないのは硫黄酸化活性が見られなかった腸、多いのは硫黄酸化細菌がいる毛でした。また、筋肉にも印付き炭素が取りこまれたことは、ゴエモンコシオリエビは硫黄酸化細菌を栄養源にすることを示します。つまり、消化された毛の細菌はゴエモンコシオリエビに栄養源として吸収されたことがわかりました。そして、毛の印付き炭素量は、筋肉に吸収されたものの40倍以上! 毛の細菌がゴエモンコシオリエビの十分な栄養源となることがわかりました。。一方で、腸やカット腸の印付き炭素量は筋肉が吸収したものよりも少なく、ゴエモンコシオリエビの栄養を支えるには腸の細菌では足りないこともわかりました。

図11 印付き炭素の量を比較
組織間で印付き炭素量を比較することで、ゴエモンコシオリエビの栄養を支えることができる細菌は、毛の細菌だけであるという事実が示されました。

今回の研究により、ゴエモンコシオリエビは毛の細菌を口から食べて消化し、栄養分を吸収することが示されました。 ゴエモンコシオリエビのようにからだに細菌をつけた甲殻類は世界の深海熱水噴出孔で見付かっています。甲殻類とからだについたその細菌の関係についての議論は、熱水噴出孔が発見された1977年以降ずっと続いていましたが、今回の「体表の細菌は動物の栄養分(エサ)である」という結論によって決着がついたと言えます。
和辻博士は、「ゴエモンコシオリエビだけでは熱水噴出孔で生きていけない。でも細菌とともに生きることで、硫化水素とメタンがあれば生きていけるように進化した。その巧みに生き抜く術がおもしろい」と話します。
みなさん、この興味深いゴエモンコシオリエビは映像もあるので、ぜひ見てくださいね!
【参考映像】ゴエモンコシオリエビの食事風景