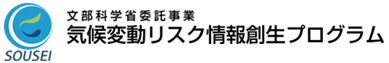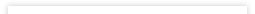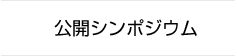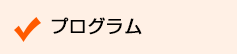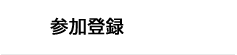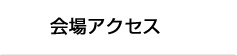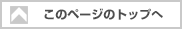プログラム
スピーカー名をクリックすると講演資料がご覧いただけます。
| 時間 | タイトル | スピーカー/所属、役職 |
|---|---|---|
| 13:30-13:35 | 開会挨拶 | 文部科学省 |
| 13:35-13:50 | 講演の全体説明・ハイライト | 住 明正 文部科学省技術参与 国立環境研究所 理事長 |
| 13:50-14:20 | 近年の気候変化を「仕分け」する -温暖化研究の新たな展開‐ |
渡部 雅浩 東京大学大気海洋研究所 准教授 |
| 14:20‐14:50 | 将来予測に向けて過去をよく理解するための技術 | 石井 正好 気象庁気象研究所 気候研究部 主任研究官 |
| 14:50-15:00 | 質疑応答(10分) | |
| 休憩(15分) | ||
| 15:15-15:45 | ダウンスケールデータの影響評価研究への適用について | 高薮 出 気象庁気象研究所 環境・応用気象研究部 第二研究室 室長 |
| 15:45‐16:15 | 温暖化に伴いスーパー台風はどこまで強くなるのか | 坪木 和久 名古屋大学 地球水循環研究センター 教授 |
| 16:15-16:25 | 質疑応答(10分) | |
| 16:25-16:35 | 講演の総括 | 木村富士男 文部科学省技術参与 海洋研究開発機構 地球環境変動領域 プログラムディレクター |
| 16:35-16:40 | 閉会挨拶 | 住 明正 文部科学省技術参与 国立環境研究所 理事長 |
講演要旨
「近年の気候変化を「仕分け」する-温暖化研究の新たな展開-」

渡部雅浩
東京大学大気海洋研究所
准教授
北極海氷の減少、より頻繁な豪雨の発生、梅雨明けの遅れ ― 地球温暖化によって生じると考えられる気候の変化について、これまで多くの研究が明らかにしてきました。これらは、今世紀後半までにそのような傾向になってゆく、という意味の変化であり、特定の年に起こるようなものではありません。一方で、気候変化の兆しは既に現れているため、例えば去年夏の九州豪雨がどこまで温暖化のせいなのか、といった個別の現象に対する疑問を明らかにすることが重要になってきています。このように、過去の特定の異常気象などの要因を「仕分け」することを、イベント・アトリビューションと呼び、最近では国内外で活発に研究がすすめられています。本講演では、気候変動リスク情報創生プログラムにおいて取り組んでいるイベント・アトリビューションの例をご紹介するとともに、結果の活用方法や温暖化予測研究に対する意義についてもお話しします。
折しも、今年は記録的な猛暑になりました。この夏の異常気象の要因についても少し触れたいと思います。
「将来予測に向けて過去をよく理解するための技術」

石井正好
気象庁気象研究所
気候研究部 第四研究室 主任研究官
地球温暖化予測の基盤となる予測システム開発は、気候変動リスク情報創生プログラムにおける大きな研究テーマの一つです。過去の長期的な気候変化を科学的に理解することなしに将来の予測はありえませんので、システム開発の過程では、過去の気候変動事例を観測データを用いて気候モデルの中に再現し、答えの分かっている過去事例について予測を成功させた実績を積み上げていきます。こういった数値実験を可能にする技術的背景について解説します。歴史的な観測データに含まれる問題を解決するに至った経緯や、システムにおいて核心的なデータ同化技術の現状、そして関連する国際的動向なども紹介します。
ダウンスケールデータの影響評価研究への適用について

高薮 出
気象庁気象研究所
環境・応用気象研究部 第二研究室 室長
モデルによる温暖化予測の結果を地域ごとの影響評価に役立てようとする際に知りたいのは各地域に温暖化の影響がどのように出てくるのかということです。このために、ちょうど虫眼鏡で覗くように詳しい気候情報を取りだすためにダウンスケール研究があります。本プロジェクトでは、解像度のより細かなモデルを埋め込んで計算を行う力学的ダウンスケール手法を用いて気候変化の様子をダウンスケールしています。この結果を用いることで、日本のような山勝ちの地域であってもその地域ごとに細かな気候変化をしめすことが出来ます。本発表ではその2、3の例を紹介して温暖化対策策定研究に対するダウンスケールデータのポテンシャルを示すことを目指します。
温暖化に伴いスーパー台風はどこまで強くなるのか

坪木和久
名古屋大学地球水循環研究センター
教授