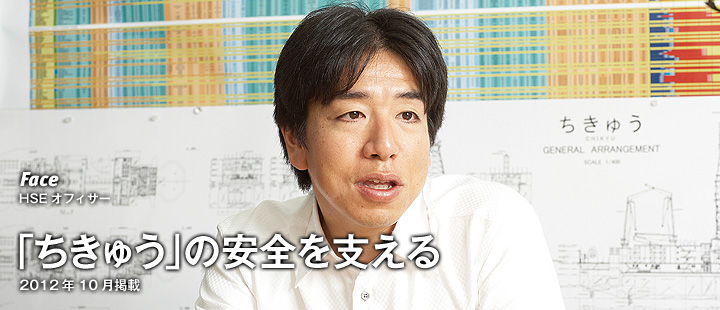
さまざまな機器を使い、ときに未経験のミッションにチャレンジする「ちきゅう」。そんな「ちきゅう」には無災害期間が1500日以上継続しているという「記録」がある。その記録を支えてきた一人、HSEオフィサーの源 穣(みなもと・みのる)さんをたずねた。
(2012年10月掲載)
| 取材協力 源 穣(みなもと・みのる) 「ちきゅう」HSEオフィサー 日本マントル・クエスト 株式会社 |
危険が一番わかる現場から、安全情報を引き上げる
「ちきゅう」には安全管理のプロが常時2人乗船している。
その一人が源HSEオフィサーだ。乗船する人々の「健康(Health)」、「安全(Safety)」、「環境(Environment)」に眼を配る。「ちきゅう」における安全管理のルールや規則が守られているかチェックし、必要に応じてそれを修正し、より安全な方法を提案していく。それが仕事だ。
源オフィサーは今までに航海士として、自動車運搬船、液化天然ガスを輸送するLNG船などの乗船経験を積み、「ちきゅう」の乗船メンバーに加わった。「ちきゅう」で行う科学掘削ではそれまでに経験してこなかった新たな手法にも挑戦しなければいけない。たとえば、2012年の春~夏に行われた「東北地方太平洋沖地震調査掘削(JFASTおよびJFAST2)」では、水中カメラシステムを「ちきゅう」史上はじめて投入した。水中「カメラ」といっても、それは掘削パイプに沿わせる大きな土管のような大型の装置である。こうした初挑戦ではどんな事故がおきるのかわからない。
HSEオフィサーはそうした危険に対して乗務員が安全に作業できるように対応策を練る。「現実的には船内のすべてを2人のHSEオフィサーで見て回るには限界があります。そこで、何が危険なのかを一番よくわかっている現場から安全に関する情報を“あげて”もらえるようにしています」と源HSEオフィサーは話す。ボトムアップの方針こそが「ちきゅう」で働く人々の安全を守っているというわけだ。
そもそも「ちきゅう」の安全規則は、世界の海洋掘削業界が定める厳しいガイドラインに従っている。民間会社が厳しいガイドラインをもっているのは、作業員が安全に作業できる環境であるほうが最終的により多くの利益が出すことができるという考えにもとづいているのだ。それは科学掘削であってもおなじことだ。

- |1|
- 2|

