領域テーマB:海洋研究開発機構
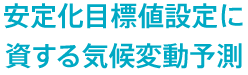
領域代表者 河宮 未知生
海洋研究開発機構 戦略研究開発領域
気候変動リスク情報創生プロジェクトチーム
プロジェクト長
海洋研究開発機構 戦略研究開発領域
気候変動リスク情報創生プロジェクトチーム
プロジェクト長
二酸化炭素濃度の予測不確実性は、気候感度の不確実性と並んで将来の気候予測を行う上で大きな障害となります。本研究テーマでは、二酸化炭素の収支、生態系、農業等の変動をより正確に予測する上で重要となる、炭素循環や窒素循環を含めた物質循環や、土地利用変化等を取り扱う地球システムモデルを開発します。研究開発の実施にあたっては、予測実験の前提となる社会経済シナリオについて科学的視点から検討します。また、目標の検討にあたっては、将来起きる可能性があるが避けなければならない事象や、回避する手段が与える影響について、把握することが重要であるため、人為起源の環境変化の度合いが一定の閾地を越えることで起こるかもしれない激変(ティッピング・エレメント)や温暖化による被害を抑制するために人為的に地球の平均気温を低下させる手法(ジオエンジニアリング)について、その影響や効果に関する新たな科学的知見を創出します。
 研究課題
研究課題
| 領域課題 | サブ課題名 | サブ課題代表者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 多様なシナリオを踏まえた長期的な地球環境変動の予測 | a | 温室効果気体濃度変動や土地利用変化等を取り扱う地球システムモデルの開発 | 海洋研究開発機構 |  ユニットリーダー 渡邉真吾 |
| b | 安定化目標値設定に向けた社会経済シナリオに関する検討・情報収集 |  ユニットリーダー 代理 立入 郁 |
||
| c | 社会経済シナリオを含めた気候予測実験の統合的評価 | 電力中央研究所 |  環境科学研究所 副研究参事 筒井純一 |
|
| 大規模な気候変動・改変に関する科学的知見の創出 | a | ティッピング・エレメントや環境変化の不可逆性(極域氷床の崩壊等)に関する数値実験技術の開発 | 海洋研究開発機構 |  プロジェクト長 河宮未知生 |
| b | ジオエンジニアリング(成層圏エアロゾル注入等)に関する数値実験技術の開発 | |||
