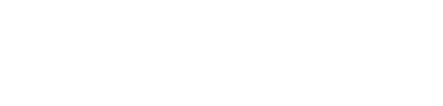「しんかい6500」研究航海 YK18-08 レポート
YK18-08調査潜航
2018/6/25 - 7/7
『YK18-08航海レポート』
今回の調査は、6月25日から7月7日にかけて、2つの研究課題について実施されました。
調査前半では、「たいりくプロジェクト」による西之島周辺海域での潜航調査を実施しました。西之島周辺の海底地殻の浅い火山では、大陸地殻を形成する安山岩マグマを噴出していることが、今までの調査で明らかになっています。
昨年7月に実施した「よこすか」ディープ・トウの調査(YK17-14 Leg.1レポート参照)に続いて、今回は「しんかい6500」で西之島の北側に位置する土曜海山で詳細な潜航調査を実施し、「地殻の薄い海洋島弧においてのみ大陸がつくられる」という大陸生成仮説を検証する目的で調査が行われました。
6月25日小笠原諸島父島の二見港で研究者が乗船し、土曜海山向け発航しました。調査海域である土曜海山までは、父島から西北西に距離約160kmと近く、夕刻前には調査海域に到着するため研究者乗船後、直ちに翌日の潜航準備や研究者との打合せ、潜航研究者へのブリーフィング等、慌ただしく準備が進められました。
潜航日の6月26日と27日は勢力の強い太平洋高気圧に覆われ、良好な海況の下、計画通り土曜海山の北西側斜面で1回、東側斜面で1回の調査潜航を実施しました。
何れの潜航でも順調な海底観察が行われ、研究者が目的とした岩石試料が大量に採取されました。その岩石試料には予想外の興味深い岩石も採取されたとのことで新たな研究対象が加わったと潜航調査の結果について大変に満足された様子でした。
土曜海山での調査潜航が終了した6月27日、早々に南鳥島沖海域向け海域の移動を開始しました。小笠原諸島から南鳥島海域までは約1200km、「よこすか」の船速で2日半の行程です。
調査後半戦では、南鳥島海域周辺のプチスポット火山の分布、マグマ源の組成や噴出年代分布を明らかにする目的で調査が実施されました。
プチスポット火山とは、これまで知られているプレート境界の火山やハワイ島のようなホットスポット火山とは異なる新型の火山です。海洋側プレートが海溝に沈み込む際のプレートの曲がりに亀裂が入り、その亀裂が火道となってアセノスフェアからマグマが吹き出す単成火山(1回の噴火で作られる火山)だと考えられています。2006年に三陸沖日本海溝の海側プレートで初めて発見された火山ですが、その後の調査で南鳥島周辺の海底でもプチスポット火山の存在が明らかになりました。アセノスフェアから噴出する火山ということで地球深部の状態を知る手がかりになると注目されています。
南鳥島周辺海域へは、調査潜航予定の6月30日早朝ギリギリに到着することができましたが、この日の調査海域は、海況が悪く、気象予報も悪化傾向であったため残念ながら、潜航を取り止めとし、終日MBES広域地形調査となりました。翌7月1日からは、海況も徐々に回復傾向にあり、7月3日まで3連続潜航を実施しました。

写真1:初のコ・パイロット業務で緊張気味
初の潜航調査に緊張気味の飯島潜航士。耐圧殻内は、純酸素ボンベを使用して酸素を供給するため、油分の持ち込みは禁止されている。潜水船で潜航するときは、当然ノーメイク。
南鳥島海域の調査初日の海況不良により調査潜航の1回は中止となりましたが、3回の潜航については、調査の優先度が高い海域を調査することができ、何れの調査でも溶岩試料が採取され、採取した試料から火山は全てプチスポット火山だろうとの見解でした。研究者からは厳しい海況が続く中、重要な3海域の調査潜航ができ、大きな成果が得られたとお礼の言葉を頂きました。調査を終えた「よこすか」は、一路東京湾に向け、予定通り7月7日に晴海ふ頭入港しました。研究者は、今回の調査潜航で採取された多くの岩石試料と共に下船されました。
双方の調査で採取された岩石試料は、地球を知るうえでも大変貴重な試料です。今後、陸上の研究施設で詳細な分析作業が進められるでしょう。
『深海調査の現場でも女性が活躍する時代』

写真2:スイマー作業
潜水船の着水作業。貝野3/Eが、先輩スイマーの指示に従って潜水船の吊り上げ索のガイド索外しているところ、吊り上げ索を外した後は、海に飛び込み潜水船の船首に付いている主索の大きなフックを取り外し、「しんかい6500」の潜航準備が完了する。

写真3:深海調査の現場で活躍する女性たち
6月26日の「しんかい6500」オペレーションで同日にそれぞれ活躍した両名。左が女性初のスイマー作業に従事した貝野3/E、向かって右が潜水船Co.Pilotデビューした飯島潜航士。YK18-08航海では、この他に研究者1名、研究支援1名、司厨員2名の計6名の女性が、海洋調査の現場で活躍されました。
6月26日の「しんかい6500」調査潜航では、2人の女性が各々の分野でデビューを果たしました。1人は「しんかい6500」運航チームの飯島潜航士です。前回のレポートでご紹介しましたが、今回の調査潜航で初のコ・パイロット(副操縦士)業務に向けて訓練を重ねてきました。マニピュレータ操作訓練では、良いセンスを持っていると感じていましたが、今回一緒に潜航した研究者もテキパキと岩石を採取する飯島潜航士には、感心した様子でした。
この日潜航した研究者は、「しんかい6500」では10回以上の潜航経験を持つ、ベテランのクラスですが、その研究者に褒められるのは、本人もさぞ嬉しかった事でしょう。
しかし初の調査潜航、出来たこと、出来なかったこと、それを一番感じたのは本人だと思います。これから多くの経験を積んで、研究者から信頼される潜水船パイロットに成長することを期待しています。
2人目は、支援母船「よこすか」三等機関士(以下、3/Eと記載)の貝野さんです。JAMSTECの深海調査始まって以来、初の女性スイマー誕生です。スイマー作業とは、「しんかい6500」の着水時に潜水船に繋がった吊り上げ索や主索(潜水船の曳航ロープ)を外したり、また揚収時には、主索を引っ張りながら泳いで潜水船を捕まえに行き、その後吊り上げ索を勘合させる作業ですが、波やうねりが高い外洋では、とても大変な作業となります。潜水船オペレーションの要と言っても過言ではありません。
【写真2】は、6月26日初コ・パイロットの飯島潜航士が乗った潜水船の上で着水作業を行っている貝野3/Eです。先輩スイマーから指示を受けながら作業を進めますが、初めてのスイマーにしては、落ち着いた流れで作業が進みました。良い素質を持っています。これからも技量を磨いて、頼りになるスイマーに成長することを期待します。
同日の潜水船オペレーションで2人の女性が活躍する!深海調査の現場にも新しい風が吹き始めたことを感じた1日でした。
【潜航情報】
-
6月26日 No.1518DIVE
- 潜航海域:土曜海山
- 観察者:石塚 治 (JAMSTEC)
- 船長:千葉 和宏
- 船長補佐:飯島 さつき
-
6月27日 No.1519DIVE
- 潜航海域:土曜海山
- 観察者:田村 芳彦(JAMSTEC)
- 船長:鈴木 啓吾
- 船長補佐:千田 要介
-
7月1日 No.1520DIVE
- 潜航海域:南鳥島沖
- 観察者:秋澤 紀克 (AORI)
- 船長:大西 琢磨
- 船長補佐:千葉 和宏
-
7月2日 No.1521DIVE
- 潜航海域:南鳥島沖
- 観察者:町田 嗣樹(千葉工業大学)
- 船長:千田 要介
- 船長補佐:鈴木 啓吾
-
7月3日 No.1522DIVE
- 潜航海域:南鳥島沖
- 観察者:浅見 慶志朗 (東京大学大学院)
- 船長:大西 琢磨
- 船長補佐:松本 恵太
【航海情報】
- 6月25日
- 研究者14名乗船、運航チーム1名下船(二見港手配の通船)
研究者乗船後、調査海域向け発航(西之島周辺海域、土曜海山)
研究者向け船内安全レクチャ、潜航研究者ブリーフィング
調査海域到着、XBT計測、MBES広域地形調査(事前調査含む) - 6月26日
- 調査潜航(第1518回)、MBES広域地形調査
- 6月27日
- 調査潜航(第1519回)、8の字航走実施、南鳥島沖海域向け発航
- 6月28日
- 南鳥島沖海域向け回航、時刻改正(船内時計1時間前進JST+1h)
- 6月29日
- 南鳥島沖海域向け回航
- 6月30日
- 調査海域着、XBT計測、MBES事前調査
海況不良で調査潜航取り止め
プロトン磁力計投入、MBES広域地形調査及び地球物理探査
延縄漁船が確認されたためプロトン磁力計揚収 - 7月1日
- MBES事前調査、調査潜航(第1520回)、プロトン磁力計投入
MBES広域地形調査及び地球物理探査 - 7月2日
- プロトン磁力計揚収、調査潜航(第1521回)
プロトン磁力計投入、MBES広域地形調査及び地球物理探査 - 7月3日
- プロトン磁力計揚収、調査潜航(第1522回)、晴海ふ頭向け発航
- 7月4日
- 晴海ふ頭向け回航
- 7月5日
- 晴海ふ頭向け回航
- 7月6日
- 晴海ふ頭向け回航、8の字航走実施
- 7月7日
- 晴海ふ頭入港、研究者14名下船
櫻井 利明(運航チーム司令)