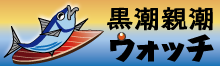APLコラム

山形俊男
アプリケーションラボ 所長
今年の冬はエルニーニョ現象というのに、
どうしてこんなに寒いのでしょう?
気象庁の発表では、今年の冬はエルニーニョ現象が発生しているそうですね。こういう時の日本は、いつもより暖かくなると聞いていましたが、どうしてこんなに寒いのですか?
日本の冬は、熱帯の海の水温や極域の方の大気の様子など、いくつかの要因で決まりますが、今年の冬は熱帯の海で起きている現象が関係しているようです。
それはどんな現象ですか?
まず、今年の1月の海面水温が平年からどれくらいずれているか見てみましょう(図1)。赤道太平洋の日付変更線付近で、海面水温が平年より高くなっていますね。
たしかに。こういうのをエルニーニョ現象というのではないのですか?
エルニーニョ現象ならペルー沖でも海面水温が高くならないといけないのですが、むしろ低いですね。これは、エルニーニョ現象ではなく、エルニーニョモドキという現象なのです。
エルニーニョモドキ? 面白い名前ですね。どんな現象か説明していただけますか?

この現象は私たちが名付けて発表したものですが(注1)、今は世界の気候研究者がこぞって研究しています。エルニーニョモドキ現象が発生すると、西太平洋のインドネシア付近にある大気の上昇域が東にずれて、日付変更線付近に移動します。
熱帯の上昇域で励起された大気の渦の波動が(ロスビー波といいます)、遠く離れた極の方に向かって伝播して(テレコネクションといいます)、中緯度上空の偏西風を蛇行させます。エルニーニョモドキ現象の時、日本付近では北西から風が吹き込む形になり、西高東低の冬型の気圧配置が強まって寒くなります。これは、ラニーニャ現象の時に似た状況と言えます。
中緯度で偏西風が蛇行するのは、エルニーニョ現象でも見られますよね?
はい、エルニーニョ現象でもエルニーニョモドキ現象でも、偏西風の蛇行は起きます。しかし、蛇行の谷と峰の位置が大きく異なります。エルニーニョ現象の時には、日本付近では南西から風が吹き込む形になり、冬型の気圧配置が緩んで暖かくなります。
テレコネクションというのは難しいですが、分かったような気がします。このエルニーニョモドキ現象は、いつまで続きそうですか?
アプリケーションラボでは、天気予報に用いられているのと同じような大気の大循環モデルと海の海流変動予測に使われる海洋の大循環モデルを結合した気候変動予測システムを、2005年に完成させました。それを改良しながら毎月2年先までの季節予測を行っています(注2)。
今年1月に行った予測実験によれば、熱帯のエルニーニョモドキ現象は少なくとも初夏ごろまでは続くようです。その世界各地への影響は季節の進行との関係で変わりますが、今後も熱帯域の海面水温の様子に関心を持ち続けてください(注3)。特に、春に寒気が入ると時ならぬ大雪になったり、爆弾低気圧が発生したりしますので、注意が肝心ですね。

図1 2015年1月の海面水温の異常値(IRI Map Room(注4)より)。暖色が平年より暖かく、寒色が冷たいことを示す。

図2 2015年1月時点で予測した、2015年6-8月の海面水温の異常値(SINTEX-Fモデル(注2)より)。暖色が平年より暖かく、寒色が冷たいことを示す。
- 注1:
- http://www.jamstec.go.jp/frcgc/research/d1/iod/elnmodoki/about_elnm.html
- 注2:
- http://www.jamstec.go.jp/frcgc/research/d1/iod/seasonal/outlook.html
- 注3:
- http://www.esrl.noaa.gov/psd/map/clim/sst.shtml
- 注4:
- http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/ENSO/SST_Plots/Monthly_Anomaly.html
(山形俊男)