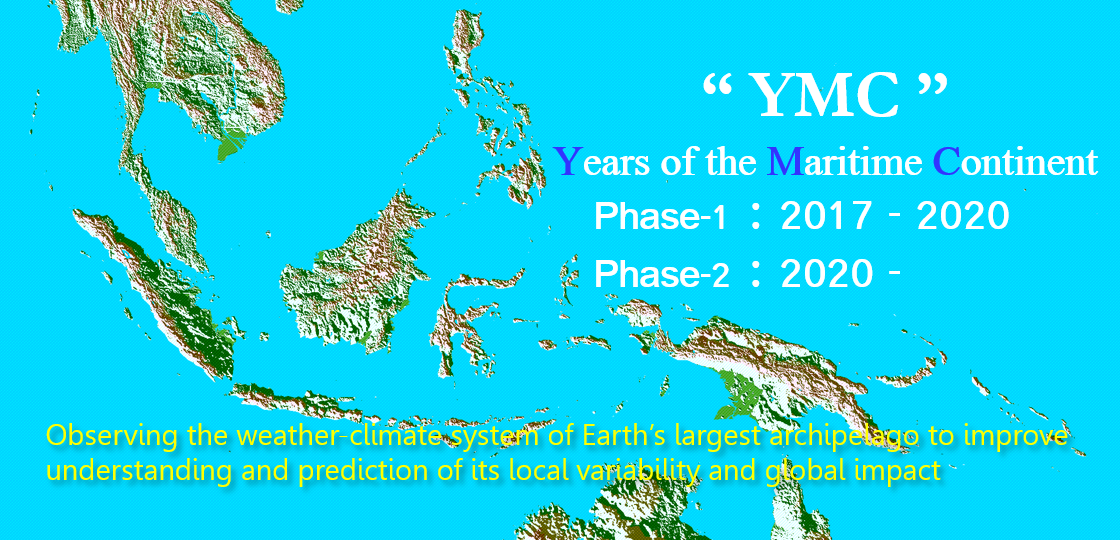|
|
13 Nov. 2015: Miraiいよいよ太平洋の「端」が近づいてきました。本日を以って「みらい」の観 測は一旦終了です。 ……といっても観測航海が終わるわけではありません。最近ニュースで取り 上げられることも多いですが、排他的経済水域(EEZ) (昔は「200カイリ」なんて 呼び方もされてましたね) に進入する為です。 このEEZの中で何らかの活動(例えば、今回の我々のような科学調査)をするた めには、事前に相手国に申請しておく必要があります。今回の航海はインドネシ アEEZ内での観測が主目的であるため、このEEZ内観測許可申請をインドネシアに 申請しました。一方、今回の航路上には、約半日ほどフィリピン(かパラオ)の EEZを通過する必要があります。この海域は今回の科学目的からは外れており (いや面白いんですけど、次の機会に……)、かつ通過には僅かな時間しか要し ないので、今回は申請を見送りました。結果、フィリピンのEEZ内では、観測機 器を全部止めた「無害航行」としてしずしずと走ることになります。 写真は、フィリピンEEZ進入直前の夕暮れ。雲は極めて少なく、細い月が沈んだ 後には星空がよく見えました。漁船もちらほら。同じ海の上で同じ星を見て、向 こうの乗組員の方はどんなことを考えているのでしょうね。 フィリピンのEEZを抜けたら、いよいよインドネシアのEEZ。そちらでの観測再開 の様子は、また後日ご紹介します。
13 Nov. 2015: Bengkulu一般に熱帯陸上では,一日のうちで雨が降りやすい時間が場所ごとに決まっています。例えば内陸部では,太陽によって地表面が暖められて上昇気流が発生しやすくなる午後から夜半にかけて最も雨が降りやすくなります。一方でベンクルのような沿岸域では,内陸部の特徴と海上の特徴が混在するため,海岸からの距離によって降りやすい時間が異なるなど,複雑な特徴を示すことが知られているため,今回の集中観測のターゲットのひとつに挙げられています。 ベンクル入りして10日ほど経ちますが,(少なくともこの季節は)観測所や滞在先のホテルの周辺では内陸部と同じように夕方から夜半にかけて雨が降りやすいことがわかってきました。今日は観測所で午後4時からの1時間に33mmの雨が観測され,その直前から気温が4度ほど下がりました。 午後から夜半にかけて突然数十mmの雨が降る,というと,日本の夏のいわゆるゲリラ豪雨を彷彿とさせます。雨をもたらす積乱雲ができる条件は少々異なるかもしれませんが,日本の夏はある意味で熱帯的だと言えるでしょう。熱帯の雨の研究は,日本の雨をより詳しく理解することにもつながっているのです。 今日の雨は観測所から見える風景がいちめん白く煙るほどの大雨でしたが,近くの空き地では地元の男の子たちが何も気にすることなくサッカーを楽しんでいました。私も雨天での観測の度に雨合羽を着るのが馬鹿らしくなってきました。どうせ濡れても何の問題もない作業着,次からは雨を気にせず観測することにします。(ゾンデ観測自体は,実は雨を気にしつつ行わなくてはいけません。詳しくは別の機会に)
|