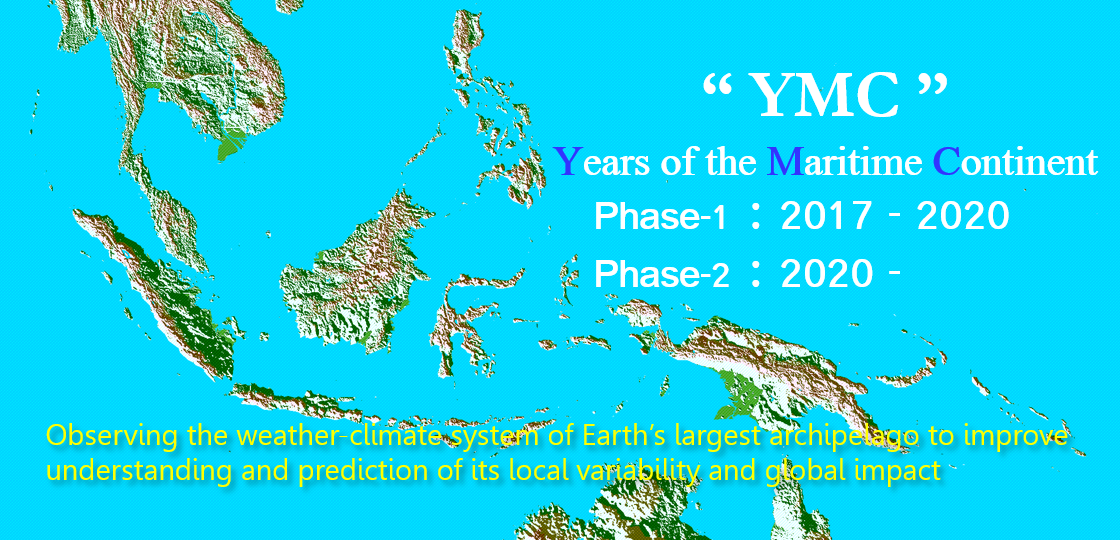|
|
13 Dec. 2015: Miraiスターウォーズの新作がそろそろ公開ですね。船内でも「下船したらすぐ見に行 く!」という方がいます。で、本日は、フォースじゃないですがブライトとダー クの話。 図は、「みらい」に今載っている異なる機材で測った雨雲の鉛直断面(かそれに 類するもの)で、発射した電磁波が雨粒や雲粒に当って反射してきた電波の量 「反射強度」をプロットしています。カラースケールはバラバラですが(ごめん なさい)、どれも、暖色系が、反射してきた電波がより多い、ということを示し ています。雨なら、反射してきた電波が多いということは、つまり雨がたくさん 降っていることを示しています。 実はケースもバラバラで大変申し訳ないのですが、どのプロットも「層状性降水 域」というものに分類されます。これは、スコールのような雨ではなく、しとし ととした雨が降り続くような状況です。こういう雲では、上空でできた雪が落ち てきて、気温0度の高度で融け、そこから下では雨になって地上(海上)へ落ちて いく、ということが起こっていると言われています。熱帯だと気温0度になる高 度はだいたい5kmです。それぞれの図では、高度4?6kmに該当する部分を赤点線 で囲みましたが、だいたいその点線の中の特定の高度あたりで、雨の映り方が違っ ているのが判るかと思います。 さてここで問題になるのが、気温0度付近の映り方です。一番下は「みらい」の レーダー(5GHz)の観測結果で、0度付近は値が「高く」、つまり強い電波が跳ね 返ってきています。電波が強い、つまり光に置き換えると「明るい」ことから、 レーダー関係者の間では「ブライトバンド」と呼ばれます。 さて一方似たようなところを、別センサーで見てみましょう。中段は、JAXAのレー ダー(35GHZ)の観測結果です。図の左側では、特定の高度を境に反射強度が強く なっています。しかし、真ん中あたりから右側では、一旦反射強度が弱くなって いる場所があります。これ、「ブライトバンド」の逆で、「ダークバンド」と言 います。 更に別の波長で。今回の航海には「ライダー」という、レーザー(可視光)を使っ てレーダーと同じ測定を行う機材も積んでいます。このデータでは……上から順 番に、一旦「ブライトバンド」が見えて、その下に「ダークバンド」が見えて、 更にその下が、より下層の雨が映っている、そんな様子が見えています。 同じような場所では同じような現象が起こっている筈なのに、どうして映り方が 違うのか? 理由は少々ややこしいのですが、一般的に2つの原理があります。 まず、水の方が氷よりも電波をより強く反射します。また、より大きい粒の方が 電波をより強く反射します。両方を踏まえて、0℃付近で起こっていることを考 えてみましょう。まず、密度が小さい(=スカスカ)だけど大きさだけは大きい雪 が落ちてきます。これが0℃層を通る際、空気に触れている外側から融けます。 その際、外側だけが水となり、中にスカスカの氷が残っていることで、外見上 「大きな水滴」に見えるタイミングがあります。この「見た目だけは大きな水滴」 が、電波をたくさん反射し「ブライトバンド」を作る要因となっていると考えら れています。で、その下では、雪が全部溶けて水=雨粒になってしまうと、中の スカスカさがなくなる為、粒の大きさが小さくなり、再び反射する電波の強さは (ブライトバンドに比べて)弱くなる、という理屈です。また、使っている電波の 波長が違うと、よく見える粒の大きさが異なるため、ブライトバンドの出方も変 わります。 ではダークバンドは? ……話が長くなりすぎてしまったので、ダークサイドの話は、ここでは秘密にし ておきましょう。興味のある方は、ブライトサイドとダークサイドを良く知る 「科学」の「フォース」を身につけて、是非我々と一緒に観測研究にご参加くだ さい。May the force be with you.
13 Dec. 2015: Kototabangパダン料理 以前のベンクル班からの記事(11月29日)にありましたが、パダン料理の本場に滞在中のコトタバン班です。 先ずは、本格的なパダン料理店のスタイルを紹介します。2名で店に入り、案内された席に着くやいなや、写真(上)のように16皿の料理と白米と辛味調味料の皿がテーブルの並べられました。この他にも食べたい料理がある場合は、注文すれば出てきます。食べたいものにだけ箸をつけて、その分の料金を支払うのは、以前の記事のとおり。写真(中)が食後の様子です。我々は5皿に箸を(正確にはスプーンとフォークを)つけました。料理の名前(インドネシア語が聞き取れない)どころか、何(どのような食材)を調理したものかがわからない料理もありましたが、どれも美味しかったです。 別の小さなパダン料理屋では、入口に並べられた料理の大皿とボウルから、食べたいものを指定して配膳してもらうスタイルです。写真(下)が昨日の昼食です。メニューは、香辛料をまぶしたチキン、ナスの素揚げ、小魚のから揚げ、キャッサバの葉のカレー、だったと思いますが確証はありません。なぜか、一人に2皿(2名で4皿)の白米が出てきました。調理された品が素早く供されて、食事に時間を取られないので、パダン料理は時間に追われる観測に向いているのかもしれません。
|