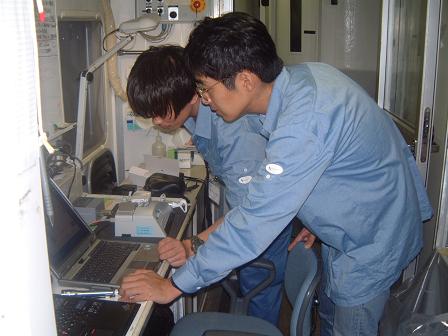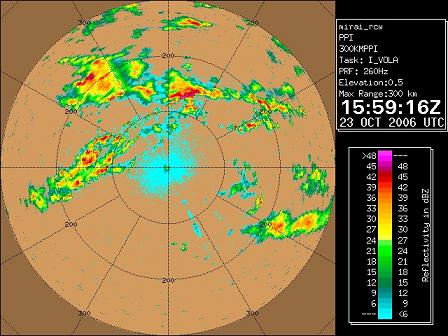■MISMO 集中観測 日報
|
|
|
10月23日(月)
「みらい」
"北緯3度で南下"
曇りのち晴れ
観測概況:
東経80度線を北上し、アルゴフロートを北緯0度30分、1度15分、3度
の3点に投入し、今航海で投入予定の計12台をすべて無事投入した。
10台は浮上間隔を1日に設定しているため、既に浮上(観測)を行った
フロートもあり、陸上にてデータ受信を確認できている。
北上途中、係留系設置予定付近にて、昨日同様、音響測深による
海底地形の確認作業が実施された。また、北緯1度30分、東経80度
30分に設置された米国のアトラスブイの被害状況を確認するため
近くを航行し、目視点検を実施。
大気の一般場を計測するラジオゾンデ観測も3時間間隔で実施され
ている(写真1)。ラジオゾンデはバルーンに取り付けたセンサーにより
気圧、温・湿度、風向・風速を高度25km付近まで計測する装置である。
データは、この航海の目的であるMJOを対象とする研究だけでなく、
観測終了後、直ちに気象庁経由で世界中の気象機関に配信され、
日々の天気予報など、さまざまな用途でも用いられている。
普段はラジオゾンデ観測は一人ですべての作業が行われるが、最初
の数日だけ、作業内容を確認しながら数名で実施している(写真2)。
コメント:
昨日の雨がすっかり消えたが、すっきりしない空に覆われる。
人工衛星による雲画像からは、MJOのピークがインド洋のどの辺り
にあるのか、まだ判断が分かれる。
降雨の中で実施されるビデオゾンデ観測のチャンスをうかがうが、
レーダーエコー(図1)には、100kmほど船からは離れていて、直上
に発達する降水システムは観測されなかった。
観測が本格化し、気象関係者はドップラーレーダー室に集まりデータ
を見てはエコーが今後成長するしないと話題にし、係留系関係者は
ブイ調整室やデッキなどで明日からの作業に備える。
24時間観測体制では、ワッチと呼ばれる観測体制が引かれ、時間
単位で作業時間を区切り、適宜交代しながら作業を連綿と実施して
ゆく。
「みらい」は現在、北緯3度で最後のアルゴフロートを投入後、進路
を南に戻し、係留系の設置点へと航走中。