成長期の「みらいⅡ」とマニアックな(?)パーツたち (北極域研究船の建造状況 Ⅳ)
2024年11月22日
北極域研究船推進部 建造チームとCOMAI先生
みなさんこんにちは、北極域研究船推進部 建造チーム(とCOMAI)です。
11月の初めに、つーちゃんに内緒で造船所の「みらいⅡ」の様子を見てきましたので、今日はその報告をします。船体ブロック以外にも少しマニアックなパーツも撮ってきました。
見てきた時点でのブロック搭載は、全85のうち36まで進んでいました。
年内にどこまで進むか楽しみですね。楽しみですね…

あと、恒例の10月までの建造の様子はギャラリーにアップしていますので、併せてそちらもご覧ください。
https://www.jamstec.go.jp/parv/j/gallery/?period=202410
さて気を取り直して、船体ブロック搭載の様子から。

まず船橋(ブリッジ)からF甲板までの上部構造物ですね。ドップラーレーダー室も見えますが分かりますか?
こちらは同じ甲板を後ろから。ブリッジは、完成予想図とほぼ同じ形状を既に見ることができて感動(涙)

今度は建造ドック正面から見渡してみました。奥にはブロック搭載中の下部構造物が遠く見えます。写真では伝わりにくいですが、迫力満点のお顔(つーちゃんに怒られそう)。

船橋横のウイングは、操船や観測などのために眺めが良くなるよう配置。ウイングには真下の海(氷)面が観察できるよう窓が設けられますが、位置は分かりますか?「みらいⅡ」のちょっとした名所になるかもしれません…

ヘリコプター格納庫のブロックも進んでいました。写真は庫内側から見ていますが、向こう側にはシャッターが付きます。

続いては船尾からの眺め。


左右の舵を吊るためのラダーホーン部と、プロペラ軸を通すためのボッシング構造が見えますね。高速カーフェリーのような多軸船ではプロペラ軸は張り出し(シャフトブラケット)軸受けで支持され露出している場合もありますが、「みらいⅡ」は砕氷船ということで、氷から守るためにプロペラ軸をボッシングで覆ってしまいます。
また、ラダー基部の後部に角のようなものが見えますが、後進時に氷が舵にぶつかるのを防ぐためのアイスナイフと呼ばれる構造です。
巨大すぎて渠底で側面を撮影するのが難しい。


船尾から船首まで、下部構造についてはほぼ搭載されていました!そびえたつ砕氷船首!


船尾側から渠底を眺める(絶景かな)。上からじゃないと全体が入りません。

船体側の様子は、この謎の部位でオシマイにして次行きましょう(ヒント:ムーンプール内の何か)。

ここからは、需要があるかナゾですが、普段あまり紹介していない少しマニアックなパーツをいくつか紹介。
これはムーンプールハッチですね。左が船上側、右が船底側ですが、船底側写真の上には開閉シリンダーを取り付けるための基部が写っていますね(つまりハッチの内側)。

これは作業艇「しろくま」のダビッド(昇降用クレーン)。写真左の奥には救命艇のダビッドも見えます。右の写真は作業艇ダビッド正面から。


こちらは船上クレーン竿受け(支え)たち。クレーンを使用しないときはこれでクレーンを支えます。受けの木部は摩耗や劣化してきたら取り替えることができます。

水密扉たち。真ん中にテープ留めされている銀色の筒は開けづらいときに使用するハンドルサポート具(ハンドルに被せて回しやすくする)。

外階段。分かりづらいですが、寒冷地対策として踏板がグレーチングになっています。

最後は船底の音響機器取り付け穴(深海用マルチビーム音響測深器・送波器用、長さ約9m!)でオシマイ!
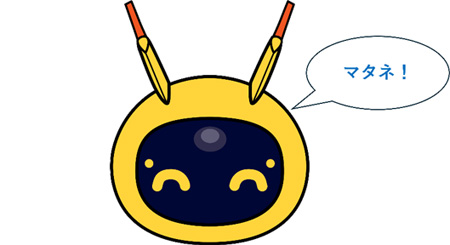
つーちゃんとCOMAI先生も登場!
「みらいⅡと行こう!北極調査隊」もぜひご覧ください!
https://youtu.be/QDN9wf9t648?feature=shared

